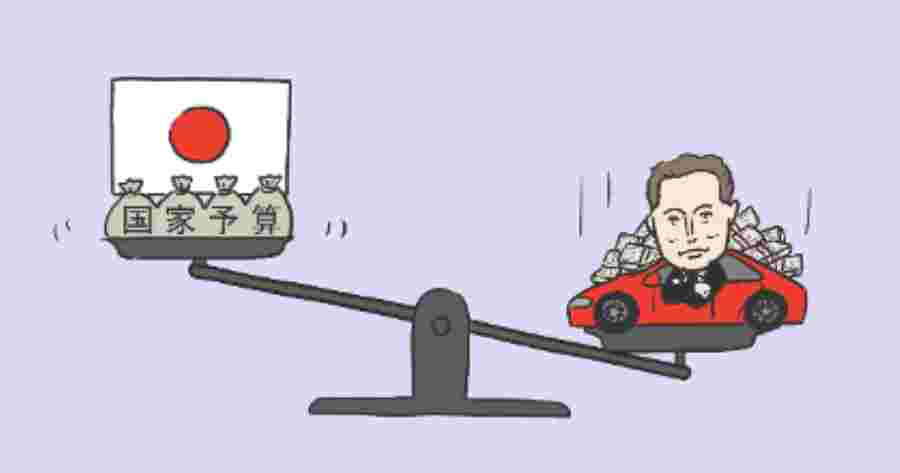第5回:病気の物語
- Erwin Brunio
- 2024年5月7日
- 読了時間: 12分
更新日:2024年6月13日
2024年5月7日

2020年10月20日から連載開始した「疫学と算盤(そろばん)」は、昨年末、通算第36回を数え無事終了しました。36回分のコラムはご承知かと思いますが、当WEBサイトにてダウンロードできる電子書籍となっています。2024年1月からは、コラム続編の「続・疫学と算盤(ソロバン)」がスタートします。筆者・青木コトナリ氏のコラムとしては、日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボのWEBサイト連載の「医療DATA事始め」から数えて3代目となる新シリーズの開始です。装いを変え、しかし信条と信念はそのままに、“えきがくしゃ”青木コトナリ氏の新境地をお楽しみください。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ氏の
「続・疫学と算盤(ソロバン)」(新シリーズ) 第5回:病気の物語
バカの壁
養老孟司さんの著作「バカの壁」をご存知だろうか。随分と以前に読んだので本文全体まではよく覚えていなかったのだが、先日読み返してみたところ冒頭のエピソードについてはハッキリと覚えていた。
それはイギリスの放送局が制作した、ある夫婦の妊娠から出産までを詳細に追ったドキュメンタリー番組を日本の某大学薬学部の学生に見せたときのエピソードである。ビデオを見た女子学生のほとんどが「大変勉強になりました。新しい発見が沢山ありました」という感想であったのに対して、男子学生は皆一様に「こんなことは既に保健の授業で知っているようなことばかりだ」という答えであったという。
氏はこのエピソードに登場する男子学生の姿勢について、自主的に情報を遮断してしまい壁が生じている、としてここに「バカの壁」をみるわけである。これをバカの壁と呼称することに賛同するかどうかは別として、情報や知識について「わかった」「わかっている」という同じ言葉であっても、その深さや感じ方には立場の違いによる差が結構あることは間違いなさそうだ。
先回は病気の「意味」を研究する分野、質的研究を広く取り上げたところである。「意味」というワードを使って上記を整理するならば、男性にとって女性ほどには妊娠・出産のリアリティを自分事として受け止めることは難しく、「意味」が違うということだろう。
質的研究は心理学や社会学、文化人類学等で発展した経緯があるが、医療の分野にあっても特に看護学分野や精神疾患系の分野では重要であり、その貢献も大きい。今回は質的研究の中でも医療分野でもよく活用されている「ナラティブ」について取り上げてみたい。
ナラティブとは
「ナラティブ(narrative)」は日本語で「物語」あるいは「語り」と訳される。少しばかりニュアンスが違うということもあってか、カタカナ表記のままとすることも多い。
研究のカテゴリというよりは研究の中にあってはパーツ(部品)、あるいはコンセプト的なニュアンスである。ナラティブを主たる成果物とするような研究を総称してナラティブ研究と呼称することもあるが、むしろその方向性を意識しナラティブ・アプローチと呼称したり、その調査にインタビュー形式を用いるならばナラティブ・インタビューと呼称したりする。
先回紹介した通り質的研究のインタビューには、個別インタビューと主たる対象の人たち複数に集まってもらって行うフォーカスグループ・インタビューなどがあるのだが、その回答が「語り」ということであればそれはナラティブ・インタビューということになる。また、フォーカスグループ・インタビューとして集団に対して「語り」をしてもらうことをグループ・ナラティブと呼称することもある。
医学系でナラティブの研究といえば、その対象はおよそ患者さんということになるだろう。病気の告知を受けたときの心情、痛みの辛さ、休職や退職という苦渋の選択、家族への迷惑、死への恐怖等々を患者さんの言葉で自由に語ってもらう。また、患者さんだけではなくその家族に「患者さんの家族として」語ってもらうということもある。罹病者が幼少であったり、あるいは認知症が進行したりしていれば病気の「語り」の最重要人物ともいえよう。
また、患者サイドのみならず医療提供者に語ってもらうということもある。これは特定の患者さんについて語ってもらうということだけではない。医師の過重労働や看護師のバーンアウト(燃え尽き症候群)などは社会課題であり、こうした課題解決のために「主役」として医療提供者に語ってもらうというナラティブ・アプローチもある。むろん、こちらは医療系というよりもむしろ社会学系の研究と言った方がよさそうではある。
ナラティブ・ターン
ナラティブ・アプローチが脚光を浴びたのは20世紀の後半であり、案外とその歴史は浅いのであるが、これを「ナラティブ・ターン」と少々大げさに(?)呼称することもあるらしい。「ターン(展開)」というのであるからレボリューション(革命)、とまでは言わないが一大転機ということであり、その引き金として少なからず量的研究に対する批判という側面が垣間みられる。どういうことか、少し整理してみよう。
医学系研究の主流である研究(量的研究)においては、そもそも患者さんに問うということ自体が珍しく、質問に対する回答者は大抵、医療者である。たまに患者さんへ質問ないしはインタビューを試みるとしてもその質問項目は定式化されており、集計しやすいように選択肢が設けられていることも多い。これは欠点ということではなく、バイアスを排除したりわかりやすい集計を簡単に行ったりするうえではむしろ科学的で合理的でもある。
しかしながらその一方で、それではあまりに研究者主体であって肝心の患者さんがおざなりではないか、という批判がある。実際の“弊害”として例えば、患者さんが訴える副作用と医療者が認識する副作用とでは、特に精神疾患系等において大きな隔たりがある、といった研究が知られており、患者さんの声をどのように生かすかというのは量的研究においても課題でもある。
インタビューをする側が“独りよがり”になるという話は研究だけに限定するものではないだろう。未熟な新聞記者さんの中には既に記事の構成を作り終わっていて、インタビューする際にはそれにフィットするように仕向けようとする人もいる。また、回答者の側が丁寧に「語り」をしたとしても、「要するにどういうことですか」と、短絡的で残念な問いかけをすることもある。
医学研究やすべての新聞記者がこうであるということでは全くないのだが、こうしたことは起きえる“事故”ともいえよう。これでは質問者が主体で回答者が客体という、あべこべ状態である。ナラティブ・ターンが起きたのも当然の帰結といえなくもない。
健康と病の語り
ナラティブ・インタビューでは質問者はオープンな問いかけを心掛け、決して話の腰を折ったり、自分の言葉で要約したりはしない。もちろん、あらかじめ質問のフォーマットを決めておくようなことしない。ある意味、事前準備がほとんど不要なので量的研究と比べたら楽ちんでもある。
一方で、本音を語ってもらううえでは信頼関係が大切であり、こちらの準備には大いに時間と手間を割くことになる。例えば患者さん団体の中に研究者が身をおく、といったエスノグラフィー研究の一環としてナラティブ・アプローチがとられることも多い。
自由に語ってもらうためにインタビューに要する時間も設定しない、その結果については要約するのではなく、語りのすべてを成果物として文字起こしするというのが基本だ。また、患者さんが了解してくれるのであれば、語りを活字にするだけではなく、その声を録音したり、インタビュー画像を保存するということもある。さすがに論文としてまとめる際には制約があり、相応の文字数以内の活字だけになってしまうのは致し方ないところではある。
さて、論より証拠。具体的にどういったナラティブがあるのかを知りたい人はDIPEx(デイペックス~健康と病の語り~Database of Individual Patient Experiences)の日本語サイト*が参考になるだろう。こちらのサイトは文字だけではなく音声や動画も含まれており貴重な資料の宝庫といえる。私たちが「意味」を知るうえで発話者の表情や声のトーン、抑揚も貴重な情報となる。ここで得られる情報が「質」という面で、端的に言えば医療者ではなく患者さん本人の視点という点で量的研究とは異なるということが実感されるだろう。また、日本人が対象であることも重要だ。病気の受け止め方については冒頭の男女差のように文化や価値観による影響が大きい可能性があり、海外で得られた「ナラティブ」を日本人にも一般化することが難しいことが想定されるためだ。
得られた情報を生かす
私のように、これまで量的研究、つまりA治療とB治療を比べてどちらが統計学的に優れるのだろうか、といった世界に染まっている者にとってはナラティブの世界観には戸惑いもある。「そもそもこれは研究なのか」というところにも引っ掛かりがある。
前回紹介したように質的研究は「それが成すところの意味を知る」ことがパーパス、主たる研究動機である。一方、医療というものは極めて実学的であり、つまりここから何が医療として得られるのかと発想するのが常である。故に量的研究者はナラティブからまずは仮説を生成し、それを量的研究で検証するといった“バトンパス”を受けることで社会に還元することを考えてみるのが基本スタンスとなろう。ナラティブからの知見は、例えば以下のような視点が医療情報として貢献するだろう。
疾患定義をより適切なものに是正する
よりよい治療アプローチの仮説を生成する
(治療とは別に)よりよい患者さんとのコミュニケーションにヒントを得る
治療満足度やQOLをアウトカムとした研究デザインの策定に用いる
政策決定や診療報酬の改定をするうえでの参考情報とする
感染ルートの特定など、罹患の機序に関するヒントを得る
ただし量的研究の場合は、その洞察に際しては基本的に生物統計等の数字が得意な専門家がナビゲート-推定値の信頼区間や有意差検定の結果を示す等―してくれたりもするのだが、ナラティブの場合は生物統計家の力は不必要であるし、決してナビゲートしてくれたりはしない。独りよがりの思い込みを排除するうえでは、混合研究(質的研究+量的研究)として生物統計家を巻き込むというのも良策である。
研究の限界と留意事項
私は医療現場から得られる医療データを使った研究をする機会がこれまで多くあったのだが、基本的にはそのデータが正しいものだというスタンスで向き合ったことがない。レセプト病名などは最たるもので、徹底的に疑ってかかった方がむしろ正しい研究が出来るというものである。また、医療者の専門力や態度、観察眼に差異があったり、処方された医薬品が実際には(飲み忘れも含めて)処方されていない可能性にも配慮したりもする。ナラティブ研究の結果を用いる際も留意事項もこれと同様であり、語られていることが真実だけであるという想定はしない方がいいだろう。
そもそも自身が患者として語る立場となったことを想像してみるとよい。私たちは誰もがその候補者のハズだ。思い込み、物忘れ、見栄、プライド、羞恥心、他者への配慮等々。治療にくじけそうなのに虚勢をはってみたり、夜尿症のような恥ずかしい症状は語らなかったりすることだろう。あるいは医療者に対して不満があっても、医療者批判をしたくないために “隠ぺい”するかもしれない。ナラティブ情報を適切に解釈しようとするならば、こうした“人間らしさ”を適切に洞察しなければならないのである。
ナラティブに対する哲学的論考
普段、量的研究をしている人にとってみれば、量的研究=客観的指標、質的研究=主観的指標、と整理しておけば実用面においては恐らく困ることはない。しかしながらこうした単純な二元論は本質的でなく、ある意味において間違っているともいえる。この点を理解するうえでは少しばかり哲学の世界に足を踏み込まなければなるまい。
量的研究の背景にある哲学は論理実証主義に紐づいているといえる。20世紀の前半に創設された思想家集団ウィーン学団は「論理的事実と検証可能な経験的命題だけが意味がある」として、主観的な意見や判断は意味のない命題とした。これを論理実証主義というのだが、この立場からみればナラティブ情報の多くは無意味ということになる。一方、この論理実証主義を否定したのが現象学を説いたフッサールである。
フッサールはそもそも客観とは何か、我々は自分の目や耳で見聞したものしか情報として入手できないのであるからしてそれは「主観」を通さざるを得ないということから、主観/客観という区分けを否定している。これはデカルトの「我思う、故に我あり」に通じるアプローチであり、客観とおぼしきものであっても夢幻(ゆめまぼろし)、幻想かもしれないではないかという意味で私たちは主観/客観を区別できようがないという指摘である。確かに、今、私が生きている世界は映画「マトリックス」のようにすべてが虚構であるという可能性を否定できるような科学的根拠はない。
現象学は物事についてそれが私たちの認知能力によってどのように作り出されるのか、その過程を理解し探求する学問である。例えば目の前に医者からもらった薬があるとしよう。これを「客観的に目の前に薬がある」とはせず、自分の視覚を通じて、自分の中で「目の前に薬がある」という現象が作り出される、といったニュアンスである。自分の中で現象が作り出されるのであるから、体温が38度であるといった客観のようなことと、身体がだるくてしんどい、という主観のようなことにそのベースとしては区別がない。(実的内在/構成的内在という整理についてここでは省略する)
このようにしてみると量的研究であっても質的研究であっても、どちらも思い違いや勘違いを含みつつ、一方で患者さん自身が「そのように理解した」「そのように認識した」ことは事実なのであり、現象学の視点でみるとナラティブ情報は量的研究における客観的指標とは明確な違いがあるとは言えないのである。また、質的研究の結果であろうが、量的研究の結果であろうがそれを受け止める研究者サイドの主観をもってその研究結果を受け止める以上、フッサールによるとそれは純然たる「客観」とは言い切れない、ということでもある。
わかっている、とは何か
さて、「あなたは認知症のことをわかっているのですか?」という問いかけがあったとしよう。冒頭の妊娠から出産にいたる動画の理解と同様、「わかっている」と表現される状況とは一体、どのような認識レベルなのかというのは、哲学分野をも巻き込む概念である。もしこれが主治医から患者の家族であるあなたに向けて発せられた言葉としたらどうだろうか。一方、もしこれが患者の家族であるあなたが医師に向けて発した言葉であったならばどうだろうか。
認識する、理解する、解釈する、、、。認知や解釈、理解といった概念はこれまで多くの哲学者を悩ませてきたテーマであり、短いコラムでは哲学的論考を到底、消化しきれそうにない。とりあえず哲学シロウトの私たちは「わかっているのか?」という問いかけについては常に「わかっていないです。」と答えておけば角も立たないだろう。また、自身が知らないということを知っている(無知の知)、ということであればソクラテスも褒めてくれるに違いない。
「続・疫学と算盤(ソロバン)」第5回おわり。第6回につづく
*DIPEx (Japan Database of Individual Patient Experiences、健康と病いの語り)