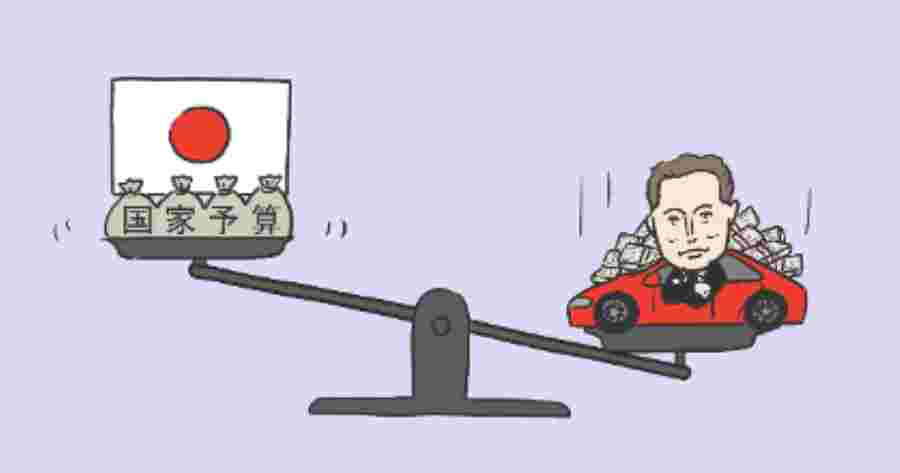第6回:オートエスノグラフィー
- Erwin Brunio
- 2024年6月13日
- 読了時間: 14分
更新日:2024年7月16日
2024年6月13日

2020年10月20日から連載開始した「疫学と算盤(そろばん)」は、昨年末、通算第36回を数え無事終了しました。36回分のコラムはご承知かと思いますが、当WEBサイトにてダウンロードできる電子書籍となっています。2024年1月からは、コラム続編の「続・疫学と算盤(ソロバン)」がスタートします。筆者・青木コトナリ氏のコラムとしては、日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボのWEBサイト連載の「医療DATA事始め」から数えて3代目となる新シリーズの開始です。装いを変え、しかし信条と信念はそのままに、“えきがくしゃ”青木コトナリ氏の新境地をお楽しみください。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ氏の
「続・疫学と算盤(ソロバン)」(新シリーズ) 第6回:オートエスノグラフィー
墓参り
先日、会社の同僚数名と一緒に墓参りに行った。千葉県の郊外にあるその墓地は、そもそも最寄りの駅からして都心のような人ごみもなく自然に溶け込んでいて心と身体がリフレッシュされるようでもある。
私自身は信心深さのカケラもなく、神も仏も信じているわけではないのだが、こうして墓参りに行くことは肯定的にとらえている。何より当人を思い出せるよい機会であるし、このところのリモート就業時代にあっては、会社の同僚とプライベートで会うという機会としてもまた貴重でもある。
亡くなった彼女とは10年ほど同じ部署にて、私が彼女の上司という関係でご一緒させて頂いていたのだが、彼女が亡くなったのは組織変更があって、別々の部署になって間もないときのことであった。
上司の立場だったので彼女の病気、乳がんのことは以前より私も認識はしていたものの、乳がんという領域の医学的進歩は他の領域と比しても目覚ましく、治療成績が向上している領域の1つである。彼女も私もその領域の医薬品メーカーで働いていることから知識量も多く、私自身、彼女の病気についてはどこかしら「どうということはない」と思っていたし、そう思いたくもあった。
何より彼女はその病状の進行については私に話さなかったし、向上心がとても高く、むしろ「病気を理由でチャレンジ性の高い仕事にアサインしないという判断は絶対にしないでください」といつも言っていたことを思い出す。彼女が生前にどんな思いで働いていたのだろうかとか、もう少し私の方で親身になって病状のことを共有しておいた方がよかったのだろうかとか、そんなことを思ったりもする。
彼女の心情をもはや聞くことはできなくなったのだが、ほんの少しだけ似たようなケースを知っており、今回はその物語(ナラティブ)を紹介しようと思う。質的研究がどうの、といった説明とは別に、実際のそれを読了することで質的研究に疎遠だった人が「質的研究の意味」について少し理解できることを助けてくれるように思えるからだ。
オートエスノグラフィー
(1)病気のはじまり
様子がおかしいと感じたのは、いつものように会社のランチタイムで同僚と一緒にお弁当を食べていたときのことです。お腹が空いていたのに、ご飯を一口、二口食べただけで不思議な満腹感を感じました。金曜日のことだったのですが、思い返してみるとこの一週間ほどは同じように、空腹だった筈が食事を始めるとすぐに満腹感を感じることがあり、ただその日はそれ以上、食べ進めることも苦しく、でも同僚の目が恥ずかしいので無理に食べ進めて、そこそこは食べきったと記憶しています。
午後の就業時間になると段々と様子がおかしくなってきました。お腹の辺りに鈍い痛みが出てきたのです。「お腹の辺りに」というのは、よくある胃痛とか腹痛と表現するのが相応しくないからで、かといって背中ということでもない。何とも表現しにくい痛みでした。
その痛みはどんどんひどくなり、会社は早めにあがりました。家に着く頃は脂汗が出るくらいに痛みが強くなって、妻に「お腹が痛い」と言ったら、「夕ご飯、食べれない感じ?」とか聞くので、「うん」と答えました。そうしたら、「救急車を呼ぶ?」と聞かれ、いやいや、これは「お腹の痛み」というカジュアルな症状だし、ひょっとして気のせいとはいわないけれど何ということも無かったら悪いし「いや、タクシーを呼んで」とお願いしました。
タクシーで近くの大学病院に着く頃は、もう歩くのが辛いほどに痛みがましていました。受付をすると「順番にお呼びします」と言われました。痛みで冷静な判断が出来ていませんでしたが、確かに大学病院というのは順番待ちをしなければいけないのだったな、ということで救急車で来なかったことをとても悔みました。救急車というルートにはいわゆるファストパス、いち早く診察にあたってもらえるという特典があることにその時になって気づいたのです。
只今は三重県にて救急車の有料化の議論が進んでいるというニュースを読んだのですが、救急救命士の負担やコストを考えると妥当な方向だと思いつつ、その「ファストパス」をもらうことをためらうことで取り返しがつかない、つまりは命を落とす人が増えるだろうなとも思います。
さて、おとなしく診察の順番待ちをしていたのでは私は多分、自分の順番がくる前に死ぬだろうな、と感じていました。かといって、「私を優先してください」ということははばかれます。皆さん、難儀をして順番待ちをしているのですから。私がそのときどのような行動をとったと思いますか。
やはり死にたくなかったので、私は公衆電話を探しました。今のように携帯電話の無かった時代の話です。息も絶え絶えでしたが、幸い、病院の中に緑電話機があり、そこにお金をいれて「119番」を押しているところで看護師さんに呼び止められました。どうして看護師さんが私の言わば“奇行”、「病院内で119番を呼ぼうとしている」ことに気付いたのかはよくわかりません。
どうやらその“奇行”のおかげで私は「ファストパス」を得たようでした。診察されベッドに横になることが出来ました。鎮痛剤を注射されたからだと思いますが、そのときは「死ななくて済んだ」と思いました。
(2)病気の診断
血液検査の結果が出たらしく医師らが「緊急入院」といったお話をしていることを聞いて、少なからずショックでした。会社で大きなプロジェクトのリーダーを任されていましたし、当時は解析担当者として10を超える医薬品の解析をまわしていたので、会社を休むわけにはいかないのに、と思ったからです。
医師から聞いた話ではアミラーゼ値が異常値で、どうやら胃の中で消化しない食べ物が残存しているらしく、まずはその残存物を取り除くことをするというお話でした。病室のベッドに移され、産まれてはじめて点滴なる装置を付けられてみると、これはもう入院するより仕方ないのだな、という覚悟ができました。
「急性膵炎」と診断されました。胃の中の残存物を取りきった後はもうすっかり痛みもなく、自分としては「完治」のようでもあったのですが、何より急性膵炎を起こしたその原因を取り除かなければ食事をすることが出来ないわけです。夜になって医師が来られて、明日から外科病棟に移すというお話をされましたので、その医師が内科医なのだな、ということがわかりました。
翌日からは6人部屋の病室で過ごすことになりました。人の好さそうな若い男性の医師が色々とお話をしてくれたのですが、どうやら膵臓に嚢胞(のうほう)性の異物があり、今回はそれが大きくなって消化のルートを邪魔していたから膵炎になったのだということでした。また、巨大化した嚢胞状のものの中には液状の物質があり、恐らくそれは悪性化しているということでした。最初は良性の液体であっても、これだけ肥大しているところをみると長期間になっているのであり、要するに私の病気は「膵がん」だろうというのです。
治療の選択肢は2つあるということでした。1つは中にある液体を全て取り除くというもの、もう1つは嚢胞性の異物そのものを切除するというものでした。医師のおススメは後者であり、前者の場合は液体を取り除く際にあやまってその癌化したものが他の臓器に飛び散ると悪いからということでした。このような説明を受けたシロウトの私には「いや、液体を取り除いてほしいです」という選択肢はありませんでした。
手術は2週間後ということになったと記憶しています。院内にも別途「ファストパス」があるらしく、病状が悪い人を優先して手術すると決定されると、他の人たちよりも優先して種々の検査を受けることができるようでした。病名欄に「膵Ca」と書かれた紙をもって様々な手術前検査を受けました。階段を上り下りして、心臓のバクバクが何秒で収まるかといった検査があり、なるほど心臓が手術に持たないとなると仮に手術以外に選択肢がない病気であっても手術は受けられないものなのだな、ということを知りました。
(3)運命を悟る
コトの次第はこのようでしたが、もう一方のファクト、つまり私の「気持ち」の方はこのように「ファストパス」のようなテキパキとしたものではありませんでした。30代で膵がんということになると寿命が長くはないことを製薬企業社員として教えられていましたので。何より、自分は化学、理工学部出身であったのに製薬企業を就職先として選んだことさえ後悔しました。「膵Ca」が「膵がん」であることも、膵がんの予後が悪いことも、若ければ若いほど癌の進行が速く進むことも、製薬企業に就職していなければわかっていなかったことだったからです。
2月でしたが、自分は年内、命が持たないと悟りました。もちろん、医師から「年内もたない」とは言われていませんでしたが、自身が知っている知識と合わせそのようであることを妻に告げると「わかった」とだけ、妻は軽く答えました。彼女が「そんなはずはないでしょ」といったような悪あがきや反論をしたり、取り乱した反応をしないことを有難く思いましたが、どれだけ辛い気持ちだったかはお互いに分かり合えていたように思います。
心残りは2歳の一人息子の存在と、つい最近、購入を決めた埼玉県のマンションのことでした。「自分が死んだら、マンションの始末は任せる」と、まだ住んでもいないのにそんな話を妻にしました。東京の板橋で1DKの小さな住まいで3人暮らしであった我が家にとって、2倍以上の広い家に引っ越すことはとても楽しみで、入院となる数日前にも浦和にあるそのマンションが見える小高い丘にたって完成間際のそのマンションを外から3人で眺めて「早く住みたいね」と話をしていたことを思い出しました。癌だとわかる前の、あの日に戻りたいと思いました。また、あの日が自分の人生において幸せのピークだったなと思いました。
自分が死ぬのだなと知ると、もはや1日中、うわの空というか、病室に設置してある小さなテレビをつけていても、テレビを見るわけではなく、テレビの後ろ側あたりに焦点があるというか、かといってテレビでもつけていないと気がまぎれず、バラエティ番組なのに、ずっと涙が流れていました。流れる涙を拭く気力さえ起きませんでした。
手術の日がきました。もはや寿命が長くない私にとって手術の日というのはどうでもいいような、些細なことでした。医者からは「もしお腹を開いてみて、胃とか他の臓器にも癌が見つかったら、胃の全摘とかもやります」と言われていたので、お腹を開けてみてそこで判断することもあるのだと知りました。麻酔科医の先生がきて、全身麻酔を施行することの同意書にサインをしました。麻酔科医から「1万人に1人、麻酔薬の拒絶反応で死ぬ人がいる」と聞かされたときは「その死に方が一番よい」と思いました。手術が終わって胃や腸が無くなって、知り合い一同に看取られながら死んでいくという想像が一番辛かったので。
(4)術後
手術は長時間だったようですが、麻酔を打たれていた私にはわかりません。目をさましたときはサイズのかなり小さいベッドに足を曲げた状態で私一人でした。ひょっとしたら親族一同、あるいは会社の同僚が周りを囲んでいるところで目を覚ますのではと思っていたので拍子抜けでした。看護師さんさえいません。頭の中で「どうして私一人なのか」、推論が巡りました。まずは「おそらく手術は成功したようだ」ということ、そして何より医療者が私という患者にあまり興味が無くなった、すなわち「治った」のではないかということでした。
その後、まずは妻がきて、私の嚢胞の異物を見せられたことなどを話してくれました。私が目を覚ました場所は救急救命室のようなところだったのですが、しばらくして一般病棟に移され、その後に手術の結果を医師から説明して頂きました。
病名は「嚢胞性良性腫瘍」ということでした。嚢胞の中にある液体は大抵の場合「粘液性」なのだそうで、これはしばらく経過すると癌化するらしいのですが、私の場合、その液体はレアな「しょう液性」だそうで、この場合は悪性化しないのだそうです。施術名には「膵頭十二指腸切除術」という名前があり、嚢胞とつながっている膵臓の半分(膵頭部)を取り除いたのちに、一旦、切り離した5か所を再縫合するという難しい手術なのだそうです。知り合いの外科医に私がこの手術をしたことがあるというお話をすると皆、一瞬、嬉しそうな顔をします。恐らくは外科医の憧れなのか登竜門なのか、難しい手術の代表選手のようです。
かくして年内もたないと確信していた私は無事に「完治」し、退院することが出来ました。何日も寝たきりだったので、リハビリとして毎日、病棟内を歩く練習をしたことを思い出します。めでたく職場にも復帰できることになり、満員電車に再び乗ることになりました。私の通勤する電車内ではたまに故意的に人を押すような人に出くわすことがあり、その日も同じような嫌な思いをしましたが、以前のようにイラッとして、その後すぐにおかしくて笑ってしまいました。「イラッと我思う、故に我あり」というか、自分が腹を立てたことで生きていることを実感したからです。
後日談として
以上、オートエスノグラフィー(もどき)でしたが、いかがでしたでしょうか。「オートエスノグラフィー」という言葉の説明をし忘れていました。済みません。
オートエスノグラフィーとは、エスノグラフィーの一種です。エスノグラフィー一般は異文化の中に身をおいたり、あるいは同じ病気の人達を観察したりインタビューするといった質的研究のアプローチですが、オートとは「自己」であり、自らの語りを伝える、つまり今回のナラティブは私自身が体験した、38歳のときの出来事です。
ナラティブやエスノグラフィーについては前回、前々回にも触れたように量的研究者にとっては異質であり、自己(オート)エスノグラフィーともなれば、なおのこと研究とは受け入れがたいところがあろうかとも思いますが、研究としては増えてきているようです。
何より病気の経験者は医療者が決して知りえない「病気の本当の意味」を知りえているという立場であり、その意味では私の病気は私しか知らないというのも事実だと思います。語りの中では触れていませんでしたが、血液の“地図”をとる検査で注射された造影剤に対してショック症状が起きてしまいました。今でも数年に1回くらいは入院するのですが、造影剤アレルギーのため精密検査が出来ず、容態が回復すると退院するということを繰り返しています。
痛みの症状が再発するのはとても辛く、その痛みで冬であっても全身から脂汗がでるのですが、このせいで会社オフィスに救急車が駆け付けたり、自宅から救急車を呼んだりするときは自分がとても情けなく感じられます。
死を知る人生
イギリスのことわざに「Man lives freely only by his readiness to die(死ぬ覚悟ができて人は初めて自由になれる)」というのがあります。手術が終わって目が覚めた以降の私は、「死んでいた自分」と比較するクセがつき、その意味で違う人生を送っていると思います。貴重な体験ができる際に感謝するだけでなく、家でだらだらしているときでさえ「だらだらすることを自分で選んでいる」感覚があり、それはそれで尊い時間です。
冒頭の、同僚であった彼女が亡くなったのも38歳でした。私は“誤診”だったのに彼女はそうではありませんでした。小学校の長男と学校にあがる前の次男坊の2人を残して逝ってしまいました。亡くなった日は彼女の旦那さんから私に直接、電話がありましたが、本来は励まさなければならないであろう私の方が取り乱してしまい、旦那さんの方がむしろ冷静で、「一緒に働けたことを感謝している」と彼女が言っていたことだけ、私に伝えてくれました。彼女にとっての私がそうであったように、私にとっても彼女と一緒に仕事をする時間が一番長く、かけがえのない存在でした。
今年は彼女の三回忌にあたります。人の命ははかなく、尊いものです。健康なときはそれを忘れがちになるので、私がたまに入院するのは、その戒めを神様がしているのかもしれません。おっと、私は無神論者でしたね。
「続・疫学と算盤(ソロバン)」第6回おわり。第7回につづく