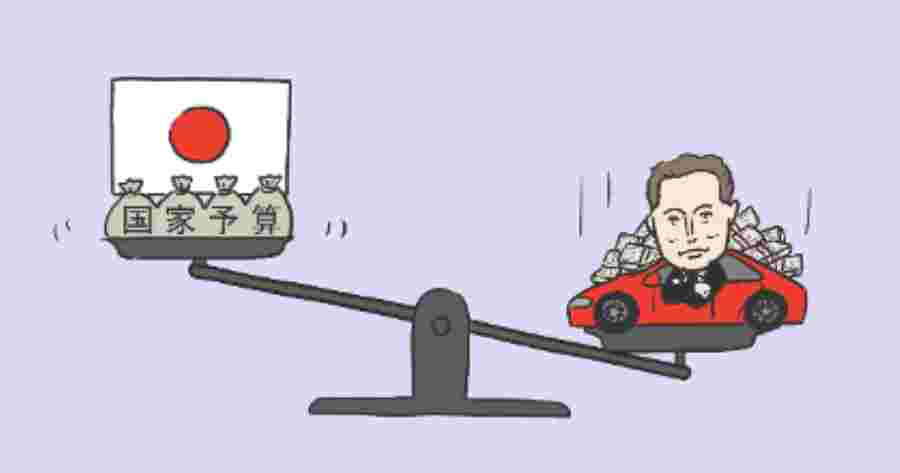第4回:病気の意味の研究
- Erwin Brunio
- 2024年4月1日
- 読了時間: 12分
更新日:2024年5月7日
2024年4月1日

2020年10月20日から連載開始した「疫学と算盤(そろばん)」は、昨年末、通算第36回を数え無事終了しました。36回分のコラムはご承知かと思いますが、当WEBサイトにてダウンロードできる電子書籍となっています。2024年1月からは、コラム続編の「続・疫学と算盤(ソロバン)」がスタートします。筆者・青木コトナリ氏のコラムとしては、日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボのWEBサイト連載の「医療DATA事始め」から数えて3代目となる新シリーズの開始です。装いを変え、しかし信条と信念はそのままに、“えきがくしゃ”青木コトナリ氏の新境地をお楽しみください。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ氏の
「続・疫学と算盤(ソロバン)」(新シリーズ) 第4回:病気の意味の研究
高尾山
東京在住の人にとって山登りといえば最初に思いつく場所はおそらく高尾山だろう。中央線で気軽にいける標高わずか599メートルの高尾山は多くの人が訪れる人気のスポットである。
先日、学校の友人たちと一緒に高尾山に登ったのであるが、山登りに興味の無かった私にとって高尾山の登山は人生初の経験であった。また、学校の友人というのは何を隠そう、私の気まぐれ(?)で昨年の4月から就学している大学院での同級生の面々である。中でも今回はアクティビティが高い一泊旅行という企画のせいもあってか、フル参加のメンバーは私以外、20代から30代という若さである。
世代の違う人たちとの登山ともなればついていくのがやっとで、恐らくは翌日には筋肉痛になって動けなくなるのではとも思っていたが、案外と苦労なく同じペースで歩くことが出来た。私もなかなかやるではないか、といえばそんな話でもない。種明かしをするならば、標高の半分ほどはケーブルカーで“登山”したのであって、これは山好きの人にしてみれば登山でも何でもない、ただのピクニックだったからである。

今回は「病気って何よ」ということの研究を取り上げてみたい。「え?何それ?」「病気は病気でしょうが」とツッコミたいお気持ちはちょっとこらえて頂きたい。確かに疾患はその定義がしっかりしているのが当たり前であり、「病気とは何か」という問いは愚問というよりもむしろその問い自体が成立しそうにない。
質的研究というアプローチをご存知だろうか。質的研究とは、研究の方法論の呼称であり、病気に限らず「意味」を調べる際に用いる研究アプローチである。今回はその質的研究をとりあげようということである。
質的研究
例えばあなたが癌であると告げられたとしよう。あるいは親御さんが来週から透析治療を開始するとしよう。はたまた、お子さんがメンタル不調になって学校を休学しているとしよう。こうした病気にかかるインシデント(出来事)を経験した人にとっての関心事は「その病気を治す」ことだけではないハズだ。
もちろん病気が治るのかどうか、もし治るとしたらそれはいつ頃なのかということは最大の関心事ではあるだろう。一方で、透析のように治すことが目的ではない治療もある。他方、病気の告知を受ける前と受けた後で、あるいは肉親やお子さんが治療開始を始める前と後で、あなたの心持ちは大きく変化するに違いない。さらには自身が罹患者であれば会社にはいつ誰にどのように伝えるのか、休職は必要になるのか、お金の負担や副作用による脱毛はどうかといった心配は尽きないだろう。親御さんやお子さんが罹患したとなれば当人よりも心が折れ、精神疾患を発症することがあるかもしれない。
「病気の意味」とはまさにこのような包括的な話であり、決して治療とか改善とか有効率だけで語りきれるものだけではない。いかに卓越した医学知識や治療法を知っているからといって、その病気を本当の意味で知っているというのは思い込みか自惚れである。当該の罹患(経験)者はその病気を経験したこともない医療者では決して知ることの出来ない、医学知識とは違う「意味」を知っている人なのである。
こうした診断や治療を主とする研究とは別にその「病気になるとはどういうことなのか」といった視点の研究には広く質的研究が用いられることが多い。私たちが普段、目にしているところの研究はその“反意語”的に量的研究と(質的研究者は)呼称するのだが、医薬系の分野においていえばそのほとんどが量的研究に分類されるものであり、案外と質的研究は“ド素人”という人も多いだろう。質的研究とは実際にどのようなアプローチの研究なのかその方法論についてまずは概観してみよう。
質的研究の方法論
「病気の意味」を探ろうとすれば私たちがよく見聞きするところの、「治療Aと治療Bとはどちらが優れるのか」といった研究目的、リサーチクエスチョンとは随分と違う世界観、研究のアプローチになるだろうことに気づくだろう。全くもってその通りであり、質的研究の基本は「当事者に聞く」、インタビューが第一選択となることが多い。
具体的にいえば「あなたが癌だと告知されたときは、あなたはどのように感じましたか」「お子さんの様子が少し普段と違って塞ぎがちになったと感じたのはいつ頃ですか」「治療に対してお金や就業の不安はありましたか」等々、当人にまずは聞かないことには始まらない。
ナラティブ(物語)アプローチという言葉をどこかで聞いたことがあるかもしれない。告知された病気を受け入れられずに感情が乱れたり、それがやがて受け入れられるようになり、といった心の動きは調査票に記載してもらうよりもむしろ対話の中で引き出す方がその本質に迫ることが出来る。
また、インタビューについては1対1で行うだけでなく、「癌告知をうけた人を何人か集めて一緒に話し合いをして頂く」ことで、研究者はその話し合い、ダイアログのファシリテータとなって情報を獲得するというアプローチもある。1人の当事者から聞いただけでは「その人の個性」と「告知を受けた人たち全般」との区別が出来ないという欠点があるが、複数の人から話を聞くことが出来ればその心配がない。また、同じ境遇同士が一堂に会することで“化学反応”を起こして、忘れかけていたその昔の出来事をより思い出しやすくする効果もあろう。一方、逆に周囲の目、羞恥心が働き「他の人たちとは違ってうちは貧乏だから」「副作用が原因かわからないけど夜尿症が酷くて」といった話は聞き出せなくなるという短所もある。
つまり、どちらの手法が優れるというものでもなく、手法の選択は研究テーマによって、あるいは時間の制限や費用の制限などから判断することになる。質的研究の分野では当人1名へのインタビューを「個別インタビュー」、何人かの当事者を集めるインタビューを「フォーカスグループ・インタビュー」と呼称する。
また、前述したようにカミングアウトしたくないといった「羞恥心」の視点を踏まえると、インタビューを受ける側(研究者)と当事者との間の信頼関係も重要なポイントとなる。加えて、インタビューを10分、20分といった短時間で行ったのではろくな研究成果が得られない。インタビューを長時間することは信頼関係の構築にも寄与するものであり、“無駄話”が案外と無駄にはならないこともある。つまり、その“無駄”な話のおかげで本音を引き出せる可能性がアップするというわけだ。時間と手間が掛かるが、生身の人間同士が面と向き合うというアプローチが質的研究においては案外とコスパ(コスト・パフォーマンス)、タイパ(タイム・パフォーマンス)の視点から見ても至極、合理的な選択肢となる。
グラウンデッド・セオリー
グラウンデッド・セオリーというアプローチはこうしたインタビューや記録で得た情報を分析し概念化、体系化するアプローチのことである。「指標(スケール)の開発」といえばピンとくる人も多いかもしれない。癌患者さんのQOLを調べるための項目や、認知症の重症度を調べるためのチェックリストを作ろうとした場合、これを医療者が独自に自身の思いで設計するのではなく、質的研究というアプローチがまずは有益ということも多いだろう。
「スケールを作る」という研究は主に質的研究でもたらされ、そこで作られた項目の列挙、チェックリストを使って病状を調べるという研究となればこちらは量的研究となる。研究デザインの中にはその双方を包含したものがあり、これをミックスド・メソッド(混合研究法)と呼称する。
例えばメンタル不調となって「出社拒否症」が“発症”したとしても、100人の出社拒否症の人を集めればそれぞれに主因も違う可能性があり、成熟していないスケールでは正しく病状やその改善あるいは悪化を観察することが出来ない。「出社拒否症」を形成するものが一体何で、それはどういった認知と紐づいているのかといったところはグラウンデッド・セオリー・アプローチによって整理する。ここまでが質的研究であり、そこで得られた構成概念をチェックリスト化したうえで量的研究を行う、というところまでセットで行う研究が混合研究法ということになる。

質的研究の本質
「なるほど、質的研究とは疾患定義の指標づくり、つまりは量的研究を助けるために行う研究を言うのだな」と受け止めるのは少し待って頂きたい。確かに量的研究のための前段となるスケールや指標作りとして質的研究は大いに貢献することもあるのだが、こちらは誤解を恐れずにいうならば質的研究としては本流ではない。
質的研究というのはその名の通り「質」を問うのであって、「病気になることの意味」「働けなくなることの意味」「学校へ行けなくなることの意味」「認知症の親を介護することの意味」「障害をもつ子供を育てることの意味」そのものを探求するのがいわばパーパス(存在意義)、本流である。医学系一般の量的研究の中にディープに入り込んでいる人にしてみれば「それって研究なの?」という感覚もあるかもしれないがそれは単に視野が狭いだけなのかもしれない。動物や昆虫の研究における求愛ダンスであるとか、歴史学・考古学などを思い起こしてみて頂ければ、世の中の研究において必ずしも直接的には人の役に立つものかどうかわからない探求的な学問領域は少なくないことに気づくことだろう。
もう少し違った角度からみてみよう。病気や治療といった、私たちに馴染みのある学問領域やアクティビティは実際に生じたこと、ファクトを拠り所とする。つまり「熱が37.9度ある」とか、「胃に直径1ミリの癌細胞がある」といった事実をもとにこれを平熱にするとか癌細胞を縮小させるといった目的で治療にあたる。一方で質的研究というのは「それをどのように感じるのか」「どのように受け止めるのか」、感情や認知を拠り所とする。いや、むしろ「すごく悲しい」「何にもやる気が起きない」といった心の中身をファクト(事実)として受け止めるともいえよう。その意味で心理学系の分野は質的研究のアプローチと相性が良い。
そして何より重要なのは「すごく悲しい」を是正し、幸せな気持ちにするためにはどうするのか、というところに必ずしも興味関心がない点が質的研究の「質的」といわれるゆえんである。「どのように悲しいのか」、「なぜ辛いのか」、その本質を知ることがゴール、「意味を知る」ためのアプローチである、というのはそういうことなのである。
エスノグラフィー(参与観察)
「意味を知る」、質的研究のルーツについては、イギリスの人類学者であるマリノフスキーによる「西太平洋の遠洋航海者」という書物がそれという説も多い。1915年から1918年の足掛け4年をかけて行われた、ニューギニア諸島の人々における「贈与」の意味を調べるための研究はエスノ(ethno、民族)を記述(graphy、グラフィー)するために長期間、研究者がその場所に滞在するというアプローチがとられ、これは質的研究の中でも「エスノグラフィー」と呼称される。
社会学や文化人類学分野で発達したエスノグラフィーは、例えばオーストラリアの先住民における婚姻の意味とは、あるいはエスキモーの暮らしにあって家族とは、といった異なる文化、「民族」を研究テーマとしたものも多いが、現代的な意味では必ずしも「民族」シバリとは限らない。例えば自殺の少ない町に身をおいた研究を書物とした「生き心地の良い町」(岡壇著、講談社、2013)や、これにインスピレーションを受け日本全国の自殺希少区域への訪問記録をまとめた書籍「その島のひとたちは、ひとの話をきかない―精神科医、自殺希少地域を行く」(森川すいめい著、青土社、2016)などは広い意味でエスノグラフィー・アプローチといえるだろう。エスノグラフィーには「参与観察」という日本語訳もあり、むしろ「民族の観察」ではなくこちらの方が現代的、実際に即した和訳といえる。
繰り返しになるが、質的研究の本懐(?)とは「意味を知る」ことであって、すなわちエスノグラフィーにおいても「先住民における贈与とは」「婚姻とは」「儀式とは」を知ることが目的となる。それゆえに自殺希少地域に身をおくというのもまた、基本的にはどのような人がそこで暮らしているのかの記述が主であり、そこから派生して「どのようにすれば日本の自殺率を減らせるのか、その対策の参考とする」という目的は従属の目的ともいえよう。
もちろん社会的な“実益”のために質的研究の成果を先行する基礎研究として受け止め、後者のような社会課題解決のための量的研究に生かすというバトンパスも大いにアリだ。自分たちだけで混合研究にて行う必要もなく、後者の研究者はエスノグラフィーを実施した研究者当人ではなくてもよい、ということでもある。

また、疫学の視点でいえばこうした質的研究は「観察者バイアス」が気になるところだ。要するに研究者、つまりインタビュアーや現地滞在者が見聞して感じたことはその当人の思い込みや「色めがね」を通しているのであって、結果を一般化するうえでその観察者バイアスは邪魔になるというのが疫学的なスタンスである。ところが質的研究のスタンスはそうではない。観察した研究者が感じたことそれ自体をファクト(事実)として受け止め、それ故に「結果を一般化することができるだろうか」には重きをおかないということも大いにアリというわけだ。思い込みや色めがねまでも肯定する、というのは医学系研究者にとって異文化であり混乱しかねない。何を隠そう、質的研究の論文や発表を聞くと私自身がそのような困惑に陥ったりもする。
若者文化に身をおいてみる
さて、高尾山“登山”の翌日になって、どうにも体調がおかしく不覚にも会社を休むことになってしまった。久しぶりにリアル会議とその後には同僚との懇親会があったので残念至極である。
「え、ケーブルカーを使ったので筋肉痛は無かったのでは?」と思われるだろうが、50代の私にとってハードだったのはむしろ登山の前日土曜日の懇親会の方である。キャンプファイヤーをした流れで始まった相部屋での飲み会は、お開きになったのが夜中の2時半。どうやら体調不良はこちらに原因があったようだ。
そういえば、私自身も若かりし頃は休日前ともなると夜通し友人と一緒に過ごして気が付いたら朝ということが当たり前だったことを思い出す。話題は何でもよい。夜半過ぎまで一緒に過ごすことそのコトに意味があるのだ。一泊二日の高尾山登山ツアーは若者文化に身を置いた、私にとってのエスノグラフィーでもあった。
「続・疫学と算盤(ソロバン)」第4回おわり。第5回につづく