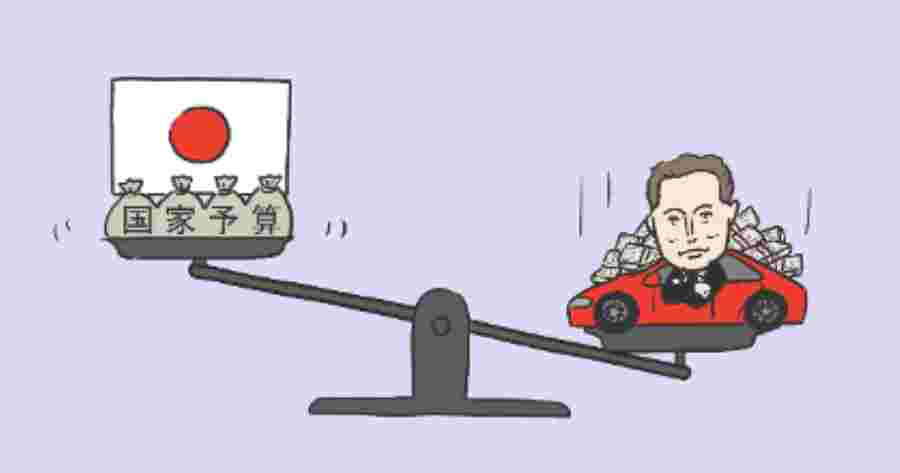第35回:RWE(リアルワールドエビデンス)を求めて
- Erwin Brunio
- 2023年8月7日
- 読了時間: 11分
更新日:2023年12月4日
2023年8月07日
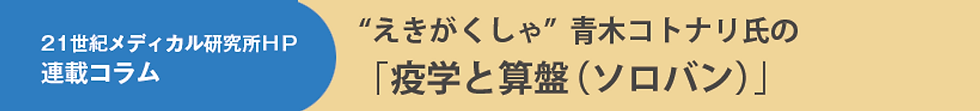
2020年10月20日から、3週間に1回、大手製薬企業勤務で“えきがくしゃ”の青木コトナリ氏による連載コラム「疫学と算盤(ソロバン)」がスタートしました。
日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボWEBサイトに連載し好評を博した連載コラム「医療DATAコト始め」の続編です。「疫学と算盤」、言い換えれば、「疫学」と「経済」または「医療経済」との間にどのような相関があるのか、「疫学」は「経済」や「暮らし」にどのような影響を与えうるのか。疫学は果たして役に立っているのか。“えきがくしゃ”青木コトナリ氏のユニークな視点から展開される新コラムです。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第35回:RWE(リアルワールドエビデンス)を求めて
代用品
土用の丑の日の数日前、我が家の朝食は「ひつまぶし」、ご飯の上に鰻とその横に土瓶が据えられていた。こんな豪勢な朝食は珍しく、何かあったのかと聞いてみるとなんてことはない、ご飯のうえにのっているのは近くのスーパーで盛んに大売出しをしていた鰻によく似たカマボコなのだという。
まあ、それでも味が鰻と同じであればそれもよかろうと思って食べ進めたのだが、どうにも見てくれほどにはその鰻らしさが感じられない。土瓶に入っていたスープと、ワサビを大量に混ぜてかきこむことでどうにか完食はしたものの、一緒に食べていたうちの子供は一口食べただけで後は全部残していた。どうやら我が家の評価としてこの鰻カマボコはまだ改良の余地がありそうで、それまでしばらく食卓には登場しないことだろう。

さて、前回とりあげた次世代医療基盤法の改正は臨床現場のデータ、俗にいうリアルワールドデータ(Real World Data、RWD)を社会にとって有効活用するためのものである。端的にいえば、医薬品の承認申請に際してどうにか臨床試験で得られた情報の補完、あるいはその代用に使えないだろうかという視点からの改正と言ってもよい。
欧米ではこうしたRWDから得られたエビデンスのことをReal World Evidence(RWE)と呼称し、医薬品の承認申請にかかる負担を減らし、何よりいち早く苦しむ患者さんに届けるために使えるためにどうするかといった動きが進んでいる。日本の次世代医療基盤法の改正もこの流れを汲んだものといえる。
今回は日本国内に限らず、先行する欧米においてそのRWD、RWEなるデータ活用が現状どのようであるかを整理してみたい。そこから日本の近未来も少し見えてきそうである。
治験の代用
RWEという言葉が現実のものとなったエポックメイキングな出来事といえそうなのが、2019年にアメリカで承認されたパルボシクリブ(Parbociclib)である。この適応拡大では治験、すなわち実際の患者さんを被験者として既存治療群と無作為化臨床試験を行うといった医薬品承認申請の第3フェーズが省略され、なるほどRWDには治験を省略できるポテンシャルがあるということが、ここ日本でも広がることとなったのである。
パルボシクリブはホルモン受容体陽性(HR+)で、ヒト上皮成長因子受容体2型陰性(HER2-)の進行性または転移性乳がんの治療薬であり、アメリカにおいて2015年には既に女性乳がん治療薬として承認を得ていた医薬品である。
一方、男性乳がんについては、そもそも女性の乳がんと比して極めてまれな疾患であり、臨床試験を行うために被験者数を十分そろえることが困難という背景事情があった。そこで開発元であるファイザー社は、実際の臨床現場において男性乳がんの治療として処方した事例を含む医療データを取り扱うFlatiron Health社の匿名化された電子カルテ由来DBを分析したわけである。
これによって既存の治療と比較し、パルボシクリブが無増悪生存期間(病気が悪化していない期間)と全生存期間を改善することを示したのである。もちろん、申請パッケージはこれだけでなく他の安全性情報等も加えているのだが、とにかく追加の臨床試験をしないで適応を拡大することに成功したのである。
一方で、ではその後これに追随して欧米ではRWEのみによる医薬品の承認申請が盛んに行われるようになったかといえば、そうではないことに留意しなければならないだろう。「患者さんが極めて少ない希少疾病であり、臨床試験を行うのが困難」という背景事情に加え、使ったRWDが行政当局として合格ラインの品質レベルであることなど、治験を省略するためには様々なハードルが今もある。
パルボシクリブの例ではFlatiron Health社において構築されたRWDのプロジェクトに当初よりアメリカの行政当局(FDA)メンバーも参画していたと聞く。つまりは「行政としての合格ラインの品質」を握る者を参画させることで、それがおおむね担保されていたともいえるだろう。なお、日本においてその合格ラインがどこに引かれているのかについては、現時点でもはっきりとは見えていない。
治験の外部対照
治験全部の省略はハードルが高く、欧米においてもなかなか追従する事例がみあたらない一方で、その“半分”ということであればいくつかの事例が見受けられる。
“半分”とはどういうことか。「対照群である既存治療の成績に関してはRWDで代用しよう」ということであり、こうしたRWDの利用の仕方を「外部対照」と呼称する。
実際の事例としてどのようなものがあるのか知りたい人は、日本製薬工業協会が2020年に発行した「リアルワールドデータを承認申請へ~活用促進のための提言~」*が参考になるだろう。海外における事例だけではなく、国内における外部対照群としての活用事例としても4製品の事例紹介がある。適応症は糖原病Ⅱ型(ポンぺ病)、ヘパリン起因性血小板減少症、多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎、低ホスファターゼ症とある。どうやら私たちが普段、耳にするようなポピュラーな病気ではなさそうだ。
やはり「外部対照」としてRWDを使うにしても「希少疾病であり、臨床試験を行うのが困難」という条件は必要なようである。本来、比較対照群には当該医薬品候補を処方する母集団、つまり同じ箱から玉を取り出すかのように同じ集団から選ばれることが大前提となるべきである。同じ箱(母集団)が前提となっているからこそ、そこから無作為に新薬候補の治療群と、比較対照群に割り付けることで比較妥当性が保たれるのである。

ただし、疫学研究一般においても、ごくまれに比較対照をこうした同じ母集団から選べないことがある。例えば、まさに画期的な新薬が発売されると同時に、当該の疾病患者の全てにその新薬が処方されるといったケースだ。こうした場合にはヒストリカル・コホート群と呼称するところの「過去の処方群」を比較対照にすることで妥協する場合がある。あまりに優れた医薬品であるために市場全体を“席巻”してしまい、比較対照となる症例群がないからだ。要するに外部対照としてRWDから処方群を使うというのはこの拡張ともいえる。
では何故に過去の処方群を比較対照とするのが基本的には適切ではないかといえば、「思いがけない交絡」が紛れ込んでしまう恐れがあり、フェアな比較であるという保証が揺らぐからである。平たく言うならば、医療現場の環境が整備されたり医療技術が進んだり、医療連携が充実したりといった時代の進歩の中に、治療成績に影響をもたらすものが潜んでいる可能性があるというわけだ。検査機器も違えば、病気の定義が緩やかながら完全に一致しないということもあり得るわけで、データからは読み取れない形で比較妥当性が揺らいでしまうのである。
とはいうものの、RWDを外部対照として利用するという選択肢が増えることは社会の実利という側面からいえば大いに歓迎すべきことだ。被験者のリクルートが困難な中で、半数の被験者で治験が出来るとしたら承認までの時間は大幅に短縮できる。特に希少疾病領域等においては、新薬が世に出てくることを待ち望んでいる患者さんにとって命に関わるお話であるということも決して珍しいことではないだろう。
治験成績の一般化可能性を補完する
RWDを医薬品の承認申請で活用する、というテーマにおいてもっともポピュラーな使い方は何かといえば、治験における一般化可能性の“欠点”を補完するというものだろう。例えば他に合併症がある人や超高齢者、妊婦などは治験において被験者候補から除外されるのが常であるが、実際の臨床現場ではそういうわけにはいかない。
つまり、治験成績として仮に既存薬よりも有効性・安全性において優れた成績が示されたとしても、実際の医療現場における他の病気を合併している患者や治験から除外された年齢層、妊婦においても優れるということは実のところ保証されてはいないというわけだ。
研究結果をより広い症例群に拡大して解釈できるだろうかという課題は、研究結果の一般化可能性あるいは転用可能性というのだが、この課題については最近、どうにかして改善・解消しようという動きがみられる。その代表選手はプラグマティック・トライアル(pragmatic trial)と呼称され、要するに被験者の条件等をより日常診療に寄せるアプローチをすることであり、臨床試験と観察研究の中間のような位置づけの研究デザインである。
ただし、プラグマティック・トライアルには通常の治験と比して明確な“欠点”がある。それが内的妥当性の問題だ。例えば通常の治験対象例であれば50%ほどの効き目がある医薬品において仮に小児には10%、超高齢者には15%しか効き目がなかったとしよう。研究者らがこうした真値を知る由もない中で、実際にどのような年齢構成比になるかによって研究結果は大きく揺らぐことになる。
一般化可能性の問題は「外部妥当性」とも呼称される。つまりは内部妥当性を高めようとすると外部妥当性が下がり、外部妥当性を高めようとすると内部妥当性が下がるといった、裏オモテの関係性がある。言い換えるならば、これまで医薬品の承認申請という仕組みは、内部妥当性ばかりを尊重し、外部妥当性を軽視してきたともいえる。
さて、RWDを使った外部妥当性(一般化可能性)の課題を改善することが出来たら、リーズナブルであり時短となろう。ただし条件が揃っている必要がある。例えば当該の医薬品において、既に別の適応症で承認され国内で治療成績がRWDとして蓄積されている場合や、海外で先行して承認されている場合などである。世界中どこにも当該の医薬品を処方したというRWDが存在していないならば、当然のことながら無い袖は振れない。
運よくこうした条件が揃っているならばある程度の副作用発現率やその重篤化を防ぐための方法論、小児や超高齢者における有効率などがRWDでの分析から予測精度が高められよう。これを治験の成績にプラスすることで大いに参考になる。
RWDの種類
さて、ここまでRWDとして臨床現場由来の医療データをひとまとめに取り扱ってきたがその種類は幾つかあり、それぞれに特性があるので整理しておく必要があるだろう。
電子カルテ由来のデータであれば、例えば臨床検査値の変動なども調べることが出来そうであるが、患者さんが転院してしまうとそれ以降の情報はわからないという短所がある。レセプトデータ(保険請求データ)は転院しても長期で観察することができる一方で、今度は臨床検査値がわからないし、俗にいう”レセプト病名“というのは案外と実際の病名とは違うことも多いようだ。
医薬品の承認申請に使うということで期待が寄せられるのは疾患レジストリデータだろう。「がん登録制度」はよく知られていると思うが、専門の学会などが特定の疾患と診断された患者さんを対象として関連する項目をしっかり記入するといったアプローチがとられる疾患登録(疾患レジストリ)は、データの品質のみならず、必要な項目の漏れがない点において、特に他のRWDよりも優れるといえる。
一方で、多忙な医療者が「疾患レジストリにしっかりとデータを入力する」ことや、「疾患レジストリをしっかりと管理する」ことを手弁当で行うというのは限界もある。実際のところ疾患レジストリが長期間運用できているのは、国から助成金が得られているケース等に限られているという声も聞こえてくる。
そんな中にあって今般の次世代医療基盤法の改正は、どうにかして疾患レジストリのような手間ヒマをかけずにRWDを薬事に利用したいという狙いがある。前回とりあげたように、行政当局が監査や査察をする際にも耐えうることが可能であり、またNational Database(NDB)と呼称される日本人1億人のレセプトデータと種々のデータとがリンクされれば、治験が得意としない、実際の臨床現場での治療成績を長期で観察することが可能となるものである。
RWD活用の未来
これまでみてきたように、医薬品として承認すべきかどうかの意思決定が少しでも早まるということは社会にとって大きな恩恵をもたらすものである。裏を返せば、RWDを適切に利用できないことでその承認が他国に劣るとなれば競争優位性として劣るばかりか、本来救えるハズの命を救えないということにも直結するものである。

RWD活用の最大の魅力はあくまで臨床現場への一般化可能性の課題解決にあり、本来的には治験の代用品とするものではないだろう。それでも治験の代用品としてのRWDの可能性にはなお捨てがたい魅力がある。アメリカのように日本でも治験を省略するRWD活用の未来が、鰻そっくりなカマボコの登場よりも先であって欲しいと願っている。
第35回おわり。第36回につづく
*日本製薬工業協会「リアルワールドデータを承認申請へ~活用促進のための提言~」