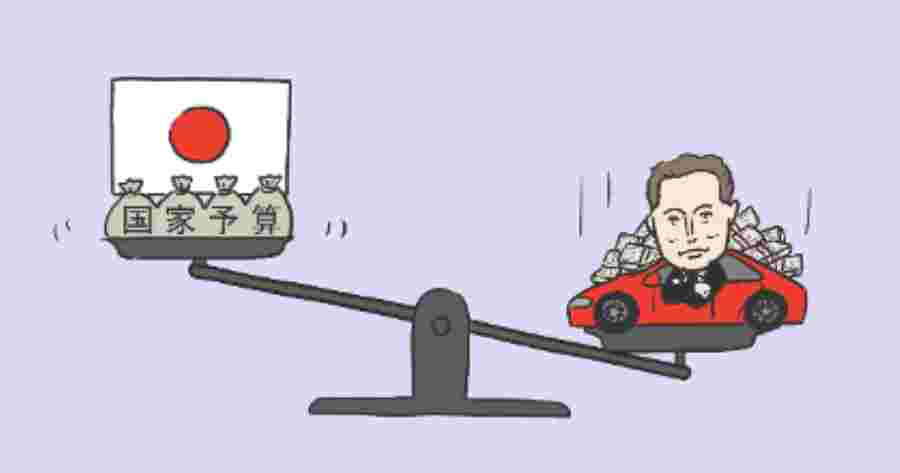第32回:行動変容を促すアプリ
- Erwin Brunio
- 2023年5月8日
- 読了時間: 10分
更新日:2023年6月1日
2023年5月8日
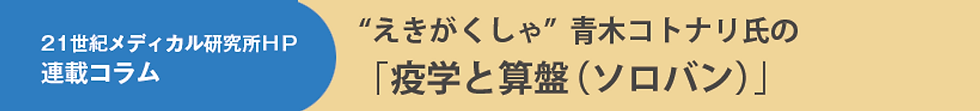
2020年10月20日から、3週間に1回、大手製薬企業勤務で“えきがくしゃ”の青木コトナリ氏による連載コラム「疫学と算盤(ソロバン)」がスタートしました。
日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボWEBサイトに連載し好評を博した連載コラム「医療DATAコト始め」の続編です。「疫学と算盤」、言い換えれば、「疫学」と「経済」または「医療経済」との間にどのような相関があるのか、「疫学」は「経済」や「暮らし」にどのような影響を与えうるのか。疫学は果たして役に立っているのか。“えきがくしゃ”青木コトナリ氏のユニークな視点から展開される新コラムです。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第32回:行動変容を促すアプリ
ChatGPTのインパクト
会話型AIツール、ChatGPT(チャット・ジー・ピー・ティ)が凄いらしいという話を聞いて私も少し試してみたのであるが、なるほど、確かにウワサに聞いていた通りだ。
手始めに自分の名前を入力して研究や論説を検索してみると、たちどころに幾つも見つけてくる。それならば、と怖いもの見たさも手伝って「青木コトナリ風のテイストで、医療DXをテーマにしたコラムを書いて」とお願いすると、ツラツラと書き始めるではないか。その出来栄えについて今のところはまだ私が書いた方がマシだなと、冷や汗をかきながらとりあえずは胸をなでおろす。

しかしながら話はそこで終わらない。思い出されるのは将棋や囲碁におけるAIの快進撃である。まだ数年は安泰だと言われていたのも束の間、瞬く間に人間がAIに勝つことは“無理ゲー”となった。もはや対局の休憩時間に棋士がこっそりとAIに次の一手を教えてもらってはいないか、それをどう管理するかというところに話題が移ってしまっている。然るに、AIが“私テイスト”で私本人よりも上等なコラムを書き出すのは時間の問題だろう。5年?10年?あるいは1年もすればコラムニストとしては失業しているかもしれない。
医療DXの潮流
こうした世界と比べると医薬系分野における医療DXなるインパクトは掛け声だけは大きいものの、さざ波の如しだ。DX(Digital Transformation)の本質は変革にあるというのに、業務効率が少しばかり改善したといったような昔ながらのIT活用のことをして医療DXと認識している人も多い。
このような“エセ医療DX”が多い中で、医療系アプリは数少ない、真なる医療DXの潮流を汲むものだろう。何せ10年ほど前には影も形もなかった存在である。最近ではプログラム医療機器とか、あるいはSaMD(サムディー、Software as a Medical Device)と呼称されるようになり、新たなビジネス市場として大いに注目されている。
本コラムでも取り上げている行動経済学分野に近いところで、人の行動を変える種のプログラム医療機器も存在する。「行動変容SaMD」と呼称するらしく、つい最近になって経済産業省がガイドライン*を発出している。“行動変容”という響きは、なんだかマインドコントロールを思い出させ少し怖い響きもあるが、前回紹介した「ナッジ」をアプリとして具現化したものと捉えれば親しみも沸くことだろう。そっと肘で突かれる程度の話だ。
今回はその行動変容SaMDを足掛かりとして、医療DX周辺について概観してみたい。
行動変容SaMDのはじまり
医療系アプリが人の寿命を延ばしたという研究を初めて聞いたときは驚いたものだ。2016年に開催されたASCO(American Society of Clinical Oncology、アメリカ臨床腫瘍学会)で発表された、アプリによる肺癌の改善研究がそれである。概略を紹介しよう。
対象患者はステージ3~4の肺癌患者さん133人で、さすがに二重盲検(どちらの治療を選んだか医療者すらわからなくすること)は出来なかったようではあるが、しっかりと比較対照をおいた試験を実施している。その比較対照群はごく一般的な経過観察群、より具体的には3~6か月ごとの医師による診察と医師の判断による適宜のCT検査を行う。 “プラセボアプリ”のようなものは使わない。
アプリ使用群の方はといえば、12種の症状を患者が自己評価を定期的に入力するというもの。この入力者は患者ではなくその代理人、介護者でもよい。入力されたデータはアルゴリズムに従って分析等がなされ、その結果が適宜医師と患者にフィードバックされる。必要に応じて診察やCT検査の実施をリコメンドする等、患者と医師の行動をナッジする。
さて結果はといえば、ハザード比0.325である。「ハザード比」について馴染みのない人には、アプリを使わなかった群での1年生存率が49%、アプリ群は75%という数字の方がわかりやすいだろう。これだけ大きな差が生じることは通常の治験でもなかなか無い。研究の途中だったというが、アプリ群の抜群の成績をもってして本研究は倫理面を配慮し終了となった。延命に関わることとなれば、そのままアプリ不使用を継続するわけにはいかない。一刻も早く被験者全員にそのアプリを持たせるべき、ということである。
SaMDのコスパ最強説
たかだかアプリに自分の容態を入力するだけで寿命が長じるというのは、長い年月をかけて化学構造を緻密に組み立て、医薬品として世に送り出すことを生業としている製薬企業にとっては受け止めがたくもある。もちろん、当該のアプリも精巧に作り上げられたものなのかもしれないが、アプリの入ったスマホを飲み込んで体内に入れるという訳でもあるまい。あまりにそれが安直にも感じられる。実際のところ、当時はアプリの使用を「治療」と考えてよいのかどうかの議論すらあった。
一方で、それだけヒトは行動を変える―定期的に自分の容態を自己管理し、医療者と共有する―ことは容易なことではないということでもあるのだろう。アプリが果たした役割というのは患者に何らかの行動を強制するのではなく、親ゾウが子ゾウの行くべき方向をちょっと鼻で突くかの如く、検査値の悪化があれば警告を発し病院行きを勧める。だが、それだけで寿命は延びるのだ。乱暴な言葉を使うならば、「コスパ最強」である。
思えば行動変容を訴求するようなアプリは医療分野だけでなく、他の分野も加えるとその品目数は数えきれないだろう。我が家でも食事メニューを提案するアプリを使って、以前とは違う低カロリーの料理が食卓を飾るようになった。こうしたアプリは食事制限するようないわば“医療行為”ではなく、やはりちょっと肘で突くようなものだ。強制力はない。
行動変容に関わるアプリがこれほどまでに乱立してくると、境界線の問題が生じてくる。つまり、行動変容アプリの中でどれを医療機器として認可してよいか、という話である。日本では人体への影響リスクに応じてそのアプリをクラス分けしており、食事メニュー提案のようなものを「クラスⅠ:副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないもの」として、規制の対象外としている。
ウラを返せば「人の生命及び健康に影響を与える恐れがあるもの」がその医療機器候補となりえるということでもある。その中にあって実際に医療機器として認可されるということは、簡単にいえば効き目が証明されたものであるということになる。国がお墨付きを与えた医療アプリだ、となれば誉れ(ほまれ)であり、使う側も安心できる。支払いも3割負担で済むので財布にも優しい。やはりコスパ最強だ。
治療用アプリというカテゴリ
実際に日本で認可されている行動変容SaMDとは具体的にどんなものだろうか。令和2年8月21日に承認された禁煙治療アプリがその第1号である。使用目的は「ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助」。医療機器なので当然のことながら医師の処方が必須となる。
次いで高血圧治療補助アプリが令和4年4月26日に認可されている。我が家のAI献立アプリよろしく、降圧目標のために食事や運動をナッジするというわけだ。この2月に承認された不眠障害用プログラムが第3号ということになる。

一方、前述したような「肺がんの治療を管理する」といった類のアプリは行動変容SaMDとは別の分類、治療計画支援SaMDとして承認を受けることになる。肺癌治療で研究されたアプリがそうであるように、適時に情報を入力するという、日々のルーチンを変えるという意味ではナッジといえるが、禁煙の治療補助や高血圧の治療補助とは少しテイストが違うということなのだろう。ここにもまた曖昧な境界線の問題がありそうだ。なお、治療計画支援アプリも行動変容アプリも「治療用アプリ」にカテゴライズされている。
SaMD開発の促進
プログラム医療機器には治療用アプリよりも、より多くのアプリが開発されている「診断用アプリ」というカテゴリもある。行動変容アプリは3品目に留まっているが、診断用アプリ市場は数百品目に及ぶ。先日、行政の人に伺った話では、画像診断支援で326品目、それ以外の診断支援で82品目が承認ないしは認証されているらしい。文字通りケタ違いだ。
プログラム医療機器はその開発・販売会社のみならず、医療DXの促進という、国を挙げての目標設定にもしっかりと合致し、その市場規模拡大は規制緩和のカタチで行政サイドも後押ししている。
厚労省が立ち上げた規制緩和策はプログラム医療機器実用化促進パッケージ、通称DASH for SaMDと呼称する。DASHとはDX Action Strategies in Healthcareの頭文字をとったそうだが、「ダッシュ」、いかにもスピーディな承認が想起される。具体的には、以下4つの政策がDASHに含まれる。
(1) 萌芽的シーズの早期把握と審査の考え方の公表
(2) 相談窓口の一元化
(3) プログラム医療機器の特性を踏まえた審査制度
(4) 早期実用化のための体制強化等
中でも注目されるのが、(3)の中で検討されている二段階承認制度と言われる審査制度“革命”だ。ある程度の臨床実績や測定精度を含む機械性能において有益性が示されれば「第一段階承認」をしてしまおう、そのうえで臨床的なエビデンスが蓄積されたら「第二段階承認」、つまり“本承認”するというアイデアだ。
何せプログラム医療機器は医薬品とは違って好ましからぬ副作用の懸念がない。であるならば、ということでこうした制度案は十分に合理性がある。迅速に医療機器として承認されるようになれば、他国と比してビジネス上の競争優位性がでてくる。因みにドイツではこのような制度が既に実施されている。
また、IDATEN(イダテン)と呼称する変更計画確認手続き制度も魅力的だ。承認されたプログラム医療機器をバージョンアップする際の承認を迅速化させようということである。我々、製薬企業で働く者にとってみれば、プログラム医療機器分野におけるこうした規制緩和、二段階審査制度やIDATENといった制度は何とも羨ましい限りである。
医療DXの全体像
もちろんのことであるが、プログラム医療機器だけが医療DXのすべてではない。ウェアラブルと呼称されるところの腕時計やスマートスーツ、スマートコンタクトレンズなども期待の大きい分野である。一方、冒頭のChatGPTが診断や治療の真似事を可能にしたことで医師会らが警告を発している。会話型AIはまだ発展途上、信用に足りないのだ。
何より会話型AIが診断や治療をするとなるとこれは現行の医師法でみれば違法ということになるだろう。ただ、頭ごなしにこれを「けしからん」としたのでは日本における医療DXの実現は難しくもなる。オンライン診療も然りであるが、医療DXを実現するうえで医師法など法規制の更新は避けて通れない課題である。
その他、スマートシティ構想では例えば認知症で徘徊する人を見つけるといった視点も取り入れられており、医療DXに直接的、間接的に関わる。家電や不動産業も、冷蔵庫を開けたり部屋のドアを閉めたりといったログにて住人の生存確認を行ったり、スマート・トイレと呼称される技術で生体データ分析に生かそうという動きもある。医療DXはすそ野が広いのである。

さて、冒頭のChatGPTである。試してみたということは、コラムを執筆しているのは本当に私本人なのか、あるいは少しばかりChatGPTが代筆しているのかと疑われやしないだろうか。もちろん、「ワタシはロボットではありません」。本コラムのシリーズは100%の純度で私本人の執筆である(、、、が、信じてもらえるだろうか)。
第32回おわり。第33回につづく
*医療・健康分野における行動変容を促す医療機器プログラムに関する開発ガイドライン2023(手引き)