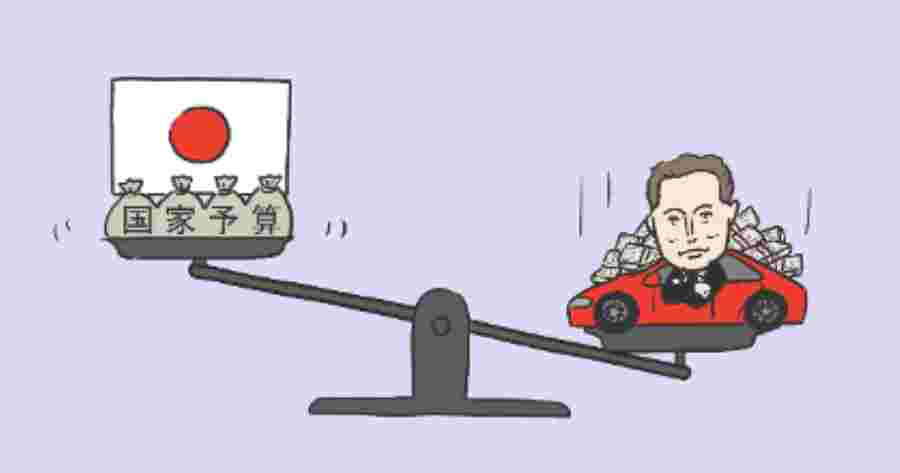第31回:ナッジとEBPM
- Erwin Brunio
- 2023年4月12日
- 読了時間: 10分
更新日:2023年5月8日
2023年4月12日
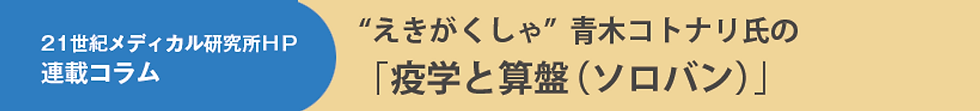
2020年10月20日から、3週間に1回、大手製薬企業勤務で“えきがくしゃ”の青木コトナリ氏による連載コラム「疫学と算盤(ソロバン)」がスタートしました。
日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボWEBサイトに連載し好評を博した連載コラム「医療DATAコト始め」の続編です。「疫学と算盤」、言い換えれば、「疫学」と「経済」または「医療経済」との間にどのような相関があるのか、「疫学」は「経済」や「暮らし」にどのような影響を与えうるのか。疫学は果たして役に立っているのか。“えきがくしゃ”青木コトナリ氏のユニークな視点から展開される新コラムです。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第31回:ナッジとEBPM
お花見
花粉症だというのに、桜の季節がくると花見をしたくなってしまうのは私だけではないだろう。池上本門寺に桜を求めて訪れたのは花見シーズンも終盤にかかる4月のことである。
現地についてみると、随分と高い石段が目の前にそびえ立っている。上りきるのは大変そうだ。信心深さのカケラもない私は、果たしてこの石段を上りきるほどの価値がこのお寺にあるだろうかと引き返したくなってしまった。後日に調べてみてわかったことだが、この石段はかの戦国武将、加藤清正公が寄進しという。恐れ多い。

そうとは知らずにそれでも石段を上る気にさせたのは、行動経済学者に言わせれば「サンクコスト(埋没費用)が背中を押した」ということになるだろうか。私たちは「せっかく来たのだから」ということで、そこに来るまでの時間や労務が勿体ない、初期投資が惜しいために計画を中止することが出来なくなる。
石段を上りきってみるとびっくりするくらい多くの人で混雑している。屋台も出店していてさながらお祭りのようだ。何せここには初めて伺ったものでこの混雑ぶりがいつものことなのかどうかは定かではないのだが、おそらくこの集客力は桜の魅力がなせるものだろう。
ナッジ
さて、「ナッジ」という言葉をご存じだろうか。最近は相応に知られてきた概念であり、行動経済学分野においては、課題解決のための打ち手として使われる。元々は「ひじで突く」が語源であり、親ゾウが子供のゾウを鼻で押すように、そっと、向かうべき方向へ誘(いざな)うことをいう。さながら桜は私たちを街に誘うナッジである。
ナッジなる概念を一躍有名にしたのは、アムステルダムの空港において男子トイレの小便器にハエのイラストのシールを貼ったという政策である。女性にはよくわからない話かもしれないので申し訳ないが、ただそれだけで多くの人がハエの的をあてるように用を足すようになり結果的に便器からそれた小便の清掃労務が8割、年間にして1億円ほど減弱することに成功したという。
アムステルダムの空港をはじめ数々のアイデアブルなナッジを提案し多大な経済効果に貢献したリチャード・セイラ―は2017年にノーベル経済学賞を受賞している。一方、こうしたアイデアそのものは科学でもないし、一生懸命、旧来の経済学のお勉強をすれば提案できるようになるとも思えない。「ノーベル賞をとりたい」という夢をもつ経済学者は多いと思われるが、何がその近道になるのかは行動経済学を世に広めた心理学者、ダニエル・カーネマンがそれを受賞したあたりから段々と読みにくくなってきたようだ。
概念に名前を付ける
「ナッジ」なる言葉は確かに行動経済学がその存在を有名にしたことであるからして、先にみた空港のトイレのように経済学的価値に貢献するための打ち手というのが王道だろう。一方、シンプルに「お金を使わずに行う工夫」としてとらえるならば、おそらくは太古の昔から社会に存在していたものと思われる。人の心理を巧みに使って人々を誘うというのがナッジの本質なのであれば、マーケターであったり詐欺師であったり、玉石混交な概念といえるだろう。
認知学の世界では、私たち人類は命名することでようやくその存在が明確になり認知が進むとされる。名も知らぬ花をみてもそこにその花が咲いていたという事実を記憶することは困難であるが、その花が「ラベンダー」であると知っている人はそれを記憶することが容易になる。花のような物理的なものでなく概念の分野でも同様であり、例えば「ハラスメント」なるものはこちらもおよそ太古の昔から存在していたであろうに、それを知覚できるようになったのはこの概念が命名されたからである。「ナッジ」も同様だ。
ハラスメントがそうであるように、ナッジの定義もまた多分に漏れずその境界線が曖昧である。優れたマーケターのマーケット戦略はその「社会的に向かわせたい方向」を向いていればナッジ、その逆方向へ誘う場合は、ナッジの反意語として「スラッジ」という言葉がこのところは使われるようになってきた。同じ“お金儲け”であっても、スポーツジムに通わせるのは「ナッジ」、ジャンクフードを買わせるのは「スラッジ」。商売する側は同じように一生懸命働いているにも関わらず、行動経済学では社会的善悪の判定で違う用語が使われる(詐欺師のやることは一律にスラッジといってよさそうだが)。
ヘルスケア行動×ナッジ
先回紹介したところの、地域の住民を健康診断に向かわせるために損失回避性という心理を訴求するチラシを配布する、といった打ち手は直接的に経済的な成功をおさめるというものではないのだが、「社会的によい工夫」でありその意味では「ナッジ」として分類される。もし「ナッジ」という言葉がなければこうしたアイデアが思いつかなかったのだとしたら、「ナッジという言葉がナッジした」とでも言おうか。このところはヘルスケア行動の促進にナッジを使おうという機運が高まっている。
実際のところ、旧来のチラシ配布と比して印刷代も配布の手間も増やさず、ただ表現を工夫するだけで健康診断をする人を増やすという“魔法”は、社会にとっては大歓迎といえるだろう。国会でも社内会議でも「その予算は確保されるのですか?」といったように活動のための予算がしばしば問題となり提案を断念するということがあるが、“親ゾウが子ゾウを鼻で押すように”、お金をかけずに目的達成を向上させるならば何よりだ。

ヘルスケア行動促進のためのナッジとしてはストックホルムの駅の階段をピアノの鍵盤にペイントした例が有名だ。人々はピアノの鍵盤の上を歩きたくなり、横にあるエスカレーターではなく階段を使う人が66%も増えたという。市民の健康促進を目的とした打ち手だとすれば、ペイント代のモトはとれたといえるだろう。
医療分野におけるナッジのお話となると、必ずといってよいほど登場するのが臓器移植に関する同意取得の話だ。日本では臓器移植の提供に関する意思表示をしている人が10%だというのに、フランス、ベルギー、オーストリアなどは軒並み99%を超える。
何故にこれだけの差が生じているかといえば、高い同意率の国は「拒絶をしなければ同意したものとみなす」、つまりデフォルト(初期値)として「同意」しているからだ。人はズボラな生き物であるから、購入したスマホの待ち受け画面やゲーム内のアバターを変更しないでデフォルトのままとしている人も多いことだろう。これがデフォルト効果と言われるものである。
EBPM(Evidence-based policy making、根拠に基づく政策立案)
さて、ナッジをナッジたらしめるもの、エビデンスある政策立案とするうえで相性がよいのがEBPM、根拠に基づく政策アプローチである。健康診断を促進するうえで「損失回避という心理に訴求したチラシにした方がよい」というアイデアはあくまで仮説でしかなく、実際にそうなのか仮説検証をするというのがEBPMだ。
EBPMというのを広い意味でとらえるならば様々なデータを駆使することや、有識者の意見徴収をすることまで含むのだろうが、より狭い意味でいえば要するに「社会実験を、医薬品の承認申請と同じ要領で行う」ことである。つまり、比較対照群をおいて、果たしてどういったチラシがベストなのか有意差検定などを施して白黒をつけるというわけだ。
こうしたアプローチは欧米ほどではないものの、日本においても少しずつ広がりをみせてきている。環境省のサイトをみると*、ナッジ・ユニット(BEST、Behavioral Sciences Team)なる活動を確認することができる。
ここでは自治体の取り組みを「ベストナッジ賞」として表彰するなど、“ナッジ”を仕掛けている。一例として2022年では京都の四条通りで問題となっていた交差点や横断歩道でのタクシーの違法な客待ち駐車削減として工夫を凝らした看板がこれを受賞している。
違法とは知りつつも人通りの多いこの場所ではなかなかタクシーの駐車が減らなかったというが、「ドライバーさん、違法駐車みんな見てますよ」「この窓から見えるタクシーは、違法駐車中です」なる看板は、その看板に“小窓”をあけたユニークなデザインだ。これを受けてもなおそこにタクシーを駐車させるというのはかなり気が引けることだろう。
最近の例では二酸化炭素排出を減らすためのナッジなどがここで共有されている。環境省ではこうしたナッジをデータベース化する活動も進めていて、奏功したナッジについては是非とも登録して欲しいとのことである(が、こうした活動があまり知られているようには思えない?!)
行動経済学の「死」
さて、旧来の経済学を批判的に再考し、ホモエコノミカス(経済的合理人)ならぬ、生身の人間の心理をそれとして整理した行動経済学は時代の寵児として脚光を浴びる一方で、少し影を落としてもいる。
コトの発端はアメリカ・ウォルマートの行動科学チームを率いるジェイソン・フレハさんが「行動経済学の死」というタイトルでネット公開されたことがきっかけである。行動経済学分野で発表された研究のうち、再現性に問題がある研究がかなりあるというのだ。ここに加えて行動経済学分野の著名人であるダン・アリエリーさんの論文にデータ操作の可能性が指摘されたことで、ネガティブな印象がさらに増大することになった。
「死」と表現するのはさすがに大げさであっても、「行動経済学の限界」と表現するのであれば、当の行動経済学者らも承知するに違いない。留意事項が様々にあるのだ。
例えば先に紹介した階段をピアノの鍵盤にペイントしたことによってエスカレーターではなく階段を使うようになったというナッジは、果たしていつまでその効果が続くのか、持続性の問題がある。行動経済学分野の言葉を使うならば「感応度逓減の法則」だ。さらにいえば他の文化慣習の国でも同じだけの効果が発揮されるのかという一般化の問題もあるだろう。階段の段数が違うだけでも再現性は違ってくるはずだ。
臓器移植のデフォルト効果についても、これを「臓器移植は同意率が高いほどよい」と定義するのであれば国のヘルスケア戦略として素晴らしいが、一方で「本人の意思はどうなるのか」という倫理の視点でみると様子が違ってくる。要するに「ノー」と言わなかったら「イエス」とみなす、推定同意の打ち手は、ウラを返せば本人の意思を尊重しているとは言えないという問題を内包している。
ただ、こうした一面だけをとらえて行動経済学を学問として亡き者にしようというのはおかしな話だ。心理学分野において結果の再現性の課題であるとか、研究不正の実例などはこれまで本コラムでもしばしば取り扱ってきたように「行動経済学だけに死を」という話では決してない。いかなる学問領域でも様々に課題や限界があり、これを生かすも殺すも私たち次第というのが妥当な受け止め方だろう。
妄想の中のナッジ
池上本門寺に花見に行ったのが4月になったのは、東京都で桜が満開となった週末が2週続けて雨模様だったからである。桜が人々を街に繰り出させるナッジだとすれば雨はスラッジといったところか。
池上本門寺の石段は96段あるという。通常の階段と比べたら確かに長い階段なのだろうが、寺院一般として考えればこれを上りきるというのは突出してハードなミッションとは言えないだろう。この地は日蓮上人の入滅の地であり、明治維新の頃は西郷隆盛軍がここに陣を構えて政府軍に抗したという、由緒正しき“聖地”なのである。

石の一段一段が大きいので上るには骨が折れるが、こうした歴史的背景を事前に知っていればその一歩一歩にもまた趣(おもむき)のあることだろう。ふと頭の中でよぎったこと―この階段をもしピアノの鍵盤にペイントしたらどうだろう―という不届きな妄想は、決して口に出して話してはいけない。心の中にしまっておくことにしよう。
第31回おわり。第32回につづく