第30回:同調圧力の有効利用
- Erwin Brunio
- 2023年3月24日
- 読了時間: 9分
更新日:2023年4月12日
2023年3月27日
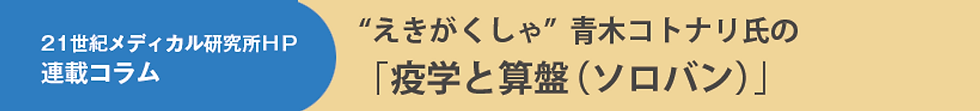
2020年10月20日から、3週間に1回、大手製薬企業勤務で“えきがくしゃ”の青木コトナリ氏による連載コラム「疫学と算盤(ソロバン)」がスタートしました。
日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボWEBサイトに連載し好評を博した連載コラム「医療DATAコト始め」の続編です。「疫学と算盤」、言い換えれば、「疫学」と「経済」または「医療経済」との間にどのような相関があるのか、「疫学」は「経済」や「暮らし」にどのような影響を与えうるのか。疫学は果たして役に立っているのか。“えきがくしゃ”青木コトナリ氏のユニークな視点から展開される新コラムです。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第30回:同調圧力の有効利用
同調圧力
マスクの着用が任意となった。もちろん油断は禁物であり、感染症の研究者からは「第9波が恐らく発生するだろう」という声も聞こえてくる。それでも誰もがマスクを着用していたこの数年間の“時代”が一区切りを迎えたという意味では、1つのエポックメイキングな出来事と言えるだろう。
ところがどうだろう。私の住む街も、TV中継に映る街も、その様子はこれまでと特段の違いがないようにみえる。心配性な国民性がそうさせるのか、それともマスク“慣れ”という、惰性・慣性の法則のような力が働いているのだろうか。同調圧力のせいではないか、といった声も多いようだ。
どうやら日本人は他国と比しても特段、人の目を気にする国民性であると言われている。互いにそのつもりがなくてもマスクを外すことで他人にどうみられるのだろうかと、そこに存在するのかどうかもわからない圧(あつ)を感じ、結局のところいましばらくはマスク社会が続くのかもしれない。
同調圧力という言葉は主に社会心理学分野で以前からよく知られているもので、その影響によって合理性のない言動をすることは同調性バイアスと呼称する。実際には誰かに批判されたりすることがなくても、何となく追い込まれてマスクを外せないというのでは合理性がない。もはや感染予防よりも同調性バイアスがマスクだらけの社会をコントロールしているのかもしれない。
今回は日本人には特になじみ(?)のある心理作用として、同調圧力・同調性バイアスについて概観するところからはじめてみよう。そのうえでこうした“合理性のない心理バイアス”を、より社会のための“合理性のある”使い方がないものか考察してみたい。
他人の目を不必要に気にするという、いわば臆病者の特性のような響きではあっても視点を変えれば周囲への思いやりにも関連する心理である。本コラムのテーマ「疫学」は公衆衛生に直接かかわる学問領域であり、案外と相性が良いかもしれない。
同調圧力の因数分解
同調圧力・同調性バイアスが一体どのような概念的構造を成しているのかという研究は19世紀頃より社会心理学分野を中心に行われている。いくつかの因子が組み合わされてい
ること、あるいは同じように圧は感じているものの、その本質はケースバイケース、個々人で少し違っているようだと整理されている。
(1) 多元的無知
周囲の言動をみて「きっと大したことない」と判断させるといった同調圧力の主は「多元的無知」と呼称する。ラタネとダーリーによる煙の実験が有名で、通気口から目がかすむほどの煙が入ってきた場合、1人だけでいると通報する人が多いのに、3人でいた場合、自分以外の2人が通報しないと自分も通報しないという愚かな判断が多元的無知である。言い換えるならば「一人ひとりは聡明なのに、みんなが集まるとおバカになる」。

この実験では1人の場合は2分以内に55%、4分以内に75%の人が通報行動をしたが、「通報しない」サクラ2名と一緒に3人でいた場合、通報する人は12%に留まったという。
(1) 責任の分散
以前、本コラム(第26回)でも取り上げたが、キティ・ジェノヴィース事件において「きっと誰かが通報してくれるだろう」として、結局のところ誰一人、通報しないといった愚かな帰結をもたらすような事象については、多元的無知に加え「責任の分散」の要素が関与しているものと整理されている。人数が多いと責任感が薄れるのだ。
ビジネスシーンでも責任の分散、多元的無知が生じることがある。例えば作成したビジネス文書について大人数にチェックをお願いしても誰からもレスがこない、という経験をしたことはないだろうか。むしろ人数を絞るとか、「1~5ページは鈴木さん、6~10ページは田中さん、11ページ以降は山田さん、お願いします。」とすればそれぞれ任命された人たちはしっかりとチェックしてくれる。責任が分散しないからである。
(2) 評価懸念
地震大国である日本はその“耐性”があるためか、少々の地震で大騒ぎするような人はあまりいない。地域性もあるようで、地震の比較的多い東京に引っ越したばかりの関西の人は、その無反応ぶりに驚いたりするらしい。多少の揺れに動揺をみせないという態度は、周囲から大げさな人に見られやしないだろうかという、“世間体を気にする”心理に関わるもので、この同調性バイアスは「評価懸念」と呼称される。
(3) ピア効果
1973年に行われた、心理学者のハントとヒラリーによる迷路学習実験では、「迷路パズル」を解くスピードは1人よりも2人、3人の方が早まることを確認している。同じ意識や目的の者同士を同じ場におくだけで、お互いに切磋琢磨して成果が向上する現象は「ピア(同僚)効果」といわれる。
このように、どうすればより生産性が向上するのかといった課題はビジネス一般の課題でもあり様々な研究が行われている。中でも特にアメリカのホーソン工場で行われた社会実験はその規模の大きさから有名であり「ホーソン実験」としてネット検索をすればたくさんヒットする。この実験では心理面だけでなく照明の明るさなどの環境面も比較検証がされている(結果的に影響はなかったようだ)。数人の同僚を選抜して一緒に仕事をさせることで1人でいるよりも成果が高まるのは、人間が社会的動物であることの特性として普遍的なことのようだ。
(4) 注意のコンフリクト
テスト中に試験官が自身の真後ろに立たれたりしたら気になったりはしないだろうか。なんだか人の目が気になる、これは注意のコンフリクトと呼称される。前述した迷路学習実験では、単純な迷路パズルでは人数が多い方が正解を解くのが早まるのに対し、複雑な迷路パズルではむしろ遅くなるという結果が確認されている。
(5) 生理的喚起
同調圧力を構成する概念の中でもユニークなのが“生理現象”説である。ラットが餌を食べる行為も、アリが巣作りに励む行為も、周囲の目があると促進されることが確認されている。これを「生理的喚起」と呼称する。人間にもこうした生理現象があるらしい。
さて、同調圧力なる概念を切り取ってみてもこれだけの研究成果に基づく知見が蓄積されているのである。こうした心理学分野の成果が案外と社会課題の解決に貢献していないように思われ、歯がゆく感じられる。心理学分野では社会的にプラス方向への活用がされた場合を「社会的促進」、その逆を「社会的抑制」と呼称するが、以降は実際に社会的促進がみられた事例を概観してみよう。
フレーミングへの活用
健康行動へ向かわせるうえでの難敵は現在志向性バイアス、つまり「目先の幸せ優先主義」といえるだろう。嫌なことは先延ばししたい、禁煙もダイエットも長続きしないのはこの難敵のせいである。定期的な健康診断の促進も同様、腰の重い人に検査センサーへ足を運ばせることは容易なことではない。
この課題について、先回紹介した「フレーミング」を使って社会的促進が得られた実験があるので紹介しよう。
大腸がん検診の受診率を向上するためのメッセージとして、下記の2パターンではどちらが効果的だろうか、まずは考えてみていただきたい。
パターンA:
今年度、大腸がん検診を受診された方には来年度、大腸がん検査キットをご自宅へお送りします。
パターンB:
今年度、大腸がん検診を受診されないと、大腸がん検査キットをお送りすることが出来ません。

これは2016年に東京都八王子市にて実際に行われた社会実験であり、当年5月に検査キットを送ったものの10月になってもまだ検査をしていない人へランダムに割り付けた2種類のメッセージをはがきで郵送したというものである。結果は以下の通り。
パターンA: 22.7%(399人/1761人)が受診
パターンB: 29.9%(528人/1767人)が受診
なあんだ、20~30%程度しか効果がないのか、と言うなかれ。人の行動を変えるというのはダイエットがそうであるように簡単なものではなく、おそらくこの督促ハガキがなければ受診してなかったであろう人の行動を変えたというだけでも自治体としてはハガキを送った甲斐があるというものだ。
そのうえで「フレーミング」としてパターンBの方が高い成果であったのは、プロスペクト理論(第28回参照)で示した人の損失回避性に訴求しているからだと整理できる。
ところで、「もしそうだとしたら最初から全員にパターンBのハガキを送った方が良かったのでは」という声も聞こえてきそうだ。確かにその意見は一理あるのだが私は八王子市のアプローチを賞賛したい。
こうした複数種の介入アプローチを無作為に割り付けて実施するのは医薬分野における無作為化臨床試験を応用したもので、EBPM(Evidence Based Policy Making)と呼称される。仮説や確信がどうであれ、実際に行って検証してみるという態度は、ひょっとしたら仮説が間違えていて、以降ずっと無駄な政策をし続けるといいう愚を避ける意味で極めて重要なことなのである。
少し話が横道にそれてしまったので、督促状のフレーミングの話に戻そう。他国の事例では納税喚起の事例が有名だ。
「イギリスでは10人に9人が税金を期限内に支払っています。あなたはまだ納税を完了していない極めて少数派の人です。」
この文章を加えたことにより例年と比して納税率が5.1%に上昇したという話であるが、これは先に述べた同調圧力、ピア効果を生かしたものだ。同調圧力は日本人にだけ特有なものではない。
あくまでこれは納税を目的としたものだが、国としてマイナンバーの取得やマスクの着用喚起等々を促進したいときに「あなたは少数派です」とするのは、特に同調圧力に弱いといわれる日本で有効打となる政策だろう。八王子市の事例のように検査促進のテクニックとしても使えそうである。
マスク継続主義
今年は花粉の飛散量が多いらしく、私も例年になく花粉症の薬を早めに始めることとなった。政府の方針としてマスク着用は任意ということになったのだが、私自身はコロナではなく花粉症という事情で、3月から4月にかけては例年通りマスクを付けての外出を予定している。

マスクを着けてさえいれば同調圧力を避けられるというものでもないらしい。「あの人、ずっとマスクする主義の人だ」と思われやしないだろうか。「同調圧力に屈している人だ」と思われやしないだろうか。
「私はマスク継続主義ではなく、単なる花粉症患者なのです!」と訴えたい。「花粉症対策」と印字されたマスクが売られていたら、買おうと思っている。
第30回おわり。第31回につづく




