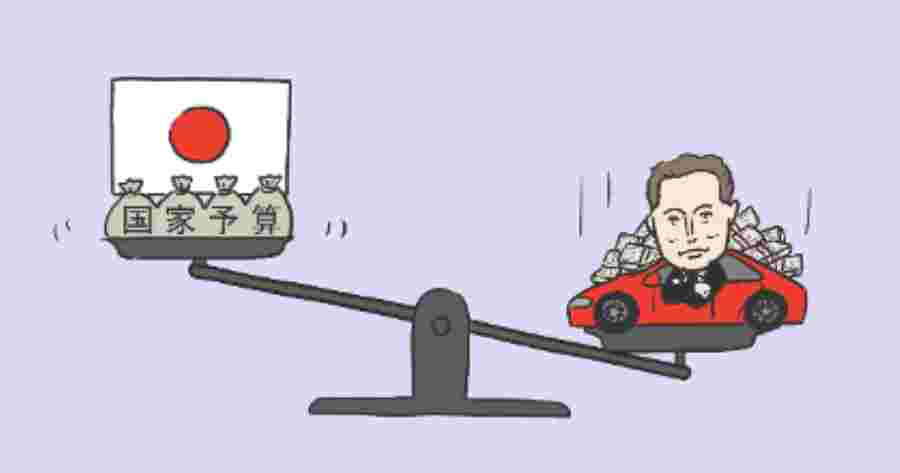第18回:非科学を科学する
- Erwin Brunio
- 2025年5月30日
- 読了時間: 12分
更新日:2025年6月25日
2025年5月30日

2020年10月20日から連載開始した「疫学と算盤(そろばん)」は、昨年末、通算第36回を数え無事終了しました。36回分のコラムはご承知かと思いますが、当WEBサイトにてダウンロードできる電子書籍となっています。2024年1月からは、コラム続編の「続・疫学と算盤(ソロバン)」がスタートします。筆者・青木コトナリ氏のコラムとしては、日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボのWEBサイト連載の「医療DATA事始め」から数えて3代目となる新シリーズの開始です。装いを変え、しかし信条と信念はそのままに、“えきがくしゃ”青木コトナリ氏の新境地をお楽しみください。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ氏の
「続・疫学と算盤(ソロバン)」(新シリーズ) 第18回:非科学を科学する
未来の予言書
訪日外国人旅行者の数が激増しているというニュースは聞き飽きているところだが、これに逆行するかのように香港では、日本行きの飛行機が減便したというニュースが聞こえてきた。その理由がどうやら“オカルト”なようなのである。

たつき諒さんが書き続けていた夢日記を題材とした漫画「私が見た未来」の初版刊行は1999年。今から26年も前のことである。その中に「大震災は2011年3月」という記載があり、これがあたかも東日本大震災を言い当てているようだということで2011年はネットなどで話題となっていたのだという。そしてこの漫画の復刻版が今般、出版され大ヒットしているのであるが、その中にある「本当の大災難は2025年7月にやってくる」なる“予言”が香港国内で話題となり、これが広まって日本旅行を予定する人が激減したのだという。ウワサは台湾にも飛び火し、台湾からの日本旅行キャンセルが相次いでいるという。
「そんなオカルトを香港や台湾の人は信じるのか」と非難するのはお門違いだろう。世界中に旅行先の選択肢があるというのに、広まったこの悪いウワサをおしてまで日本旅行に固執するのはむしろそちらの方が変ではないかと言えなくもない。日本国内での過去の歴史を振り返ってみても、悪いウワサが広まったせいで商品が売れなくなった、事業が立ち行かなくなったなど、ウワサが転じて「実際」として社会が動揺したことは幾度もある。たかがウワサでしかないが、それが実社会に大きな影響をもたらすというのはどの国であっても特に珍しいことではないのである。
さて、本コラムは科学“推し”であり、オカルトのような非科学には否定的という立場をとらないといけないのかもしれない。そうではあるのだが、ウワサが実社会に影響を与えることがあるということ自体はファクトであってややこしい。そこであえて今回は「非科学を科学する」という自己矛盾的な考察に挑戦してみたい。
集団主義・権威主義・無謬(むびゅう)主義
科学の進歩した現代では「おバカ」に見えていることであっても、人類の歴史において何十年、何百年も信じられていたというものもある。NHKで2025年3月まで放送されていたアニメ「チ。―地球の運動について―」は、長く信じられていた「宇宙の中心は地球である」という考えに疑いをもった主人公が権力との折り合いに葛藤するといった、地動説をテーマとしたものである。もちろん、現代の私たちは地球が宇宙の中心などではなく太陽の周りを回っていることを知っている(あるいは信じている)。
そうはいっても私たちがその時代にタイムスリップしたとして、常識を覆すような地動説を唱えることが出来るかといえばそれは簡単なことではないだろう。天文学に限らず普段の生活にあっても、「これは間違っているのでは?」という疑念が生じても何ら指摘しない、指摘出来ない人は多い。割と好き勝手な発言をする人だと周囲に思われているらしいこの私でも、「その場しのぎに同調しておく方が社会人マナーというものだ」、「波風をたてても得なことはない」などと自分に都合のよい理屈をつけて反論しないことも少なくない。
特に日本では権威に対して異論を唱えることははばかられる傾向があり、こうした「権威には反論しない」文化は、結果として不適切なほどに権威者に対してへりくだる権威主義や無謬(むびゅう)主義につながってしまう。日本の行政は「前任者が行ったことを間違っていたとは決して言わない」という規則が、あたかも存在しているかのように立ち振る舞う、という話はよく聞く話である。
そもそも親や上司の言うことを聞くという慣習は日本にあって美徳とされ、それは儒教の影響も大きいのだろう。明治維新という新しい時代の幕開けに貢献した坂本龍馬の人気は絶大であるが、一方でいわば盲目的に江戸幕府に対して「忠誠」を重んじた新選組もまた、人気がある。上司に忠誠を誓うことを美談として取り扱う忠臣蔵は度々、ドラマ化される。日本人は忠誠・忠義が好きなのだ。
こうした背景もあってか政策の決定や論文の読了など、本来は「忠義」など気にせずに自由に発言し、批判的吟味をすべき局面にあっても日本人はおとなしい。特にそこに権力の影が見え隠れする場合はヘンテコな意見や主張が通ってしまうことがあるような印象を受ける。権威を批判しないことのこっけいさを題材にした「裸の王様」はアンデルセンの作品であり、何も権威主義は日本だけのことでもないのかもしれない。とにかく、かくして集団主義・権威主義・無謬主義はしばしば私たちを非科学の世界に取り込んでしまうのである。
しろうと理論
他方、日本の権威主義とは違うタイプの、科学への脅威もある。人類が知り得ないことは全て神様、あるいは神様でなくても何らかの形而上学的な存在がそれをコントロールしているのだという解釈は様々な文化圏でみられるものである。
例えば日照りが続いて作物が育たない、といったときに行う「雨乞い」などは異なる文化間でも共通にみられるものである。日本でも「オテント様」という言葉で形而上学的な存在が「雨を降らせない」と意思決定していると長いこと理解されてきた歴史がある。確かに、現代のような科学が進歩していない時代にあっては、地震や雷がまるで「感情としての怒り」のようにも感じられるのは共感も出来るところで、雷オヤジと同じように「神様がお怒りになっている」と解釈するのは自然なことだったと言えるかもしれない。
社会心理学者ファーンハムは多くの人が科学的な説明よりも、自分なりの解釈や思い込みを優先してしまう傾向のことをLay Theoryという概念で整理している。これは天変地異に対する受け止め方だけでなく、対人についても当てはまる概念である。
例えば、私たちは日常の中で「こういう言動をとるということは、あの人は私に好意があるのかしら」といった思い違いをすることがある。あるいはその逆に「こういう言動をとるということは、あの人は私に悪意があるに違いない」などということもあろう。あおり運転の加害者は、大抵の場合において被害者の運転を自分の車に対する「悪意」であると思い込むという帰属意識で、その仕返しとしてあおり運転をしたと供述するらしい。
このような原因がどこに帰属するのかを知ろうとする行為について、心理学分野では原因の帰属理論として称して研究が盛んな分野の一つである。帰属理論の一つである敵意帰属バイアスは、子供がイスに足をぶつけたときに「イスが自分に意地悪をしている」と解釈してしまうアニミズム(主に幼少期の擬人化傾向)から、あおり運転という社会問題まで幅広い。
先のLay Theoryも帰属理論研究の中の一つであり、日本語で「しろうと理論」と訳されている。決して珍しい現象ではないのである。あおり運転とまではいかないが、私たちも「あの人は私のことが嫌いなのかも」という思い違いを案外とよくしているのかもしれない。イスに対して仕返しとばかりにキックをして、さらに足を痛める子供に対して「バカだな」と笑えるほど私たち大人は賢くはない。
トンデモ医療
医療分野にあっても、現代医学では決して許されない「非科学」、間違った治療法が長く実施されてきたものもある。例えば瀉血(しゃけつ)、簡単にいえば血を抜くという治療は発熱、感染症、高血圧、頭痛等々、様々に有効な手段であると信じられてきた治療法である。これはヒポクラテスの四体液説に基づき、体液のバランスを整えるため、というロジックだったらしいのだが、今ではむしろ害を及ぼすことが知られている。今となってはトンデモない治療選択肢といえよう。

また一方で、身体に傷をつけ、そこに毒を塗るなどという治療もまた、およそトンデモない医療にその昔であれば感じられたことだろう。もともとトルコで知られていた天然痘の予防法として行われていたこの治療がイギリスで紹介されたときには医師らは鼻であしらったという。しかしながら、そのトンデモ医療と思われたところの処置こそが現代でいうところのワクチン療法なのであり、今ではその有用性が広く常識として知られている。このように直観的には受け入れがたいような行為が、実は正しいということもあるのだから、あまり直観を全面的に信じてはいけないのだろう。
かくして、ではそのトンデモない医療として当初は認識されたワクチン療法がどのようにしてイギリスでは受け入れられたのかという、非科学から科学への“脱却”について歴史を振り返ってみよう。
臨床試験のはじまり
只今は医療現場から得られた情報(Real World Data、RWD)を利活用すべきという機運が高まっており、私もその促進活動をしているところである。特段、治験と呼称されるところの医薬品として承認するかしないかの最終テストにあっては、しばしばニセ薬(プラセボ)との比較で勝たなければ承認しないというアプローチがとられるのだが、これにRWDを利用できないかという期待感が広がっているのである。
治験を行う治験医師は、研究者である一方でやはり医師なのであり、患者(被験者)を騙すかのようなニセ薬を処方することにひどく心が痛むという。であるが故にそこにRWDを使えるならばプラセボを処方する人がゼロになる世界が来るのではと夢見る人もいるのだが、これはちょっと無理難題にも思える。
やはり従来通りの無作為化二重盲検、という研究デザインこそがその真偽を問うのにふさわしく、RWDがすんなりとその代用に使えるということにはならない。RWDで“代用”できる場合はノーチャンスではないものの、やはり偏見や思い込みなど、「非科学」が入り込んでしまう余地があるからである。
話を元に戻そう。傷口に毒を塗る、それが有効な手段なのかどうかを確認するために行われたテストこそが、世界初の臨床試験と呼ばれるものである。具体的には当時、猛威を振るっていた天然痘の予防法として、天然痘の患者さんから接種した膿疱やカサブタを健常な人の傷口にすりこむという方法である。これを施した人たちと施していない人たちとで、罹患する確率が下がるかどうか、罹患したとしても軽症で済むかどうかという実験をしている。およそ現代の倫理感では許されざるところの囚人と孤児が被験者とされたというが、この実験によって予防法として有効であることが確認され、この予防法は人痘法と呼称されるようになる。
大航海時代、再び
先回は只今の資本主義らしさを象徴する金融の歴史として、大航海時代における船の沈没リスクを回避する策としての株式を紹介したところであるが、実際のところは当時、海難事故による死者よりも壊血病による死者の方が多かったことが知られている。
壊血病は私たちの命を短期間で奪うという恐ろしいものである。発症した当初は倦怠感をおぼえ身体に力が入らなくなる。足がむくみ歯茎が腫れ赤黒い血が出る。嚙む力が無くなり食事が出来なくなる。皮下出血が止まらずやがて死にいたるという。インドへの航路を開拓したことで知られるバスコ・ダ・ガマは乗組員の半分以上を、世界初の世界一周を成し遂げたマゼランに至っては乗組員の3分の2をそれぞれ壊血病で失ったという。大航海時代を通して壊血病で命を失った船員の総数は200万人にものぼるというのである。
もちろん現代の私たちからみたならば、その壊血病の治療法として行われた瀉血が無意味であることは知っている。何ら有効な治療法が見つからない中にあって、1947年に医師であるジェームズ・リンドが行った治療間比較が現代における無作為化比較試験の原型といわれるものである。具体的には下記のような6種類の治療を比較している。
(1) アップルタイザー(1ℓ)を与える
(2) 硝酸薬(4mℓ)を与える
(3) 酢(80mℓ)を与える
(4) 海水(250mℓ)を与える
(5) ナツメグ、ニンニク、芥子の種子、西洋わさび等の種子や樹脂を与える
(6) オレンジ2個とレモン1個を与える
この研究が世界初の無作為化試験であると言われる所以の一つは、治療方法以外の全てについて均質化にこだわったところだろう。リンド医師の科学的感性の高さがうかがえる。この試験の結果として第6の治療群だけが突如としてはっきりと効果が見られ始めたのだという。また、研究倫理という視点においても、被験者全員が壊血病に苦しむ人たちなのであり、囚人や孤児を被験者とするような非人道的な行為はみられない。
かくして、今ではビタミンC欠乏症の一種とされる壊血病の脅威はこのような無作為化臨床試験というアプローチを通して、非科学的治療が蔓延していた世界から、科学的合理性のある治療方法へ導いたのである。
非科学主義?!
オカルト、敵意帰属バイアス、瀉血。人はどれくらい非科学に影響を受けているのだろう。また、どれほど科学的根拠について信頼を向けているのだろう。前述したリンド医師による無作為化比較試験の結果もその後しばらくは無視され続け、治せもしない瀉血治療が壊血病患者に対して標準的治療として20年ほども続いたのだという。フルーツを与えるだけで快方に向かうと言うのに、不必要に血を抜かれ、命をおとした人たちは浮かばれない。他方、地動説を教会が認めたのは2008年のことである。どんなに科学的にみて合理性があっても、どんなに確からしい根拠があっても、自身の思い込みを払拭するのは難しいことらしい。

科学の進歩した現代にあっても敵意帰属バイアスを契機とした犯罪は後を絶たないし、雨乞いの儀式を続けている文化圏も未だにある。神を信じる人にしてみれば無神論者こそが間違いであり不届き者だろう。幽霊など信じない、と言っている人でも事故物件に住むのは気が引けるというものだろう。統計学者の某先生も「自分は雨男だから」などと言って笑う。かくしてオカルトをはじめとした「非科学」はその影響が衰えそうにない。
私は疫学をきっかけとして科学をもっと世の中に広く普及させたい、という思いで仕事をしている。その一方でしばしば神社やお寺で参拝するし、おみくじで大吉が出るとうれしかったりもする。普段の生活は大いに非科学に囚われているのである。
さて、「私が見た未来」にある2025年7月について。とりあえずは、旅行などせずに家でおとなしくしていようと思う。
「続・疫学と算盤(ソロバン)」第18回おわり。第19回につづく