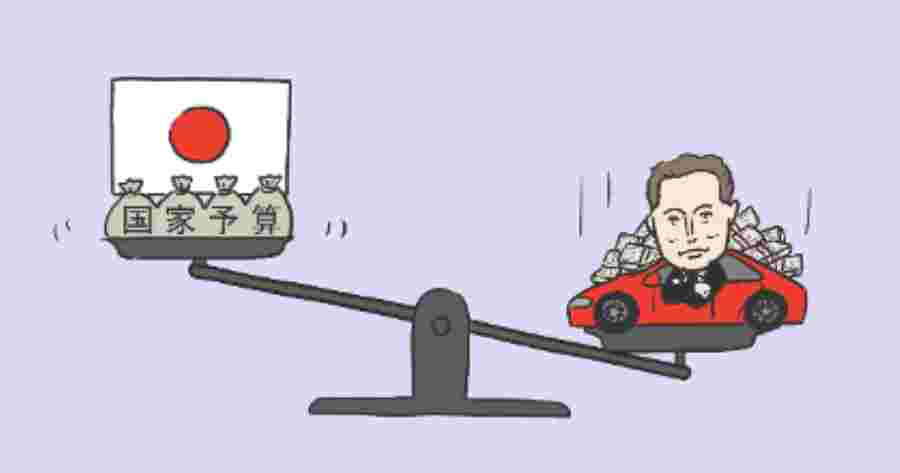第19回:日本の疫学のはじまり
- 21medicaljp
- 2025年6月25日
- 読了時間: 13分
更新日:2025年7月31日
2025年6月25日

2020年10月20日から連載開始した「疫学と算盤(そろばん)」は、昨年末、通算第36回を数え無事終了しました。36回分のコラムはご承知かと思いますが、当WEBサイトにてダウンロードできる電子書籍となっています。2024年1月からは、コラム続編の「続・疫学と算盤(ソロバン)」がスタートします。筆者・青木コトナリ氏のコラムとしては、日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボのWEBサイト連載の「医療DATA事始め」から数えて3代目となる新シリーズの開始です。装いを変え、しかし信条と信念はそのままに、“えきがくしゃ”青木コトナリ氏の新境地をお楽しみください。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ氏の
「続・疫学と算盤(ソロバン)」(新シリーズ) 第19回:日本の疫学のはじまり
スティグマ?!
2023年4月に入学した公衆衛生学の大学院をこの3月に無事、卒業(修了)することが出来た。当初に想像していた程には楽な卒業ではなかったのは、どうにも今どきのコミュニケーションツールを私が正しく操作できなかったことによるところが大きい。連絡がきていることに気付くことが遅れたり、出席操作をしたハズの授業が何故か欠席と認識されていたりと、そのようなことの連続であった。
思えば最初の関門は幼少の頃のワクチン接種に関わるところの、種々の免役を獲得しているという証明書を入学までに提出せよ、というミッションであった。これは大学病院の敷地内でも授業があるためなのだそうで、医療者や患者に対する無用な感染リスクを避けるうえでの措置だという。そうは言われても幼少の頃に受けたワクチンが何で、要求されている免疫を全て獲得しているかどうかの確証は全くない。提出期限の直前になってようやく無事に全ての免疫を獲得していることがわかったときには、これでどうやら入学できそうだと、胸をなでおろしたのである。
大体においてワクチン接種自体にも他の学生らと私との間には世代間ギャップがある。右上腕部に残る、いわゆるハンコ注射の跡はもはや根絶した天然痘ワクチンの接種跡であり、その義務化は1976年に満了している。然るに、20代から40代の同級生にはハンコ注射跡があるハズもなく年齢がバレるというのか、そういう意味では社会的烙印(スティグマ)と言えなくもない。

天然痘の根絶によって腕へのハンコ注射(種痘)は廃止となったのであるから、人類としての視点からすれば喜ぶべきことである。他にも座高を測ったり色覚異常を確認したりといった検査項目も廃止されている。無駄な検査、あるいはプライバシーへの配慮が足りない検査が無くなるのは時代の要請、進歩ともいえよう。
さて、以前は実施されていた、膝のところをハンマーで軽くたたいて足がちゃんと反応するかどうかという検査は、年配の人ならば一度は経験もあるだろう。神経系状態を評価する目的で以前は実施されていたのだが、この検査も今では廃止されている。我々の世代ではこの検査のことを「脚気(かっけ)の検査」と親から教わってきたのであるが、今回テーマとして取り上げるのはこの脚気にまつわるお話である。
脚気とは
ハンマーで膝を軽く叩くという検査を受けた人ならばご存知だと思うが、足がピコン、と反射的に動くさまはちょっと滑稽でもあり、その印象もあってか脚気はとるに足らない病気だろう、などと想像していたものである。しかしながら日本の病気の歴史を振り返ってみると脚気は一大事であって多くの悲劇をもたらしている。徳川の時代では、江戸や京都で多く発生していたことが知られており、「江戸わずらい」あるいは京都では短期間で命を落とすことから「三日坊」と呼称されてもいたという。将軍家でも第三代の徳川家光を始め、第十三代の徳川家定、第十四代の徳川家茂が重症の脚気にかかり命を落としている。脚気の脅威は日本の歴史にさえその影響をもたらしているのである。
時代が変わって1800年代の日本はご存知の通り、日清戦争や日露戦争が起きていた頃であるが、戦死者よりもはるかに脚気による死者が多かったという。これは前回紹介した欧州における壊血病を思い起こさせるエピソードである。日本の軍人の多くが、何故だか足元をグラつかせて歩いていることを他国の兵士たちは奇妙に思っていたという話も伝え聞くが、恐らくそれは脚気によるものだろう。脚気とは一体、何者で原因は何なのか。本コラムの読者諸氏には医療に明るい人も多いので既に真犯人はご存知のことかもしれない。
脚気の症状としては初期に手足のしびれ、筋力低下、むくみなどがあり、やがて食欲不振、視力低下、歩行困難などの症状を経て心不全など心疾患も発生することから、当初は心臓疾患であろうと考えられていたようである。原因不明であった1800年代の後半には日本にも西洋医学の知見が持ち込まれ、イギリス医師による脚気死亡患者の解剖がなされ、心臓に異常がなかったことから心臓疾患説は否定されている。また、西洋の医師にしてみれば不思議でならなかったのは、西洋では脚気あるいはそれに近い症状を呈する患者がほとんどいなかったことである。その意味では風土病であり、かといって、ではどういった原因でこれが発生するのか、最先端の西洋医学をもってしてもなお当時はわからなかったのである。
食事説
原因不明の感染については、悪い空気がそれをもたらすと信じられてきたことについて、以前、疫学のはじまり、ロンドンで起きたコレラの大流行で紹介したところである。さすがに1800年代も後半となれば、瘴気(しょうき)説や「神がお怒りになっている」といった原因論は影を潜め、脚気の原因についてもウィルスあるいは菌がこれをもたらしているのだろうという説が有力視されることになる。
この脚気感染症説に異を唱えたのが、「疫学の父」ジョン・スノウならぬ、のちの世が「日本の疫学の父」とも称する海軍医、高木兼寛(たかき・かねひろ)である。高木の生涯を追った小説「白い航路」*を読み進めると、氏が脚気の食事説を支持するに至った思考回路まで追体験することが出来る。彼は25歳の時にロンドンにて医療に従事する傍らセント・トーマス病院医学校にてイギリス医学を以降5年間学んでいる。因みにここはナイチンゲールが看護師養成施設を開設した医学校である。その5年間では診ることのなかった脚気の患者が、帰国してみると日本の海軍病院では信じがたい人数であり大変驚いたという。
具体的に罹患者はどれくらいの人数であったか。全海軍で統計をとりはじめたのが1878年。その1878年においては4528人の海軍兵のうち1485名、実に3人に1人が脚気の罹患者で死亡例は32人。脚気を感染症説とした場合、若くて身体の丈夫な軍人で多くの死亡例が出ているというのは合理的に説明することが難しいところでもあろう。また、航海中に患者が多発しているものの、港に碇泊中に発症した人がいなかったという状況についても奇妙である。もちろん、船中に菌やウィルスが蔓延していたのであって、だからこそ船から降りていれば罹患しないということで感染説の説明がつかなくもない。しかしながら日本の海軍において幾度も繰り返される多くの発症が、イギリスでは皆無であることに感染症説ではどうにも合理的な説明がつかないのである。
かくして高木の確信は、当時の海軍の食事、つまり「白米+味噌汁+漬物」にあると行きつくことになる。海軍における船中での食事が理由であるとすれば、イギリスでは患者がいないことも説明がつく。また、「白いご飯が食べられる」という謳い文句で軍人をリクルートしていたこと、すなわち当時の一般の家庭ではゼイタクなため食べることの滅多にない精製された白米が真犯人であるならば、軍人でばかり脚気が多発することも説明がつく。また当時、総菜については“現物支給”ではなくお金が支給され、各人が好きなものを購入してよいとされていたのだが、貧しい時代にあってお金は家族への仕送りに回ることが多く、結果的には「おかず無し」の人も多かったという。高木は白米そのものではなく、このような栄養バランスの悪さに真犯人があるだろうと睨んだのである。
比較実験
高木の行ったことは自身の仮説が正しいのかどうか、現代でいうところの「仮説検証のための試験」である。白米ではなく麦飯やパンを主体としたんぱく質を増やし、栄養バランスを改善させた食事を一方で与え、もう一方は比較対照として従来通りの白米の食事をさせる。両群間において脚気の発生および脚気による死亡の割合を比較するというわけである。具体的にはこれを2隻の船で行っている。「龍驤」では白米の食事を、「筑波」では西洋の食事をさせ航海のルートや日数などは徹底的に同一のものとした。

その結果はこうだ。
戦艦 | 脚気発症(人) | 脚気による死亡(人) | 乗組員数(人) |
龍驤(白米主体) | 169 | 25 | 376 |
筑波(麦米主体) | 14 | 0 | 333 |
(出典:日本腹部救急医学会雑誌 Vol.28(7) 2008)*
結果として麦飯やパン、栄養バランスに配慮した食事を与えた「筑波」が圧倒的に優れていたのである。この結果を知った高木がどれだけ嬉しかったことか、というよりもどれだけ安堵したことか、といった方がよいだろう。何せこの実験については天皇に謁見して了解を得るということまでしている。実験の失敗は当時の価値観からしたら何を意味しただろうか、まさに命がけで行ったのである。かくしてこの画期的な“疫学研究”の結果を受け海軍では以降、大幅に食事の中身を変更したことによって、脚気という難敵を根絶させることに成功したのである。
少し補足しておかなければならないだろう。「白米」は、脚気の真犯人なのか、もしそうであるならば現代の私たちはもっと多くの人が脚気に罹患していないとおかしいことになる。それどころか、もはや世界中で食べられるようになったお寿司など、白米を食べる習慣は日本に限定されるものではない。これはどういったことなのか。
結論からいえばビタミンBの接種が不足すると脚気になりやすいというのがその答え合わせであり、白米そのものは真犯人ではない。むしろ当時のお話の中で注意すべきは「おかずをほとんどとらない」兵士が多かったことにあるだろう。高木による実験以降、「おかず」は現物支給となった。前回紹介した壊血病予防におけるフルーツの接種と同様に、食事が健康に密接に関わること、「栄養をとる」ことの重要さが認識されるようになるにはもう少し時代が進む必要があった。
脚気対策のその後
読者諸氏にあって高木の行った実験は、前回取り上げたところの壊血病に対する6種の治療との類似性を感じることだろう。比較対照をおく、というアプローチ以外にも双方に特徴的なのは具体的な対処策は見つかったものの、原因特定については明確でないという点にもある。
こうした主義や思想はイギリス医学とドイツ医学との違いにも関係しているのかもしれない。細菌学の研究が盛んであったドイツが瘴気や「神の思し召し」を超えた、現代医学においては常識的であるところの原因究明に注力していたのに対して、イギリスの実証主義は少しスタンスが異なる。すなわち、真なる原因がわからなくても、フルーツを接種する、麦飯を食べる、ということで実際に病気発症が減るならばそれが大事であり、まずは実行にうつすべきで原因究明を最優先しない。真犯人が特定できないというのはなんだかモヤモヤして気持ち悪い、というのはわからないでもないのだが、これがザ・疫学ともいえる。
高木はこの研究によって名を馳せたことから「麦飯男爵(むぎめしだんしゃく)」とも呼ばれる。また、西洋の食事をどうにか取り入れようと、日本人の口に合うよう工夫したのが「カレーライス」である。先の実験においても脚気を発症した人は全てが出された食事メニューが口に合わなかったため残した人であり、当時の日本人にパンや肉を食べさせるというのはなかなかハードルが高かったらしい。「海軍カレー」というブランドは今でも知られているが、本来的には麦飯や雑穀米にルーをかけて食べなければ海軍カレーではないだろう。
高木の研究から25年。脚気の予防に有効な成分、オリザニンを鈴木梅太郎が発見したのは1910年のことである。以降は白米を食べることは禁止ではなく、食事バランスとしてオリザニンを接種さえしていれば白米は食べても食べなくても脚気にはならないことが知られることとなった。ご存知の通り、オリザニンは後にビタミンB1と呼称を変え、鈴木は世界初のビタミン発見者となる。
本実験の評価
高木が行った研究は、現代において医薬品の承認申請に用いる無作為化臨床試験と共通するところも多い。まずは比較対照をおくこと、そして興味関心のあること以外はなるべく統一させることである。特に海外において高木の功績に対する絶賛の声は多く、高木の講演はランセットやイギリスの医学雑誌に詳細が紹介されている。また、アメリカにおいてはフィラデルフィア医科大学から名誉学位を、イギリスではダラム大学から名誉学位を受けている。
「高木兼寛の医学」*(松田誠)によると、この他にも数々の著名な科学者からの絶賛の声が多かったことがわかる。DNAポリメラーゼを発見しノーベル賞を受賞したコーンバーグは、「当時の脚気研究者のなかで、高木はその研究方法、実証方法の確かさにおいて群を抜いている」としている。また、「Evolution by Gene Duplication」の著者Susumu Ohnoは下記のように述べている。
“高木兼寛の脚気に関する疫学論文は,いま読んでも全く非のうちどころがない”
“かつて日本に独創的研究者がいたとすれば,それは脚気の栄養説をだした高木兼寛とモデル飛行機を飛ばした二宮忠八ぐらいであろう”
さらには1987年の日本医学会では重松逸造が下記のように証言している。
“高木兼寛の脚気の研究は,わが国における疫学研究の始まりである”
他方、高木の実験は脚気の根絶に貢献したことに加え、当時は理解が進んでいなかったところの栄養学の発展にも貢献することとなった。イギリスのビタミン学界の第一人者レスリ・ハリスは世界の八大ビタミン学者を写真入りで紹介したが、その際、高木を二番目に取り上げ、彼の偉大な功績を称えている。
このようにして栄養学にも貢献したことから、高木は「日本のビタミンの父」とも称される。色んな異名をもったものである。ビタミン研究者らは南極大陸に功績を残した偉人らの名前を借りた地名を付けるという不思議な慣習があるらしく、高木の名前は高木岬として今も残っている。
白米の健康リスク
さて、高木の偉大さは研究デザインそのものというよりも、これだけの研究を実現したその精神力や政治力にもある。文字通り命がけの研究だったのであり、その成果の価値も含め日本初というだけでなく、これを越える日本の疫学研究は以降にも無いといえるだろう。また、彼は慈恵医科大学の創設者でもある。今でも慈恵大の先生らには「けんかん(兼寛)先生」と呼ばれ愛されている様子が伺われる。
折しも只今は令和の米騒動と言われるところのコメ不足に多くの人が困っている。大臣は頑張っているものの、未だコメの価格は昨年の倍額以上で、仕方がないので白米を食べるのをあきらめてパンを食べているという人も多いらしい。脚気の予防についてだけ言えば、白米を食べていても他でビタミンB1を接種すればよいのだが、白米は糖尿病のリスクを上げることが多くの疫学研究で確認されており、実は「健康によくない食べ物」である。
私も高木の精神のわずかだけでも見習いたいとは思いつつ、およそ命がけで研究を実施する気概も機会もなさそうである。ならばコメが高騰してもいるので、コメほどには高騰していない雑穀米やオートミールに食事をシフトすることで“兼寛愛”を示すよい機会としようか。

そうはいうものの実家の新潟から定期的にコメは送られてくるし、 “白米愛”も“兼寛愛”に負けていない。疫学の仕事をしている身としては、「偉大なる高木兼寛先生の意思を継ぐ者です」など言ってみたいのだが、白米をパクパクと食べている口で言ったら叱られそうである。
「続・疫学と算盤(ソロバン)」第19回おわり。第20回につづく
*「白い航路(上・下)」吉村昭/講談社文庫(2009)
*日本腹部救急医学会雑誌28(7):873-881(2008)