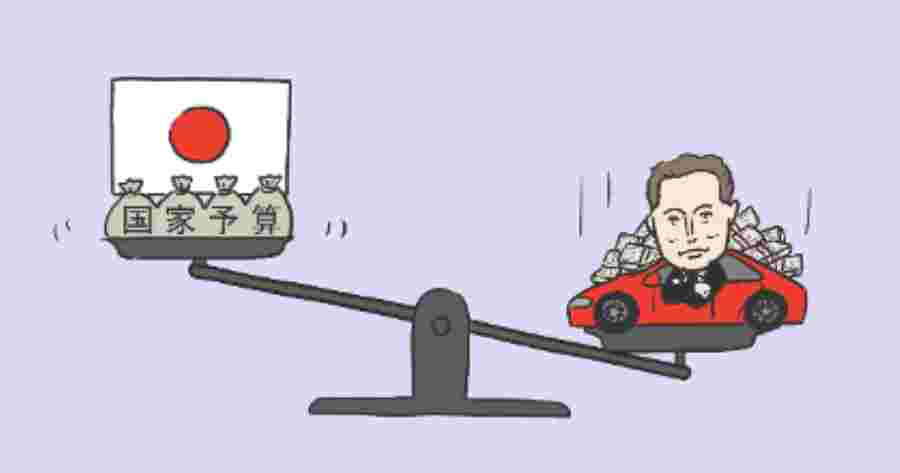第21回:生死をめぐる二元論
- 2025年9月10日
- 読了時間: 13分
更新日:2025年10月9日
2025年9月10日

2020年10月20日から連載開始した「疫学と算盤(そろばん)」は、昨年末、通算第36回を数え無事終了しました。36回分のコラムはご承知かと思いますが、当WEBサイトにてダウンロードできる電子書籍となっています。2024年1月からは、コラム続編の「続・疫学と算盤(ソロバン)」がスタートします。筆者・青木コトナリ氏のコラムとしては、日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボのWEBサイト連載の「医療DATA事始め」から数えて3代目となる新シリーズの開始です。装いを変え、しかし信条と信念はそのままに、“えきがくしゃ”青木コトナリ氏の新境地をお楽しみください。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ氏の
「続・疫学と算盤(ソロバン)」(新シリーズ) 第21回:生死をめぐる二元論
高瀬川
毎日のようにオーバーツーリズムに関わるニュースが報道されている。背後に富士山が見えるコンビニで写真を撮るために信号無視が後を絶たないだとか、私有地に勝手に入ってしまう人が多いだとか、地域の人にとっては困った話だろう。オーバーツーリズムとは「想定を超える観光客が集中し住民生活、景観、インフラなどに悪影響をおよぼす現象」のことである。言うなればそれだけ日本が他国の人にとって来てみたい、魅力のある国だから起きえる問題であり、いまや観光客なくして成り立たなくなったというビジネスをしている人も多い。
京都の街並みなどはもはや海外の人がたくさん歩いていることが当たり前になって久しく、もはやそうでなければ京都らしくない、といった風情、景観となったとも言える。人ごみを避けたいならば、大通りから細い路地に入るといいだろう。鴨川を横切る三条大橋は人だらけであるが、鴨川の横にある木屋町通りにある小川に架かるいくつもの橋はほんの数メートルと短く、人で渋滞するということもない。

この小川は高瀬川という。当時は今ほどには小さな川ではなかったろうが、その昔、罪を犯した罪人が島流しの刑に処されるとこの川を下ったとされる。その舟上で物語が展開される小説「高瀬舟」は、明治の文豪、森鴎外の作品として知られるところである。高瀬舟に登場する喜助が犯した罪は少し入り組んでいて「殺人罪」ではあるものの、重い病気のため働けなくなった弟が自殺を図った際に、そのほう助をしたという罪である。しかも薬を飲ませたといったような計画立ったものではなく、弟が自ら刺した刃物を、苦しむ弟の懇願にほだされてとっさに抜いたという、それが罪として問われたのである。
今回は鴎外が「高瀬舟」にてテーマとしてとりあげたところの「死」について取り上げてみたい。疫学分野でしばしばイベントだとかアウトカムだとする「死」を、自分事あるいは自分の身の回りのこととしてとらえるならば、研究で扱うときのそれとは違い、心穏やかではいられない。生と死の間には高瀬川ならぬ三途の川が横たわり、これを二分するという。今回は生と死の周辺を二元論の形でとらえることで死とは何か、その本質に迫ってみよう。
生物学と思想学
疫学研究では複数の治療を比較するうえで、治療の帰結として病気が治ったのか、それとも治らなかったのかという情報が極めて重要となる。その帰結、ゴールのことをよくアウトカムと呼称し、興味のある治療群間においてどちらの群がより多くアウトカムに至ったのか、あるいはより早くにアウトカムに至ったのかを比較するのである。
アウトカムには「治った」とは逆の悪い方のものも多く、「癌の増悪」や「容態の悪化」、「入院」、「集中治療の開始」なども利用され、言わばその“ラスボス”が「死亡」である。アウトカムに用いる指標や判定には“途中経過”、つまり容態が逆方向に戻るということもなくはないのだが、こと死亡に関しては不可逆であり、決して「生き返る」ことがない。
また、「癌の増悪」や「容態の悪化」などは、およそ文字づらそのものの意味合いしか持たないのに対して、死亡というのは病理学・生物学だけで語りきれない。人が亡くなる、ということにはしばしば何らかの「意味付け」がなされるのが常である。例えば宗教学的には「天に召された」と表現されたり、「神様のところへ行った」と表現されたりもする。また、極悪人の死に対しては、「天罰が下った」といったような「意味付け」がされる。これは生物学とは相容れないところの思想や宗教、死生学、あるいは社会学にかかる死のとらえ方である。
イベントと競合リスク
前述の通り死のとらえ方には生物学と思想学とに大きく大別されるが、医学や疫学における研究にあっての大別はまた様相が少し異なるものである。生物学的にみて死亡そのものは強靭なアウトカムではあるものの、研究目的によってそれはイベントが発生したという場合と、イベントの発生を観察していたのにそれが妨害されたという場合とに二分されるのである。
例えば肺がん治療の研究に参加していた被験者がある日、運悪く自動車にひかれて亡くなったとしよう。そうなれば、研究者が観察したかったイベントである「肺がんによる死亡」は、もう観察することが不可能となる。主たる観察を“妨害する”イベントのことを疫学分野では「競合リスク」と呼称する。研究者にとってイベントと競合リスクは水と油ほどにも違うのである。
ただし、イベント発生なのかそれとも競合リスクなのか微妙なケースも少なくはない。例えば同じ自動車事故であったとしても、自身が自動車を運転していて別の自動車と正面衝突によって亡くなったとしたらどうだろうか。このケースにあっても肺がんによる死亡というイベントの観察がさえぎられたことに違いはないのだが、もしそれが抗がん剤による副作用が強すぎて運転の途中で意識がもうろうとしていたせいであったする。イベント発生ではないものの、治療間を比較する研究にあっては、単なる観察の脱落とするよりもむしろ治療の失敗という悪いイベントが発生したともみなせることになろう。それ故に「肺がんによる死亡」というわけではないが、競合リスクとはせずに悪いイベントが発生したとして評価する方が妥当かもしれない。
他にも「肺がんが別の部位に転移しそれが主因での死亡」であるとか、「がんの増悪により将来を悲観し自死」などもまたイベントなのか、それとも競合リスクとするのか迷うところがあるだろう。そのため、メインの解析では「観察脱落」とし、念のために、ということで競合リスクも「イベント発生」とみなし解析してみるというアプローチがよくとられ、これを感度解析、感度分析などと呼称する。
メインの解析結果も感度解析の結果もどちらもA薬治療の方が優れている、といったように結果が変わらないならば、研究結果は説得力を増すだろう。反対に一方の定義ではA薬治療が優れるのに、他方、感度解析ではB薬治療の方が優れるということになると研究者としては混乱することになる。主たる解析の結果を強く訴えることはせず、その結果の解釈を少し控えめにした方がよいかもしれない。
「あの世」の存在と輪廻説
死を生物学と「意味付け」とに二分されると述べたが、後者「意味付け」も一つにまとまる概念とは言えないだろう。細かくいえば「意味付け」は多種多様であり多元論的ではあるのだが、大きくみてここでも二つにわかれそうだ。
まず一方の「意味付け」であるが、「あの世」の存在論である。宗教の中では私たちが生きているところの「この世」とは別の世界があるとする考えで語られることが多い。それを天国と言ったり地獄と言ったり、閻魔大王が出てきたり三途の川をわたったりする。
他方、「あの世」なるものは存在せず、死んだあとは別の個体として生まれ変わるのだ、とする宗教もある。仏教では輪廻転生と呼称し、死んだあとは別人格の人間として生まれ変わり、「あの子はあの人の生まれ変わりだ」などとしたり、あるいは他の生き物として生まれ変わったりすると考えられている。
ところで、無神論者はあの世の存在も輪廻転生も「非科学的だ」などとするかもしれない。その意味では、「意味付け」を二つにわけるうえでは有神論と無神論がまず先といえるかもしれない。ただし、無神論者が言うところの「神はいない」、あるいは「非科学だ」という有神論者への批判は科学に立脚した態度ではない。私たちは死んだことがないのだし、あの世が存在する、しないも、別の生き物に生まれ変わるかどうかも、科学的に証明できないならばどの意見も否定することが出来ない、というのが本来の科学的態度だろう。
加齢に関連する死と関係しない死
長寿国といわれる日本だけでなく、もはや先進国に分類される国々では寿命が80歳ほどに延伸して久しい。そうであっても生物学的には決して200歳まで生きたりはしないのであり、せいぜいが120歳くらいまで、とされる。それは私たちが生き続けることによって老化というシステムが働き、種々の臓器がもつ機能が劣化していくからである。
昨今では不老不死研究なども盛んであり、生き物の中には加齢や老化という概念と縁遠い存在もある。「亀は万年」というが、亀などはほとんど老化しない。不老不死研究で盛んに用いられるハダカデバネズミも老化しない。ベニクラゲは人間と同じように「成長」はするものの、成長したその先はポリプといわれる赤ちゃん状態に戻るのでその意味では不老不死の生き物である。しかしながら、現代科学をもってしても人間は加齢とともに老化し、100歳を超えて生きることはまだまだ「珍しいこと」なのである。

一方で先に述べた交通事故死や、震災・犯罪被害などは加齢や老化とは無関係に発生するものである。縄文時代の日本人は寿命が13歳~15歳であったといわれるが、その時代にあっては加齢も老化も概念としてすら存在していなかったことだろう。亀やクラゲのことはおいといて、人類に限っていうならば加齢・老化に関わる死と、関わらない死とは別モノなのであり、その対策なども大きく異なってくる。
ただし、感染症による死は例外的である。コロナの罹患は今でも成人一般よりも高齢者にとって命の危険に関わる一大事である。一方で感染症の罹患は、高齢者とは別に赤ちゃんや幼少期もまた成人と比してリスクである。年齢とは無関係ではないものの、加齢が常に死亡リスクを高めるともいえず、若年では負の相関もしている。
感染症を例外として考えると、私たちが「寿命」などとされる類のものは加齢や老化といった時間との関係で語られるところの死であり、一方で時間とは関係しない死の方は「寿命」という概念からは語られようのないものとして捉えられるものである。前者の死はときに“大往生”などとして捉えられ必ずしも悲劇を伴わないのに対して、後者は寿命の途上の死としてとらえられ、ときに深い悲しみを周囲にもたらす。
自分の死と他の人の死
他人事と自分事。これは随分と違うものだろう。死んだことのある人などこの世には存在しないのであって、その意味では自分と他人という区分けではなく、むしろ現実と非現実・想像の世界とに二分する方がしっくりくるかもしれない。また、他人の死であっても、ごく身近な人の死と、そうでない、メディアから流れてくるところの見知らぬ誰かの死もまた社会学や心理学分野では別のこととして整理されるだろう。その意味では自分の死、自分の周囲の死、その他の人の死と三元論的でもある。
公衆衛生学分野で近いところにはグリーフケアという学問領域がある。狭義では自身のごく身近におきた人の死に対する悲しみを癒す、その方法論などを研究するものであり、医学一般のように「人の死を防ぐ、人の生を延ばす」ことは目的としていない。目標とするのは「喪失」にどうかかわるかであって、これは自分の死ではなく他者の死に関する学術分野なのである。
個体の死と細胞の死
生物学的な死というのもまた案外と一元論的ではない。臓器として例えば心臓が止まった、それすなわちが死であるというものではなく、医師が死亡診断する際には心拍停止に加え呼吸の停止、瞳孔反応の消失の3つが揃わなければならない。
その意味では生と死は頑健な、三途の川を挟んだクリアな線引きが出来そうで出来ないともいえるだろう。「脳死は死なのか」といったテーマはおよそ哲学分野の話のようであったが、臓器移植などの医療技術が進む中にあっては物理的に、有り体にいえば人類の“ご都合主義”的に「死んではいない」とされたり「死んでいる」とされたりする。
実際のところ、先に述べた死亡診断の3つの条件が揃ったとしても、身体の中の一部、細胞が全てそのタイミングで死んではいないのであり、であるが故に人が植物状態となり、もう意思疎通が出来ないとなった場合のそれを「死亡した」とするのかどうか、といった話は自然科学ではなく社会科学や倫理学分野でのテーマとなる。
望まない死と自ら選ぶ死
一般論としていえば、自ら命を絶つという「自殺」ほどに悲しい死も他にないだろう。周囲は「何かしてあげられなかったのか」と自分を責める。また、もとよりその自殺を促進したところのいじめや経済的困難、社会的糾弾、精神的な切迫などは公衆衛生学の実践として解決すべき重要なテーマでもある。
「高瀬舟」が発表されたその当時にはどのように呼称されていたのかはわからないが、小説の中で描かれたのは現代でいうところの「安楽死」がテーマである。目の前に“死ぬより辛い状態”を訴える人がいて、それをほう助して欲しいと懇願されたときに人はその願いをかなえてあげる行動をするのが正義なのか、それともかなえてあげないのが正義なのか。両親を失い、残された唯一の家族であるところの弟が、死にきれずに苦しんで苦しんで懇願しているのを目の当たりにした喜助が行った“殺人”は、読者にとって疑いもなく「正しい行為」に見えるよう著者は工夫を凝らしている。
安楽死問題は現代日本にあっても継続課題といってよいだろう。世界で初めて安楽死を法制化したのはオランダであり、以降はベルギーやルクセンブルクなどでも合法化されている。当該の目的にてスイスを訪れることを「自殺ツーリズム」と呼称したりもする。こうした国々をもってして軽々しく「先駆的な国」であるとか「残念な国」であるとかするのは適切ではないだろう。社会倫理の問題は「こちらが正解となります」とは一概にいえないのが常である。大抵の死は自身が望むものではない一方で、安楽死問題を考えるならば自死なるものが一律に悪いことなのかどうか、「尊厳死」として肯定的にみる向きもあることにも留意すべきである。
本業と副業
ものごとをわかりやすくとらえるうえで、文筆家、あるいは優れたプレゼンターは、例え話をしたり、反対のことを併記することで比較論にて説明したりする。今回の本コラムでの試みは後者を目指したものであるのだが、死というテーマがデリケートであるが故に、「死を軽々しく語るな」とか「死を面白おかしく言うな」といったお叱りを受けるやもしれない。疫学分野には色んなアウトカム定義があるのだが、こと「死」なるアウトカムだけはスピリチュアリティに関わることであり、慎重に言葉を選ばなければ思いがけず人を不愉快にさせてしまいかねないことから積極的には取り上げたくない題材であったというのが本音である。
かといってタブー視ばかりしているのも公衆衛生学の実践としては正しいことではないようにも思えたのである。生と死とは生き物にとって最重要な関心事なのであり、これをタブー視するのではなくむしろ直視するところから、よりよい社会が形成できるのではないだろうか。そんな風に死をテーマとしてとりあげるべきだろうと、私の背中を押したのは他ならぬ鴎外である。彼は安楽死という問題を小説「高瀬舟」の中で罪人である喜助と、船頭である庄兵衛との掛け合いという形でわかりやすく日本に紹介したのである。これは「たとえ話」の手法とも言えるだろうが、あまりに巧みなため身勝手な押し付けや説教臭さはみじんもなく、読者はシンプルに物語として面白く読み進めることになる。

鴎外は医師であるという側面と小説家という側面とがあり、これはまるで今回の構成である二元論を地でいくようでもある。私自身も製薬企業社員という側面と、副業としてこうした執筆業や講演業を営んでいるという側面とがあり、これを鴎外のそれと比べることがおこがましいと思いつつ、二足の草鞋(わらじ)ということでどこか共感してしまう。
前回は鴎外を“酷評”し、今回は鴎外を“師範”として取り上げた。これもまた二元論であり、人の評価は一面的にするものではないという思いも今回の隠れテーマではある。安楽死という難しい問題を大衆文学という形でわかりやすく社会に伝えるというそのセンスと才能。文筆家、社会へのメッセンジャーとしての鴎外に、私も憧れるのである。
「続・疫学と算盤(ソロバン)」第21回おわり。第22回につづく