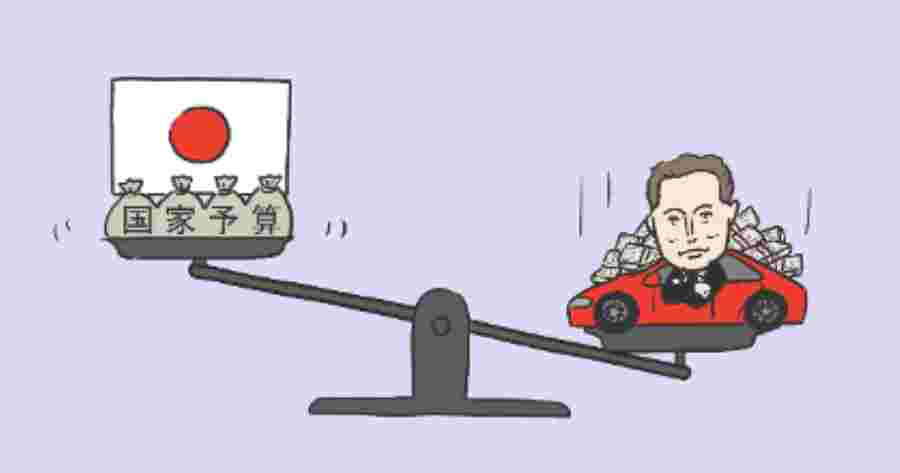第24回:医療の行きつく先
- 2025年12月8日
- 読了時間: 12分
更新日:1月19日
2025年12月08日

2020年10月20日から連載開始した「疫学と算盤(そろばん)」は、昨年末、通算第36回を数え無事終了しました。36回分のコラムはご承知かと思いますが、当WEBサイトにてダウンロードできる電子書籍となっています。2024年1月からは、コラム続編の「続・疫学と算盤(ソロバン)」がスタートします。筆者・青木コトナリ氏のコラムとしては、日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボのWEBサイト連載の「医療DATA事始め」から数えて3代目となる新シリーズの開始です。装いを変え、しかし信条と信念はそのままに、“えきがくしゃ”青木コトナリ氏の新境地をお楽しみください。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ氏の
「続・疫学と算盤(ソロバン)」(新シリーズ) 第24回:医療の行きつく先
長州力
「ちょうしゅう、、、りき?」
先日、熊本で発生した震度5強の地震が発生した際、それが長周期地震動1である旨が報道された。長周期地震動というのは、どうやらゆっくりとした振動のことなのだそうだが私にとっては初耳であった。

この頃は随分と耳が遠くなったように思う。まだ補聴器はいらないだろうと自分に言い聞かせてはいるのだが、ちゃんと聞き取れないということもしばしばである。長周期地震動(ちょうしゅうきじしんどう)は初耳であっても、元プロレスラーの長州力(ちょうしゅうりき)さんなら耳に馴染みがあり、冒頭のような、アナウンサーが「長州力」と発声したものと聞き間違えるのはよくある私の日常の一コマである。
とはいえ耳の難聴というのは、前回取り上げたところの認知症のリスク因子として堂々の(?)1位に輝いている。周囲の音を正しく聞き取れずに暮らし続けるということは、認知症になる可能性を高めてしまうということであって、もう観念して補聴器のお世話になった方がよいのかもしれない。
さて、前回は疫学的な視点から未来社会について空想したところであるが、今回はそのスピンアウトとして、医療の視点、医療の未来やそれがもたらす世界について想像を膨らませてみたい。とうに“夢見るスキル”が劣化した私が描くそれは、やはり難しい課題をあぶり出すだけだろうという批判の声もありそうなのではあるが、耳が遠いことを言い訳にそういった声は聞こえてこなかったことにしてとりあえず進めてみよう。
機能の補完
私の“機能劣化”はもちろん耳だけではなく目もそうである。近視となったのは中学生の頃であって、近頃はそれに加えて近いところが見えにくくなるという老眼が追加されたという、二重苦である。遠くも見えなければ近くもまた見えない。私と同じ悩みを抱えている人も多いことだろう。
現代ではメガネ、という便利機能が当たり前に存在しているので昔の近視の人の苦労については想像もしにくいのだが、日常にあっても戦場にあっても不便であり不利であったであろうことは想像に難くない。今年の大河ドラマは、江戸中期の商家、蔦谷重三郎が主人公であるが、その妻“おていさん”のメガネは印象的な黒くて太いフレームである。今のように決してファッショナブルでもないそれを付けることは、抵抗感や劣等感も一緒に身にまとっていたに違いない。
メガネは医療機器でないため医療分野の外ということになるのだが、私のようにコンタクトレンズやメガネが欠かせないという人は、こうした“身体機器補完ツール”がなければ外を出歩くことさえ困難である。それにしても難聴を疾患とし近視・遠視・乱視の方は疾患ではないとするのは、一体どういったロジックなのだろう。メガネはオシャレで補聴器はオシャレではないからだろうか。何だか釈然としない。一つだけ確実にいえることは社会問題でもある医療費のひっ迫との関係であり、メガネ・コンタクトレンズまで医療機器としてしまうと医療費に6000億円が上乗せされてしまう。ここにオトナの事情がありそうだ。
さて、医療機器としての認可がされるかどうかはともかく、こうした装着型の機器がこれから益々、人類に恩恵をもたらしてくれそうな予感はある。装着型サイボーグHAL(ハル、Hybrid Assistive Limb)は、脳・神経・筋肉の機能低下によって身体を動かせなくなった人の改善治療を行う。分身ロボットカフェDAWN ver.βで働く分身ロボット「オリヒメ」を操縦するのは主に身体を動かせない病気の人達だ。義足や義手の技術革新も凄まじい。こうした技術の進歩がその当人や家族に対してどれだけの福音をもたらしているのかは計り知れないだろう。利用者にとってこうした技術の開発者は大げさではなく神様と言えるのかもしれない。
ちなみに、義足による100メートルの走行記録は世界記録に迫っており、走り幅跳びの方では、既にオリンピックの金メダル記録を抜いている。ここまでくると義足や義手を使ったスポーツ等の記録の取り扱いに悩みが生じたりもするのである。例えば、もしも義手で時速200kmのボールを投げられる野球の投手が出てきたら、これはもう打てる打者も居そうにない。果たしてそのような未来があるのかはわからないが、現代にあっても故障した投手の肘に金属製のボルトを入れることは珍しくない。もしもこうした施術の進歩の先として手術する前よりも明らかに早いボールを投げることが出来るとなったらどうだろう。ケガもしていないのにそれと偽って肘に強化ボルトを入れる選手も出てくるとしたら、これはドーピングよりタチが悪い気がする。
施術の進歩
投手の肘の手術に限らず、手術のスキル向上は日進月歩といえよう。中でも手術ロボットを使った治療技術の進歩は大いに期待されるところである。手術ロボットを人間の医師が遠隔操作できるのであれば、医療機関のない地域での医療格差の問題もかなり改善されることだろう。また、人間では到底不可能なミクロの単位での手術も実現するかもしれないし、何れは医師が操作しなくてもロボットのボタンを押しただけで簡単な手術くらいは完璧にこなせるようになるかもしれない。
さらには、従来ではその治療方法の無かったものが手術として実現できるようになろうという期待も高まる。例えば視力回復のためのレーシック等の技術が日本で広まったのは2000年代であり、ならば私の聴力回復もそのうち完治させる技術が広まるかもしれない。臓器移植術の進歩については施術そのものの進歩のみならず、他者の臓器を身体に入れることによって生ずる拒絶反応に対してそれを防止する医薬品の進歩による貢献も大きい。
加えて、以前、本コラムでも取り上げた直美(ちょくび)問題は、医師の“就職先”として美容整形分野が人気になっているという背景があるのであり、既に美容整形市場は6000億円ほどである。今後さらに拡大が予想されており、早晩に1兆円市場になるらしい。美容整形技術の元を辿れば、戦傷や外傷治療として負傷兵のための”医療行為“に属するものだったようではあるが、只今の美への追及はさすがに医療とは言い難い。その一方で、手術を行う人は医師でなければならないという少し不思議な世界であり、こちらの進歩も目覚ましい。
気になるところは、美容整形は今や戦傷や外傷治療から程遠いところの、従来の状態が損なわれたためそれを是正するために行うという行為ではないというところである。美容整形によって容姿端麗を武器とし獲得した社会的地位には何だかモヤモヤ感がないだろうか。美男美女ばかりの社会は、ヒト個々人では美しくあっても社会としてはどうなのだろう。むしろ多様な容姿の人が暮らす今の社会の方が、社会全体としては美しくはないだろうか。

ゲノム医療
その昔はこれまたSFのようであったゲノム、遺伝子の解析によってもたらされた医療技術の革新もまた凄まじい。今や癌の治療分野にあっては、まず「がん遺伝子パネル検査」が実施され、患者それぞれの腫瘍遺伝子に合わせた治療が選択される。例えば乳がんであれば、それがBRCA変異であればPARP阻害薬(オラパリブなど)、PIK3CA変異ならPI3K阻害薬(アルペリシブ)、HER2遺伝子増幅なら抗HER2療法(トラスツズマブ、ペルツズマブなど)といった具合である。
血液がん領域におけるCAR-T細胞療法が出てきたときは、その治療法の斬新さに驚かされたものである。患者自身の免役細胞であるT細胞を一旦取り出して、それをカスタマイズ(遺伝子改変)し体内に戻す。ゲノム医療の進歩によって急性リンパ性白血病や悪性リンパ腫の他、治療法の無かった脊髄性筋委縮症(SMA)や遺伝性網膜疾患などに対する治療薬が新たに承認されており、不治の病と目されていた病気が完治できる可能性を大いに抱かせてくれる。iPS細胞技術等の進歩の先には、臓器不全の対処策として他者の臓器ではなく、自身の細胞由来で作り出された臓器を移植する世界が待っているかもしれない。そうなれば免疫反応による機能不全といった懸念も払しょくされよう。これが心臓や脳にまで広がると、「永遠の命」がSFから現実に近づく。
一方で、その先にある未来に影を落とすのがゲノム編集である。先天性の疾患を治療するということであれば誰しも歓迎するのだろうが、疾患でもないのにゲノム編集によって知性や運動能力を増強するということを未来社会は受け入れるのだろうか。ドーピングが許されない世界にあって、自己中心的なゲノム編集が許されるとしたらおかしな話だろう。
実際のところ既に出生前診断は一般的になりつつあるが、それによっての出産判断は哲学的な課題に影を落とす。哲学者マイケル・サンデルが「出生前診断は許されるのか」をテレビ討論のテーマとして取り上げたことがある。命の選別は直感的にも哲学的な問題を感じるが、その命を維持するためにゲノム編集を行うことは正しい、と言い切れるのだろうか。ゲノム編集の結果、圧倒的に「頭が良すぎる」「足の速すぎる」ヒトがもし生まれてくるということが技術的に可能となった場合には、その行為を人類は「正しい」とするだろうか。それとも技術的には可能なのに「ヒトの標準的な能力を超えてはならない」といった規制を作るのが「正しい」のだろうか。
優生学の悲劇
ゲノム編集の悩みはその昔の人類の汚点、黒歴史であるところの優生学とも関連が深い。優生学とは進化論と遺伝学とを人間にあてはめ、集団の遺伝的な質を向上させることを目的とした一連の信念と実践である。こうした説明を聞いただけでは何だか良さげな響きもあるのだが、端的にいえば優れたヒトだけが暮らす世の中を目指すといった、とんでもない思想である。もちろん、今は優生学は完全に否定されており、そもそも「優れる」という価値観自体が普遍的なものではないとされる。戦国時代では戦(いくさ)上手な猛者が「優れる」人材であったろうが、戦国時代が過ぎた後にあっての「優れる」人材とは、むしろ政(まつりごと)上手な人材と、そんな風にして時代によって変化するのが常である。
ただ、現代の感覚では“トンデモ”論である優生学は、実際のところ19世紀末から20世紀の半ばまでの数百年の間、先進国の中でも受け入れられていたものである。数年のブームではなく、数百年。当時の人たちにとっては空気のような、当たり前の価値観だったというわけである。優れたヒトばかりになる世界を思い描いたその先には、ユートピアではない、まさにディストピアが待っていた。能力の劣るものが否定され、能力に優れるものが歓迎される。差別が増長され一部の人には出産が禁止される。ドイツでは優生学から派生した民族浄化思想によって、障害者の安楽死計画や同性愛者の迫害、そしてユダヤ人の大量虐殺という悲劇を生んだのである。
こうした黒歴史から察するに、仮にゲノム編集が容易になった世界では、偏差値が50未満の人を「知能劣化症」としたり、足の遅い人を「遅足症」としたりする恐れが生じる。この数十年で病気として定義された自閉スペクトラム症(ASD)、双極性障害、多動症(ADHD)などは、治療法の進歩という明るい面の裏側に、人をそのようなレッテルを貼るという差別的な要素をはらんでしまうである。大いに福音をもたらすゲノム医療を肯定し、他方でゲノム編集を否定するというのは無理筋であって、その技術や思想はクリアカットに出来ない地つなぎといえよう。只今は差別禁止法制定の議論や具現化が先進国の中で進んでいる。
おこがましいとは思わんかね
医療用ロボットやiPS細胞による臓器の複製にゲノム医療。未来はどうやら私たちの寿命も健康寿命もさらに延ばしてくれそうである。今回は取り上げなかったが、癒し系の介護ロボットも実用化されて久しく、そこに見守り機能や健康増進のリコメンド機能などが加わるであろうことも想像に難くない。
その一方で、何が病気で何が病気でないのかの区別は、近視や老眼が病気でなく難聴が病気とされている通り曖昧なものである。然るに、医療が進歩され様々なヒトの願望が実現できるようになると、新たな「病人」として勝手に知能劣等症、運動劣等症、容姿劣等症などとされかねない。恐ろしい。病気として定義されることで差別は助長され、優生学という黒歴史が復活してしまう恐れもはらむ。今回のコラムにおける展望は悲観的すぎだろうか。
ふと思い出されたのが漫画界の巨匠、手塚治虫さんの名言「人間が生きものの生き死にを自由にしようなんておこがましいとはおもわんかね?」である。医療漫画の金字塔「ブラック・ジャック」では完璧な手術であったにも関わらず、主人公ブラック・ジャックの師匠であり命の恩人でもある本間丈太郎医師の命を救えなかったところでこのセリフが登場する。手塚漫画ではしばしば本間医師のように鼻の大きなキャラクターが登場するが、手塚先生ご本人がモデルとされる。この言葉に励まされたという医療者の声もよく聞くところであるのだが、これは本当に「励ましの言葉」として受けとっていいのだろうか。
ひょっとすると私たちは生成AIの進歩がそうであるように、ロボット工学もゲノム編集もその行きつく先として「おこがましい」ことの代償を支払わなければならないのかもしれない。私は科学の“信奉者”なのだが、その科学の進歩によって原子力爆弾が現実のものとなり、ダーウィンの進化論を優生学が“仲介”してホロコーストが引き起こされたことをどのように受け止めたら良いのだろうか。その答えがわからない。
そのようにして考えてくると科学の進歩が、医療の進歩が「おこがましい」とすら思えてくる。あるいは進歩ではなく、医療そのもの、そして医薬品や医療機器は存在そのものが「おこがましい」ということはないのだろうか。医療というものが、薬というものが、生き物の生き死にを自由にしよう、という“越権行為”ということはないのだろうか。果たして手塚さんは、どの行為や行動のことを指して「おこがましい」としたのだろうか。

かくいう私は医療の進歩によってここまで生きながらえているのであり、医療がなかったらとうにこの世には存在していない。医療の進歩なくしてはとうに死んでいた私が医療の存在を疑うということが何より自己矛盾的であり、おこがましい。そんな気もする。
「続・疫学と算盤(ソロバン)」第24回おわり。第25回につづく