第20回:健康の測量
- Erwin Brunio
- 2022年4月25日
- 読了時間: 11分
更新日:2022年7月26日
2022年4月22日
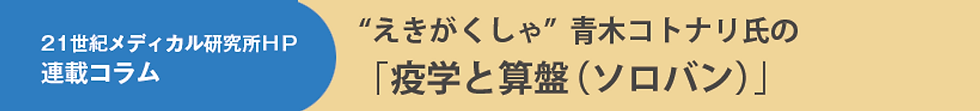
2020年10月20日から、3週間に1回、大手製薬企業勤務で“えきがくしゃ”の青木コトナリ氏による連載コラム「疫学と算盤(ソロバン)」がスタートしました。
日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボWEBサイトに連載し好評を博した連載コラム「医療DATAコト始め」の続編です。「疫学と算盤」、言い換えれば、「疫学」と「経済」または「医療経済」との間にどのような相関があるのか、「疫学」は「経済」や「暮らし」にどのような影響を与えうるのか。疫学は果たして役に立っているのか。“えきがくしゃ”青木コトナリ氏のユニークな視点から展開される新コラムです。
(21世紀メディカル)研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第20回:健康の測量
回転寿司
医療経済学の“イ”として紹介した効用(Utility)は経済用語で取っつきにくい言葉であるが、「幸せ度」と言い換えれば少しは親近感も湧くだろうか。
我が家にとって回転寿司は一つの「効用」である。月に1度か2度は決まって寿司屋にお邪魔するのであるが、寿司屋といえば回転寿司であり、そうでない寿司屋に行くことは滅多に無い。回転寿司屋では寿司に限らずラーメンやスイーツまで好きな物を自由に選べ、何より「寿司が回転している」というエンターテイメント性が楽しい。子供がまだ幼い頃は「回転を繰り返すことで寿司がおいしくなるのだよ」などと口から出まかせの教育(?)もしていた(ひどい親だ)。店にもよるが、ガチャガチャも出来る。あくまで我が家限定の話ではあるが高級寿司店に行くよりも「効用」、つまり「幸せ度」が高いのである。

仮にもしこの先、回転寿司屋に行ってはならない50年の人生を送るとした場合、私にとっては回転寿司屋に行くことが禁じられていない、要するに今まで通りの人生をこの先49年、生きるとしたらどちらの人生の方がよいかどうか、つまり1年の寿命の長短を少し迷うほどの「効用」がある。
測れないもの
さて、「測れないものって、例えばどんなもの?」
子供にもしこんな質問をされたら皆さんはどうお答えになるだろうか。
医療の世界でも痛みやうつ症状などは、科学の進歩した現在でもその分量を測定するのは難しいが、世の中一般的にいえば、その答えは「愛」だったり「幸せ」だったりではないだろうか。今回はこの測れないものへのチャレンジの話である。「愛」の分量を測定するアプローチは心理学分野では盛んに行われており、ただ「愛」そのものを測量するのはやはり不可能であって、対象との接触回数や会話時間など、「恋愛」「親の愛情」といった「愛」の形態にあわせた代替指標で研究を行うのが常である。
同様に、「幸せ度」をどうにか測量しようと考えると、こちらもまた「愛」に負けず劣らず難題である。「私は世界一、幸せです」なんていう台詞を聞くと「そんなのわかるものか」なんてうそぶく一方で、「では何番目でしょうか?」と聞き返されても、うろたえるだけだ。何より愛も幸せも主観的な判断であり、であるが故に客観的なモノサシを準備しようにもうまくいきそうにない。自分は果たして会社で、東京都で、地球上で、何番目に幸せなのか、調べたくてもどうやったら調べたらいいのか、皆目見当がつかないのである。
効用の正体
前回のコラムで紹介した医療経済のイロハの“イ”、費用最小化分析や費用効果分析については、シンプルに「効き目のコスパを調べる」ものではあるが、医療経済学の親分である経済学が何より経世済民、世の中をよくする、皆を幸せにするための学問領域であって、「幸せを測る」チャレンジを避けては通れないのはこのためだろう。その代表が費用効用分析であって、この「効用(Utility)」なる用語がいかにも経済学なのであるが、冒頭で紹介した通りこれは「幸せ度」と言い換えができそうである。
もう少し正確性を追求して「効用」を辞書で引いてみると「使いみち」とある。「幸せ度」とはかなり違う。そこで今度はウィキペディア*で調べてみると、まずは経済学の用語であるという前置きのうえで、「消費者が財やサービスを消費することによって得ることが出来る主観的な満足度」とある。「幸せ度」と「満足度」の違いを明確に説明するのは難しそうで、故にニュアンスの近い概念であるともいえよう。
さらに原語であるUtilityに立ち返ってニュアンスを考えてみよう。読者諸氏がサッカーや野球に詳しいならばユーティリティ・プレイヤーという概念をご存じのはずで、これは複数のポジションを守れる器用な選手のことを指す。一方、ゴルフファンにとってのユーティリティというクラブは3番とか5番とか、一般の飛距離を想定した数字の指標がないフワッとしたポジションにあるものだ。効用(Utility)という言葉の意味合いは幅広いのである。
費用効用分析という、科学的な分析法にとってこれは実に都合の悪い話である。そこで昨今では効用=QOL(質調整生存年)が医療経済学分野でのスタンダードになったというわけだ。ただ、このQOLですら科学という“固い頭”の権威にとっては都合が悪い。前回も触れたように、女優さんにとっての脱毛やピアニストにとっての手のしびれといった副作用によるQOLの劣化が私たちと同一であるはずがないからだ。主観を客観で判定しようなどというのはそもそもおこがましい。医療経済学が幸せのための学問である経済学の一分野でなかったなら、きっと費用効果分析は行っても費用効用分析には手を出さなかったことだろう。

こうしたことから現在、医療経済学分野でQOLといえば、そのほとんどの場合において健康関連QOL(Health-related Quality of Life、HRQOL)に限定している。主観的な幸福感まで測るのではなく、あくまで健康に関することだけを効用の代用にしてしまえば、どうにか客観的な指標に持ち込むことが出来そうではある。
このように本来、効用とはより広い概念であるが、その妥協案としてのQOL、さらに妥協して健康関連QOLとしていることは踏まえておいた方がいいだろう。何故ならば複数の治療のどちらがよいかを比較する上で、健康関連QOLが優れる方が、実は真なる効用(幸せ度や満足度)において優れていると断定しきれないことが起こりえるからだ。
健康の正体
もう少し概念的整理のお話に付き合って頂きたい。健康関連に焦点を絞れば客観的な測定が出来ると果たして断定出来るのだろうか。「健康」を効用としたとき、本当に幸せ度や満足度に含まれている多義性、曖昧さを完全に除外しているかといえば実はそうでもない。
WHO(World Health Organization、世界保健機関)では健康について以下のように定義化している。
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
(健康とは、肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。)
これは私たちが日常使いしている「健康」という言葉とは少し違うだろう。「健康に気をつけています」という言葉の中には、仮に精神性のニュアンスが若干含まれることがあったとしても社会性のニュアンスを含んで話をしているとはちょっと考えにくい。
さて、この定義をそのまま直視してしまうと折角、「効用→幸せ→健康」と、一旦は客観的に調べられそうになったものが「健康→幸せ→効用(社会的に良好、という意味も含意)」という難題に逆戻りしかねない。難儀な話である。
健康関連QOLの直接測定
開き直って健康関連QOLを一体どうやって客観的に測定できるのか、話を進めていこう。方法論として有名なのがスタンダードギャンブル法(標準的賭け法、SG法)である。
ギャンブルや賭け事、という言葉や概念は日本ではネガティブな、違法まがいの印象もあるが、考えてみれば私たちの人生はいわゆる遊興としてのギャンブルと比べて桁違いの賭け事をしていると言えないだろうか。就職先の決定、結婚や離婚の決断、数千万円の借金をしての不動産の購入など、それが確実に「当たりクジ」を引くとはわからずともギャンブル的な意思決定をして生きている。SG法はこの延長戦上にあるアプローチとも言えるだろう。
例えばあなたが不幸にも大事故にあって、このままでは両眼の視力を完全に失ってしまうとしよう。これを避け、両眼の視力を完全に元通りに戻せる手術があるにはあるのだが、その成功確率は70%でしかなく、手術の失敗は死を意味する。想像しただけでなんだか嫌な気持ちになるたとえ話で申し訳ないのであるが、これがSG法のベースとなる考え方である。
この70%を例えば90%としたり50%としたり、あるいは両眼を片眼にしたりすることで、「完全なる生存」と比べてどの程度なのか、「手術をする」という選択肢、ギャンブルを選ぶのか、選ばないのか。こうすることで、あなたにとっての「片眼失明での1年」「両眼失明での1年」がQOL、質を調整した生存年としては例えば0.9年であるとか0.5年であるとかを算出することができるわけだ。
また、健康関連QOLを直接測る方法として時間得失法というものもある。これは、冒頭の回転寿司のお話で消化した「回転寿司屋に行ける49年と、2度と行くことができない50年が同値」のように、失う人生の時間との天秤にかけてその効用を測るやり方である。回転寿司とは言わずとも、皆さんにとって仮に豚骨ラーメンやアイスクリームが食べられない、ゴルフができない、きれいな洋服では外に出られないといった縛りのある50年の人生よりも縛りのない49年の方がトータルとしてQOLが高い、という効用は何かしらあるだろう。
主流となったEQ-5D法
このような直接的にQOLを測る方法はどうにも手間が掛かってしまうのが頂けないところである。QOLの改善を調べたい調査では定期的に測りたくもあり、1回辺りの回答に何十分も掛かってしまっては被験者の負担が大きい。負担の大きさが何をもたらすかといえば皆さんももしかしたらご経験があるかと思うが、私のようなサボりクセのある人はテキトーな回答をしはじめる。簡単にいえば「大/中/小」や「強/中/弱」、「はい/まあまあ/いいえ」のような選択肢があったときに中間の「中」や「まあまあ」のような類の選択肢をよく考えもせずに連発してしまいがちになる。詳しく調べたいからたくさん質問したいのに、結果として何もちゃんと調べられない恐れが増大し、これでは本末転倒である。

只今、国内において主流のQOL手法といえばEQ-5D-3Lという、QOL直接的ではないものの、記入者の負担を最小限に留めることに長けた間接的な測定方法である。色々と聞きたいことがあってもグッと我慢してシンプルに5つしか質問はしない。具体的には以下の5項目である。
(1) 移動の程度
(2) 身の回りの管理
(3) 普段の活動
(4) 痛み・不快感
(5) 不安
3Lとあるのは3つのレベル、「問題なし/いくらか問題あり/出来ない」が選択肢となる。EQ-5D-5Lという測定法もあって、こちらは「問題なし/少し問題あり/中程度の問題あり/かなり問題あり/出来ない」の5レベルの選択肢であるところがEQ-5D-3Lと違う。
EQ-5Dとはその質問書式を開発したEuroQolグループによる5つの寸法(Dimension)という意味のネーミングである。「たかだか質問項目を5つ勝手に決めただけでしょ」というなかれ、QOLのフォーマットを決定するにはその質問項目の妥当性や時系列で追ったときに実際に変化を観察できるかどうか、文化による違いはどうかといったように妥当性検証には様々な試行が必要なものでシロウトが気軽に作ったものとはわけが違うのである。
ゆえにEQ-5Dを使った研究を行う場合には、このEuroQolグループの了解*が必須となる。なお、研究利用の場合、費用は無料である。
他にもこうした簡便型の健康関連QOLを間接的に測定する方法としてはHUI(Health Utililties Index)、SF-6D(Short Form Six Dimension)などが知られている。書式もさることながら、調査票を被験者に提供するところも注意が必要となる。医師や看護師が「これに記入してください」とお願いしてしまうと、自分のために一生懸命、治療や対応をしてくれている人の前では実際よりも健康であるかのような記入になる恐れがある。思いやりが科学の邪魔をする。遠慮なく本音を引き出す研究というのは意外とコツが必要なのである。
回転しない回転寿司
先日、会社の同僚と話したところ、「生まれて初めて回転寿司屋に行きました」とのことであった。てっきり1皿1貫がデフォルトだと勘違いして家族3人分3皿頼んだら9貫もきてしまって困ったとか。なんだかその「回転寿司知らず」という逸話がセレブリティでかっこいい。対して私の方はどうかといえば、どのようにすればお茶が飲めるか、ガリや醤油はそれぞれのチェーン店でどう違うのか、1皿3貫のネタにはどのようなものがあるのか等々、なんでも知っていて、もはやわからないことを見つける方が難しい。最近では“回転しない回転寿司”も増えてきており、これは注文すると高速レーンに乗ったお寿司が自分の席に届くという仕組み、いわば「レーン寿司」が増えてきていることも知っている。
なんだかその詳しさが恥ずかしい。よく考えてみると、本当に回転寿司、レーン寿司が高級寿司よりも「効用」が高いということを家族に確認したことは一度もない気がする。ひょっとすると、思いやり、つまり我が家の経済状況を配慮して単に遠慮しているだけなのかもしれない。ただ、それを確認することは私の効用値を上げることにはつながらない気がするので、やっぱりやめておこう。
*ウィキペディアより「効用」(2022年4月16日現在の記載)
*EQ-5Dの利用登録サイト
第20回おわり。第21回につづく




