第19回:医療経済学の“イ”
- Erwin Brunio
- 2022年3月22日
- 読了時間: 12分
更新日:2022年7月26日
2022年3月22日
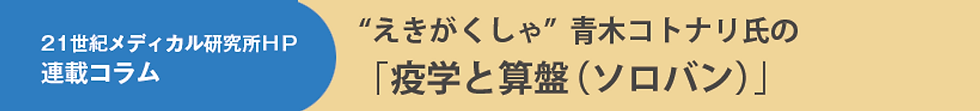
2020年10月20日から、3週間に1回、大手製薬企業勤務で“えきがくしゃ”の青木コトナリ氏による連載コラム「疫学と算盤(ソロバン)」がスタートしました。
日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボWEBサイトに連載し好評を博した連載コラム「医療DATAコト始め」の続編です。「疫学と算盤」、言い換えれば、「疫学」と「経済」または「医療経済」との間にどのような相関があるのか、「疫学」は「経済」や「暮らし」にどのような影響を与えうるのか。疫学は果たして役に立っているのか。“えきがくしゃ”青木コトナリ氏のユニークな視点から展開される新コラムです。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第19回:医療経済学の“イ”
イロハの“イ”
昨年の東京オリンピック・パラリンピックに続いて、北京で開催された冬季オリンピック・パラリンピックも先日、無事に閉会式を迎えた。さすがに2年続けての開催となると “ありがたみ”が少し薄れたような心持ちではあったが、繰り広げられる世界最高レベルの競技技術やドラマは今大会も私たちの心を様々に揺り動かしてくれた。退屈な巣ごもり生活の中でこれはありがたいことである。
国内において最も人気の高いウィンタースポーツは何かといえば、恐らくはフィギュアスケートではないかと思われるが、私の場合はスキージャンプやスピードスケートの方に軍配が上がる。その一方で、「ではTVでの応援・視聴に最も時間を費やした競技は何だろうか」と思いを馳せてみると、これはジャンプやスケートではなく、「恐らくはカーリングだったな」ということに思い至った。フルに見た試合は3試合程度であって、つまりは1試合当たりの時間が長いせいといえばそれまでかもしれないのだが、私のように無自覚に「一番、時間を奪われた北京オリンピック競技はカーリングだ」、という人は案外と多いかもしれない。

カーリングが日本でも人気となったのはいつの頃だっただろう。国内で認知されるようになった理由は、日本がメダル争いの出来る世界レベルになったからだと思われる。少なくとも私の場合、10年ほど前はカーリングの“カ”の字も知らなかった。一方で、カーリングはジャンプやスピードスケートのわかりやすさと比べて少しばかりルールが複雑で、初心者が楽しむには敷居が高いところがある。それでもいつの間にかルールの概要を知ったおかげで、こうしてまたオリンピックでの楽しみな競技が一つ出来たということでもある。
さて、前々回、前回と医療経済学分野のお話として薬剤経済学と私の個人的な病歴にお付き合い頂いたところだが、今回は立ち返って医療経済学の基本の話について取り上げたい。医学の世界において、「よい治療とはどれだけ効くのか」というシンプルな、~ジャンプやスピードスケートのような~基軸で優劣が付くのが基本である。
一方で、医療経済学の方はカーリングにも似て少しばかり概念がわかりにくく取っ付きにくい学問ではある。しかしながら食わず嫌いでは勿体ない。医療経済学の“イ”を知ることで、私の得たカーリングの“カ”の字のように、皆さんの知的好奇心を刺激することが出来たら何よりである。
費用最小化分析(CMA、Cost Minimization analysis)
医療経済学分野のアプローチの中で、もっともやさしい小学1年生的なアプローチといえば費用最小化分析だろう。これは医薬品や手術といった医療行為を比較する際、「比較する対象となるそれぞれの治療法の有効性も副作用リスクも全く同じとしたら」という前提に立つ。この前提に立てば、当然のことながら「コストが安い方がよい」という単純明快な答えが返ってくることになる。言い換えるならばこれは医療経済学というよりも純粋な経済学だ。
費用最小化分析のわかりやすい活用シーンとして想定されるのは、例えばジェネリック医薬品の普及促進に関する話題であろうか。病気を治す物質を発見しこれを医薬品として認可するまでの困難な道のりは本コラムでもしばしば取り上げてきたところである。その物質特許は大体10年程度であって、我々の業界でいうところのその特許性を取得している先発薬(せんぱつやく)が特許切れした後に、別の会社でも“同じ医薬品”を発売できるようになる。これを以前は後発薬(こうはつやく)と呼んでいたが、今はジェネリック医薬品と呼称する。もちろん、価格は先発薬と比べて随分と抑えられることが一般的で、この場合、ジェネリック医薬品の存在意義として「同じ効き目で同じ副作用リスクならば安価の方がよい」というロジックが費用最小化分析のコンセプトと重なる。
費用効果分析(CEA、Cost Effectiveness Analysis)
治療選択肢がいくつかある場合において、そのどれもが費用最小化分析のように効き目も副作用リスクも同じであるという仮定が成立することは多くはないだろう。治療選択肢は効果(effectiveness)にも差異があるとしたうえで、掛かるコストと共に分析するというアプローチが費用効果分析である。要するに「コスパによる比較」である。高級ステーキと牛丼のどちらが勝るのかを、美味しさだけでなくコストと組み合わせて比較するというわけだ。なお、ここでの「効果」というのは生存期間分析であったり、有効率であったりと、以前本コラム(第14回)で取り上げた薬剤疫学や生物統計学でおなじみの指標を用いる。
一方、コストといっても治療費の総計(直接費と言います)だけを比較の対象とするとは限らず、医療提供者側であればスタッフの人件費や機材、電気代なども要時は間接費として検討の対象とする。また、患者側であれば病院までの交通費なども含まれる。私のように毎年10万円以上の医療費を使っている人はよく知っていると思うが、病院までの交通費を医療費に含めて良いのは医療経済分野の専売特許ではなく、公的にも認められていて確定申告をすれば医療費控除として免税対象にもなる。
医療経済学では病院までの交通費に加え、「病気にかかっている間に失われるお金」にも思いを馳せる。有給休暇制度や福利厚生の充実している会社に勤務している人にはピンとこないかもしれないが、パン屋さんや美容院といった自営業者の主人が入院ともなれば、店を閉めなければならなくなる。こうした働く機会で本来得られるはずであったものは「機会費用」と呼称される。機会費用の損失額については、残念ながら手厚い生命保険にでも入っていなければ確定申告をしても返ってきそうにない。
さて、勘のよい人ならばお気づきかと思うが、前述の通り「医療者側」と「患者側」とでコストの対象が変わってくることもまた“医療経済学的”といえるだろう。社会・行政サイドの立場に立てば、仕事が出来ないことによって失われるサービスや商品、必要となる税金の額であったりと、対象とするコストや視点が変わってくる。つまり視点が変わることで、例えば患者側では「トータル評価で治療Aが優れる」と結論づけられる治療選択肢が、医療者側で見れば「別の治療Bの方が優れる」といった真逆の結論となることも起きえるというわけだ。
立場によって優劣の順序が変わる。この点がまさにザ・医療経済でもあり、純粋な医学・薬学分野の学問領域とは異なる特性といえるだろう。ピュアに「どちらの治療が効くのか」を訴求してきた人にしてみると、視点や立場が変わることで結論がひっくりかえるというのは学問や科学として生理的に認めたくない、という心理も働くかもしれない(正直にいえば実は私も“少し”そうだ)。
費用効果分析として、もっとも重要な指標と言えそうなのがアイサーである。日本語では増分費用効果比とも訳され、Incremental Cost Effectiveness Ratioの頭文字をとってICER、アイサーと発音する。ザックリいえばいくらの追加費用を掛けるとどれだけ効果が増すのかの比、ということである。先回の私の事例におけるICERの計算ロジックは表に示した通りであるが、より詳しい解説については専門書に譲りたい。

費用効用分析(CUA、Cost Utility Analysis)
費用効用分析は費用効果分析の親戚、お友達だ。先回、少しばかり触れたが、費用効果分析における「効果」が、例えば生存解析のように純粋に延命をモノサシとしているのに対して、費用効用分析は効用(Utility)をモノサシとする。効用とは、ザックリいえば、健常な1年と寝たきりの1年とを「質」の点で別のモノとして扱う。指標としてクオリー(QALY、quality adjusted life-year、質調整生存年)を用いることが基本となる。
概念的には例えば寝たきりを健常の0.5倍として算出した場合、100人の患者さん全員が健常な状態で5年延命する治療と、100人の患者さん全員が寝たきり状態ではあるが10年延命する治療を同値とみなすというのが費用効用分析の考え方となる。
実際のところ、健常な1年と寝たきりの1年とを同じ1年とはみなせない、というスタンスについてはある程度、賛成して頂けるところかと思える。一方で、ここにも厄介な“不確実性”が内在している。例えば、極めて有効ではあるものの、残念ながら脱毛や手のしびれという副作用が発生する治療があったとしよう。もう一方の治療では効き目はいまいちでもこうした副作用がないとしたら、果たしてどちらの治療が良いということになるだろうか。
QALYを使った判定をする際、女優さんにおける脱毛やピアニストにおける手のしびれと、一般の人での脱毛や手のしびれがもたらす社会的・経済的なダメージは同値ではないはずだ。視点の違いで優劣の判定が変わりえるだけでなく、その患者さんの感じ方や受け止め方の違いにおいてもまた医療経済学特有の不確実性の課題が内包する。
費用便益分析(CUA、Cost Benefit Analysis)
「便益」は経済学用語であり、医療分野においてはアイサーやクオリー同様に医療経済学分野特有の概念だといえるだろう。前述したような種々の分析は、あくまで「効き目(+副作用リスク)」と「費用」という異なる概念をセットでとらえる考え方に立つが、費用便益分析では、ザックリいえばヒトの人生や命を金額に換算して、例えば1年の生存を均一に500万円とする等、「価格」という1つの単位で算出して治療間を比較するやり方である。
「オリンピック競技でいえばノルディック複合のような考えである」とするとわかりやすいだろうか。ノルディック複合はスキージャンプの距離を時間に換算してクロスカントリーのスタート時間を変えるという、「時間」で統一させて競う競技である。
マルコフモデル
医療経済学の“イ”として最後の紹介したいのがマルコフモデルである。ここまで紹介してきたアプローチは、全て病気の罹患から治癒に至るまで時間的には一方通行の考えに立ったものであるが、慢性疾患など容態が良くなったり悪くなったりするものをうまくとらえることが苦手という弱点がある。私もこれまで入退院を繰り返してきており、そこには赤信号、黄色信号、青信号のような、おおまかに3種類ほどの健康状態で考えると研究や考察がしやすくなる。
図はマルコフモデルの一例を示したものであり、矢印の横に添えてあるパーセントの数字は、次の状態へ移る確率を表す。私のように入退院を繰り返す病状を表しているが、入院したとしても退院出来る可能性の方がはるかに高く、それでも平生と比べればやはり死亡する可能性は高めに“確率変動”する。一旦、状態が「死亡」となれば別の状態に映る確率は0%、可逆性がない(説明するまでもなかったですね)。

因みに、先に紹介したモデル図のことは「判断樹モデル」といい、図示する場合には治療選択を□で、イベント発生確率のところは○で、ゴール・帰結のところは左向きの△で表記することが万国共通で決まっている。判断樹モデルやマルコフモデルを用いて病状の回復や悪化と、一方で要する医療費とを検討することを総称してモデル分析という。
医療経済学と科学一般と
ここまで、医療経済学の”イ”として、いくつかの分析方法やキーワードを紹介してきたところであるが如何だったろうか。「アイサー」「クオリー」「マルコフモデル」といった言葉を使えば、少なくとも医療経済学についてはシロウトではないな、と認識されること請け合いである。
さて、「医療経済学は随分と不確実性があって、科学一般のようにはスッキリしない学問領域だな」と感じられたとしたら、恐らくそれは正しい認識といえよう。私は社会学や哲学分野に近い領域だと思っていて、故に自然科学のような万人が承知するような正解が用意されていることはほとんどないものだと認識している。立場が異なれば必要経費の考え方が違ってくるし、QALYについても個人差があり、数学や物理学のように江戸っ子気質にスパッと合意形成が出来るものでもない。その意味において、現代における医療経済学的アプローチの社会的地位(?)は「科学」というよりはむしろ意思決定に際しての「検討材料」「折衝材料」といった参考資料的な立場にあるといえるかもしれない。
これはオリンピックやスポーツ大会において、どんなに優れたパフォーマンスを演じたとしても評価者によって得点に相応のブレが生じてしまうことにもどこか似ている。ある意味では人間の限界であり、その価値観の違いによってしばしば悲劇を引き起こすのもまた然りである。
実際のところ、経済的な合理性がないということで、効き目があることは証明されていても実際には自国でその治療を受けることが出来なかったり、高額すぎて手が出せなかったりということが起きている。価値観の不一致は他国での話ばかりではない。例えば国内においても「90歳以上の老人に高額な治療を提供するのは是か非か」といった問いでは意見が一致しそうにない。正義はどこにあるのだろうか。
遺憾の意
人の業(ごう)、そして悲劇。北京オリンピックの閉会式で子供たちが歌った歌声は美しく心に響く。その一方でオリンピック・パラリンピックの式典で演出される美しい世界が実は虚構であることを大人になってしまった私たちはよく知っている。ウイグル自治区の問題、ドーピングの問題、そしてパラリンピックの最中におきたロシアによるウクライナへの侵攻。私たちはこうした問題に対してなんと無力なことか。出来ることといえばイカンの“イ”(遺憾の意)を示すことくらいだろう。

最後にカーリングの話に戻そう。カーリングは基本的に審判員ナシで競技が行われるという。最初にそれを聞いた時は耳を疑った。「そのようなことが果たして可能なのだろうか」と。地球上で戦火が消えた時代はなく、今こうしている間でも悲劇が続いている。それでも敵と味方が“監視”など無くても分かり合える可能性があることを、審判員の不要なカーリングが示唆してくれているではないか。せめて前向きな気持ちで今回の結びとしたい。
第19回おわり。第20回につづく




