第26回:報道の歪曲と科学
- Erwin Brunio
- 2022年11月2日
- 読了時間: 11分
更新日:2023年9月20日
2022年11月07日
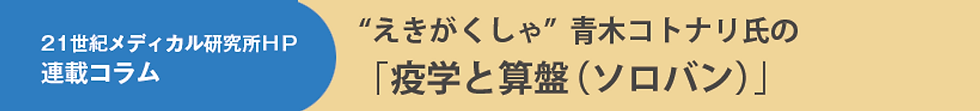
2020年10月20日から、3週間に1回、大手製薬企業勤務で“えきがくしゃ”の青木コトナリ氏による連載コラム「疫学と算盤(ソロバン)」がスタートしました。
日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボWEBサイトに連載し好評を博した連載コラム「医療DATAコト始め」の続編です。「疫学と算盤」、言い換えれば、「疫学」と「経済」または「医療経済」との間にどのような相関があるのか、「疫学」は「経済」や「暮らし」にどのような影響を与えうるのか。疫学は果たして役に立っているのか。“えきがくしゃ”青木コトナリ氏のユニークな視点から展開される新コラムです。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第26回:報道の歪曲と科学
人間だもの
全国旅行支援策の影響もあるだろうか。東京駅の丸の内口近辺を歩いていたらコロナ禍の前に戻ったかのように人が溢れ賑わっている。外国人旅行客らしい人の姿も見られ、入国規制の撤廃も関わっているのかもしれない。
東京で働き東京で暮らす私にとって、東京の街に活気が戻るというのは本来喜ばしいことなのだが、シンプルに「ランチを食べる」ことだけ切り取るとそうとも言えない。どの店も大行列で、なかなか最後方に並ぶ気になれない。この店もダメ、ここもダメ、と歩いているうちに思いがけず隣駅の有楽町まで来てしまい東京国際フォーラム内にあるレストランで食事をすることにした。
この東京国際フォーラムの一角に相田みつをさんの書道作品を展示する「相田みつを美術館」がある。美術館に入るには入場料が必要なのだが、併設されているミュージアムショップは入場料無料なのでぶらりと立ち寄るにはちょうど良い。「人間だもの」なんて言葉を活字にしただけではどうということもないのだが、独特な書道タッチで表現されるとどういうわけだか心に刺さる。陳腐な表現をご容赦いただけるのであれば、これはもはや情報伝達の発明品といえるだろう。

ショップには氏の書道作品が転記された様々なグッズや土産品―マグカップ、クッキー等々―が所狭しと売られている。まさかのクッキー。氏が生きていたなら驚くに違いない。キャラクタービジネスで有名なサンリオとコラボした日めくりカレンダー、「ハローキティの、人間だもの」なんていう商品まである。ところでキティちゃんって人間だったかな。
前回、前々回と心理学分野で有名なスタンフォード監獄実験とミルグラム実験を取り上げたところである。研究により得られた人間の心理はその後の研究にて再現され、確かに役割効果や社会的勢力といった目に見えないものの存在が共有された。その一方で、望ましい結果を得ようとせんがための研究者らの“熱病”、それもまた一方での人間らしさとして概観したところである。
キャサリン・ジェノヴィース事件
今回とりあげるのは心理学分野で語られる“伝説”のうち、これほどにセンセーショナルな事件もないだろうという、キャサリン・ジェノヴィース事件についてである。もし皆さんが社会心理学に関する書籍をお持ちであれば、スタンフォード監獄実験、ミルグラム実験と合わせ取り上げられていること請け合いだ。
これは1964年アメリカのニューヨーク州で起きた殺人事件である。何故に有名になったのかといえば、推理小説にも有りがちな殺人動機やその方法でもなく、また殺人犯の個性や
異質性でもない。この事件の有名にさせたのは“脇役が主役”というところにある。どういうことか、事件の概要を簡単に紹介しよう。
事件当日、ジェノヴィーズはキュー・ガーデン地区とは別地区であるホリスにてバーのマネージャとして未明まで仕事をしていた。自宅近くの駐車場まで車で帰宅し、そこから自宅まで歩いているところをモーズリーにナイフで背中を刺された。ジェノヴィーズが悲鳴を上げると、アパートの窓に明かりがともり、1人の住人が窓を開け、ジェノヴィーズを離すよう怒鳴った。モーズリーは住民を見上げ、肩をすくめると、ジェノヴィーズから離れ、自分の車まで歩いて行った。しかし、窓の明かりが消えると、モーズリーは、また向きを変えて、自分の部屋に帰ろうとしたジェノヴィーズを再度刺した。ジェノヴィーズは再び叫び声を上げると、建物の明かりが灯った。だが、モーズリーはジェノヴィーズのもとへ戻り、首などを刺す致命傷を負わせた。モーズリーは自分の車に乗って立ち去った。
その後、同じアパートに住む男性が警察に通報したが、ジェノヴィーズはすでに亡くなっていた。事件から6日後、モーズリーを逮捕し、起訴した。(2022年10月24日ウィキペディア*より)
この事件をアパートから見聞していたといわれる“傍観者”は37人にもおよぶという。ニューヨーク・タイムズは「ジェノヴィーズは大声で助けを求めたが、近所の住人は誰ひとり警察に通報しなかった」と報道している。これを読んだニューヨーカーは「なんて冷酷な連中だ」と心を乱したことだろう。恐らくであるが「きっと誰かが対応してくれる」と考え、自分は行動しないという経験は誰しも身に覚えがあるハズだ。こうした心理は傍観者効果と命名され、以降の研究でも度々再現され確認されている。ただ、この事件の場合、本当に誰一人、行動を起こさず傍観したなんていうことが本当に有り得たのだろうか。

マスメディアの力学
さて、前々回、前回と本コラムを読んでくださった方はひょっとしたら“同じフォーマットだな”と察したことかもしれない。その通り、この事件も2つの心理学実験と同様、一般的によく知られているお話と実際がかなり違うようだ。
以降はルトガー・ブレグマン著「Humankind」からの引用である。これだけの人数が全員無関心であったことを疑い再調査に乗り出したのは歴史研究家ジョセフ・ド・メイ氏、事件から10年後のことだという。その結果、実際には目撃者から警察へは複数の通報があったことが確認された。またキャサリン・ジェノヴィーズ絶命の際はアパートの住人らに無視され孤独に死んだのではなく、ソフィアという同じアパートの住人に抱きかかれながら息を引きとっていたことも判明した。犯人逮捕のお手柄も当日の目撃者によるものだ。しかしながら不思議なことに、こうしたことの一切は全く報道されていない。
因みに何故、複数の通報を受けながら警察が出動しなかったかといえば、それに至らない夫婦喧嘩だろうと判断されたらしい。結果的に殺人が起きたので失態であることは間違いないのだろうが、今でいうところのDVが当時は珍しくなく、通報がきてもしばしば手に負えないことがあったという時代背景の違いも踏まえるべきだろう。
一方、キャサリンを抱きかかえたというソフィアは、アパートの階段で血を流しながら倒
れている人がいると夫から聞くと、犯人と鉢合わせになるぞという通告も顧みずに部屋を飛び出したという。ソフィアの息子によればその一部始終を新聞社に話したらしいのだが、実際に記事になったのは「巻き込まれたくなかった」というコメントであって、これは捏造といっていい。彼女は憤慨し「マスコミの人間とは二度と口を聞かない」と誓ったという。かくして誰一人、通報すらせず部屋からも出てこなかったとして、その“異常さ”に彩られニューヨーク・タイムズ紙の一面トップ記事となった。
一流といわれる新聞社がこれでは、ソフィアの決意もある意味で正解といえるかもしれない。こうしたマスコミの言動は日常茶飯事であって氷山の一角に過ぎないのだろうか。私の知り合いにも事実と異なる報道に傷つけられ、「マスコミの人間とは口を聞かない」という人がいる。運よく私の知る記者さんや編集局の人は少なくとも私にとって信頼に足る人ばかりで、「マスコミ」と十把ひとからげにして忌み嫌うのもどうかとは思うのだが。
マスメディアの役割
さて、マスメディアの役割とはそもそも何だろう。私たちはマスメディアに何を期待しているのか。その有力な答えの1つは、『ジャーナリズムには「客観報道主義」が求められている』というものである。客観性のある報道をする上での構成要素は真実性と不偏性であり、客観性はさらに事実性と関連性、一方の不偏性は均衡性と中立性で構成される*。詳しい説明は専門書に譲るが、キャサリン・ジェノヴィース事件の報道は到底こうした要求を満たすようなものではないだろうし、少しばかり誇張や偏重が混ざったような記事ということであれば私たちもよく目にする。
一方で、ジャーナリズムには「権力の監視」こそが最も重要な要求であるという視点もある。政治家や組織のトップ、あるいはアカデミアにおける権力者の不適切な立ち振る舞いを糾弾できるのは立場の弱い被害者当人よりもむしろマスメディアだ。

客観報道主義と権力の監視、どちらを優先して期待するにしてもバランスをとるのが難しそうである。情報の受け手である私たちもマスメディアに期待する要求の優先度は違っており、シンプルに客観的であることだけを期待する人もいるだろう。しかしながら一方で、様々な候補の中から報道する事件・事案を選び、その順序や記事の大きさを判断するマスメディアという機能は、いわば主観とバイアスにまみれている。然るに、存在としてそもそも客観的なのかといえばそんなハズはあるまい。無論、未来社会にはこうした判断に人間の主観に代わってAIアルゴリズム判定が導入されることはあるかもしれないが。
メディアドクター研究会
本コラムのテーマである「科学」に関する記事については、刑事事件と比べてもはるかに報道の客観性に強い要求があるといえるだろう。一介の記者に「私はこの研究結果を支持します」と宣言されるのは迷惑でしかなく、読み手、聞き手としてはいかに客観性をもった報道をしてくれるのかということを期待するばかりである。
その意味では日本の科学記事は欧米に比して大きく劣ると言われている。例えば日本のある有名な大学での研究結果が無批判に大きな記事となって「〇〇であることがわかった」といった論調で報道されることがよくあるが、これは国際的な科学記事のマナーを守っていない。単に「有名大学の研究だから」といった“偏重”報道であることを疑うべきだろう。
では、本来的にはどのような報道がなされるべきだろうか。まずは同じテーマでの研究が世界では行われていなかったのかどうかを調べたうえで、あくまで1つの研究結果として
取り上げるべきだ。調べてみたら同様な研究が過去に30件あり、今回と同じ結果が10件、その逆の結果が20件あるかもしれない。今回の研究結果は目新しいものでもなく、単に1件の研究結果がプラスされただけで学説には影響が無いかもしれないのだ。
また、引用したジャーナルについては出所を明らかにする必要がある。その他、どのようなことに留意すべきかについては、メディアドクター研究会が10の指標(利用可能性、新規性、代替性、あおり・病気づくり、科学的根拠、効果の定量化、弊害、コスト、情報源と利益相反、見出しの適切性)として整理している*。こうした指標を用いて採点してみると、あまりに日本の科学記事に合格点が少ないというのが本研究会の共通見解のようである。
キティは帰らない
現代は情報沸騰社会である。私たちが情報ソースに利用している記事も以前のようにマスメディア一辺倒ではなく、むしろSNSやインターネット経由の口コミの方が多いかもしれない。フェイクニュースの中から正しい情報を嗅ぎ分けるのは私たち自身の責任であり、しばしばメディア・リテラシーを向上させよと注意喚起される。それでも、あるいはだからこそマスメディアに対しては、是非とも正しいニュースを伝えて欲しいという期待が大きいとも言えよう。
それにしてもキャサリン・ジェノヴィース事件の報道は酷いものである。これだけの意図的な歪曲は本来、日本の科学報道の残念さとは同じ次元で語るべきものではなく、犯罪といっていい。後年になってこの“でっちあげ”を曝露したドキュメンタリーが製作されたようだが、あとの祭りとでも言おうか、その話はほとんど知られていない。傍観者効果の説明をするにはこの事件がうってつけだからということもあるのだろう。
前回、前々回と取り上げた科学者による“熱病”、あるいはデータ捏造、今回取り上げた、でっちあげの記事、不適切な科学報道、そして殺人。あるいはテロ、戦争。これらをごちゃ混ぜにして「人間だもの」では済ませられまい。また、一個人や一組織を取り上げて糾弾したところで本質的な問題が解決されるとも思えない。資本主義に代わる新たな価値観への移行や社会システムの再構築など俯瞰的にとらえる必要のある課題といえるだろう。

キャサリン・ジェノヴィースは当時28歳、ダンスに夢中でニューヨークが大好きな快活な女性だったらしい。友達も多く、キティと呼ばれて親しまれていたという。彼女の命は返ってこないし、また人類にとって恐らく未来永劫、殺人事件ゼロということは考えられないだろう。一方で傍観者効果については、後の研究で確かにその存在は幾度も確認されたものの、心理学者マリー・インデゴーによれば重大事案に直面すると傍観者効果は効かない、90%のケースで人は人を助けることが確認されたという。
傍観していないで助ける人の方が多い―。良かった。相田みつを氏は人間賛歌を筆にしたためたハズで、決して犯罪行為の言い訳に使って欲しかったわけではないだろう。どうして人は人を助けるのかと問われたときにこそ「人間だもの」と、そう応えたい。
第26回おわり。第27回につづく
*ウィキペディア「キティ・ジェノヴィーズ事件」より2022年10月24日取得) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6
*Westerståhl's (1983) Scheme of the Concept of Objectivity(客観性の概念のスキーム) https://www.researchgate.net/figure/Westerstahls-1983-Scheme-of-the-Concept-of-Objectivity_fig1_279527458
メディアドクター研究会 http://www.mediadoctor.jp/




