第27回:科学の境界線
- Erwin Brunio
- 2022年12月6日
- 読了時間: 14分
更新日:2023年1月25日
2022年12月06日
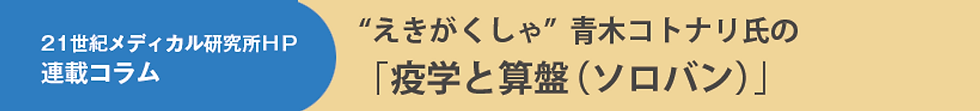
2020年10月20日から、3週間に1回、大手製薬企業勤務で“えきがくしゃ”の青木コトナリ氏による連載コラム「疫学と算盤(ソロバン)」がスタートしました。
日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボWEBサイトに連載し好評を博した連載コラム「医療DATAコト始め」の続編です。「疫学と算盤」、言い換えれば、「疫学」と「経済」または「医療経済」との間にどのような相関があるのか、「疫学」は「経済」や「暮らし」にどのような影響を与えうるのか。疫学は果たして役に立っているのか。“えきがくしゃ”青木コトナリ氏のユニークな視点から展開される新コラムです。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第27回:科学の境界線
リアルな学会参加
先日、神戸臨床研究情報センターで開催された、日本薬剤疫学会主催の学術総会に参加することが出来た。出来た、というのは少々大げさかもしれないのだが、コロナ流行以降の学会参加は近郊での開催以外はもっぱらオンライン参加だったので、新幹線での遠方出張はおよそ3年ぶりの“レア”であった。会社も学会等へのリアル参加は控えるよう、推奨していたので、まずは会社・上長の許諾に感謝である。
当該の学会は私自身も理事職を務めさせて頂いており、理事の先生方はもとより、評議員、学会員を問わず多くの先生方や企業会員と知り合いも多い。学会参加の意義というのはその専門スキルを向上させたり、新たな知見を得たりというのがもちろん主たる目的なのであるが、一方でこうした先生方や友人と直接会えることは、コロナ禍にあっては何より有難い機会である。今回も懐かしい面々と久しぶりにリアルでお会いすることが出来た。

日本薬剤疫学会は、民間企業の社員である私が当該の運営を担う理事職であることが、まさにその性格としての象徴ともいえるかもしれない。つまり通常の学問領域の学会ではアカデミアの先生方、医療分野では医療者が、それぞれ運営に関わる理事職を構成するものであって、民間企業に所属する者にしてみれば見えない境界線のようなものを感じることがあるのだが、本学会においてはそれがない(あるいは私が鈍感なだけかもしれない)。
実際のところ、医学系学会では臨床医をやめて製薬企業でメディカル・ドクター職となったと同時に退会しなければならないという学会も多いと聞くが、こうした規則の良し悪しを部外者が評すべきものではないだろう。それは相応に当該の専門力を高めたり、同じ悩みを抱える“同業者”としての結束を高めたりといった、学会員にとって得難い価値もあるハズだ。境界線があることは必ずしも悪いことではない。
今回はこうした学問領域の「境界線」という、ニッチなところにスポットを当ててみたい。日本には、本コラムタイトルでもある「疫学」という文言を含む学会として、他に日本疫学会、日本臨床疫学会もある。傍からみたらこうしたくくりの違いはあまりよくわからないものだろうし、ときには学問の定義としては合理性があるとはいえず、やはり人間の営みである以上、学会創始者らの仲の良し悪しのようなところで“境界”が引かれていたりもするように感じることもある。もちろん今回取り上げるのはあくまで学術的な定義や認知科学としての「境界線」の方であり、仲の良し悪しについていえば園長先生が園児にたしなめると同じように「みんな、仲良くしようね」としか言いようがない。
便利だから線を引く
私たちが学問領域に境界線を引きたがる理由は、何のことはない、その方が便利だからだ。あるいはその方が認識しやすいからだ、ともいえよう。ハラリ氏は、世界的ベストセラーとなった著書「サピエンス全史」の中で、何故に私たちホモ・サピエンスが、唯一の人類種として現存しているのかについて、「虚構を信じる力が優れていた」と考察している。絶滅した人類種であるネアンデルタール人は私たちよりも体格的にも優れ、脳の大きさも優れていたという。1対1での生死をかけた勝負では到底勝ち目のない相手に対して、私たちはどうやらありもしないことを集団で信じる~言い換えるならば少しおバカな~特性により、集団での勝敗では逆転することが出来たらしい。
確かに、神話も宗教もこれから未来永劫、科学的にその存在を示すことは出来そうには思えないが、多くの人類-ホモ・サピエンス―はこれを信じ切ることが出来る。国境のような見えない境界線も地図上で引くことが出来るし、宗教や国境を巡っておバカな殺し合いという副作用があるにせよ、便利だとなれば、新たな分類が提案されたとき、それを皆で受け入れることが可能である。ネアンデルタール人が私たちより聡明で、「天や地の創始者などいるものか」と形而上学的な(あるいは妄想狂的な)ものを否定する能力があったせいで絶滅したとすれば、これは皮肉ともいえる。私たちホモ・サピエンスの仲間の中でもあまり聡明でない方が生命力としては案外と優れているのかもしれない。
便利な境界線というのは、学問領域に限定されるものではないだろう。欧米においては「海草(seaweed)」としてひとくくりに分類する方が便利なそれを、日本の食文化では海苔、ワカメ、昆布、ひじき、めかぶ、もずく、アオサと、まあ多種多様に分類しているのはそれが便利だからだ。花に名前を付けたり、オオカミとイヌとを別種としたりするのもそのように分類した方が好都合であり認知がしやすいからである。
オントロジー
一方で、便利だからと言ってモノや概念に名前をつけ、他と境界線を引いた後になって、その境界線の線上ともいえる微妙なモノや概念が見つかったり登場したときは厄介だ。上述したオオカミとイヌの分類がいつ頃のことなのかはわからないが、外観としてそのどちらかはっきりとは区別がつかない写真に出会ったときに戸惑うのはAI技術だけではない。こうした事態に直面してしまうと私たちは仕方なくその定義化を試み、予定調和的に溜飲を下げるのが常である。
とはいえ、実際のところはこうした定義まで理解していないと困ることはそんなに多いことでもなさそうである。心理学分野には「プロトタイプ(代表的事例)理論」という用語があるのだが、これは私たち人類は大抵の場合その典型的事例にて物事を判断するのが常であり、きわどい境界線やその定義について普段は全く意識しないものである、といった理論である。
一方、もはやAIなる機械たちが「顔」という概念を理解し的確にとらえていることを私たちは知っているが、「顔とは何ですか?」とその定義を問われて的確に答えられる人は多くないだろう。AIにそれと認識させる前段として概念定義をさせる際に用いられる言葉はオントロジーと呼称されるが、これは元を辿れば哲学系分野に係る認知学からの出所であり、概念を体系化し構造化するものといった意味合いがある。
オントロジーが貢献する分野は、必ずしもAIに学習させるときばかりではないだろう。例えば病気の分類においては興味関心の違いによって好都合な境界線が異なる場合がある。具体的には、心筋梗塞と脳梗塞を同じ「梗塞」として分類したい医学系研究者も多いだろうが、脳外科と心臓外科にしてみればその発生部位別の分類で、例えば心筋梗塞は心不全と、脳梗塞は脳卒中と、近しい分類として境界線を引きたいだろう。
日本でよく用いられる病名コードはほとんどが後者の要求にのみ応えるものであるが、国際医療用語であるSNOMED-CT(Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms)*では概念の構造をオントロジー的に整理されており、異なる双方の要求に応えることが出来るものである。日本が国際整合を目指すならばこうしたコード体系の“輸入”を何れ本気で考えなければならない。
また、認知科学に目を向けるとこうした境界線の議論はとても今回こっきりでアッサリと済ますことが出来ないディープな議論を展開しなければいけないことになる。私たちの物事を構造的にとらえる認知の仕組みは、カントの唱えたアプリオリ(先験的)なものなのか、あるいは社会なる構造の中に私たちが身をおく中で、社会学者らのいう「社会的事実」などに触れ合うからこそ生まれるものなのか。話が尽きないことになること請け合いだ。
心理学+社会学
さて、このところはもっぱら心理学分野を例示しながら本来的な科学の在り方や報道の在り方を概観してきたところである。前回までの3回でとりあげたスタンフォードの監獄実験、アイヒマン実験、キティ・ジェノヴィーズ事件は確かに心理学分野のお話ではあるのだが、そこには社会学のニュアンスがすべて内包していることに皆さんもお気づきのことだと思う。
社会学なる学問領域が見いだされた、あるいは他の学問領域から切り取られて“独立”したのは「社会学」という名前を付けたオーギュスト・コント(Auguste Comte)の時代である。TVタレントでもある古市憲寿さんが著書「古市くん、社会学を学び直しなさい!!」の冒頭でとりあげているように、社会学者に「社会学って何ですか?」と聞いても自身らの専門領域であるにも関わらず、うまく答えることが出来ないらしい。
それでもデュルケームの著書「自殺論」にある社会的自殺のアルゴリズムであったり、マックス・ウェーバーが“官僚制”として組織の成り立ちや特性を整理した概念は強い説得力のあるものだ。「社会的事実」は存在し、故にそれを分析する社会学もまた存在しているように~虚構を信じられる私たちホモ・サピエンスとしては~認知することが容易に出来るのである。

一方の心理学の方もその出所としては、現代の私たちが科学と呼称する分野のものとは到底かけ離れた、占いや黒魔術的な色彩をまとったものであったといえよう。以前、本コラムでも取り上げたが、これが科学分野に仲間入りしたといえるのは、実証研究が当たり前になったからである。
ただし、もう少し踏み込んで“暴論”を申し上げるならば、心理学分野は今のような体裁としては“絶滅”するのではと、私には思える。何故なら、私たちが当たり前のように認識し口にしている「こころ」などというものは物理的には臓器として実在しておらず~あるいは少なくとも心臓にはそのような機能はなく、何れの未来においては認知論や概念論、感情論などに切り取られた脳科学の一分野に据え置く方が、よほど科学的には合理的に思えるからである(でも、心臓の形をデフォルメしているハートマークはキュートで、これは残したいナ)。
かくして「虚構」あるいは「便利」ということで切り取られた社会学と心理学は監獄実験、アイヒマン実験等の研究分野の勃興によって新たに「社会心理学」なる分野を新登場させることになった。これにより恐らくは心理学ど真ん中でもなく、社会学ど真ん中でもない研究に新たな便宜として境界線が引かれた訳である。
心理学+経済学
本コラムは「疫学」と、もう一方で「算盤」、つまり経済学ないしはその“境界線”上にある医療経済学を主たるテーマとして展開する予定であった。そろそろ心理学のお話は一区切りとして経済学分野へ戻ろうかと思うのだが、この「心理学」と「経済学」の境界線上にもやはり何らかの“虚構”が見え隠れしており、今ではかなり周知された学問分野である「行動経済学」がそれである。
こちらの創始者はプロスペクト理論を提唱したダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーと言っていいだろう。従来の経済学は「誰もが経済的に合理的な最適行動をしていると仮定した場合、」という、無茶な前提をベースとして発展した学問であったが、この大前提を大胆にも否定したのが彼らである。
「え? むしろ誰もが合理的というのは変であって、これにツッコミを入れる方が普通なのでは?」と感じられる人も多いかと思うのだが、自然科学や数理を扱う学問領域においてこれはかなり大胆な所業である。例えば算数の問題で「サイコロを振って、偶数の目が出る確率は?」と聞かれたら私たちは造作なく「2分の1です」と答えるだろうが、これは「すべてのサイコロの目が出る確率が同じ」という大前提に支えられている。およそこのような精巧なサイコロを作ることは実際には不可能であり、重さの均質性や角の曲がり具合などの違いからどうしても均一なものを作り上げるのは出来ないだろう。あるいは仮に手間暇、お金をかけて作れてもサイコロの振り方次第で完全均一な出目は破綻してしまう。
「それって誤差って言うのでは?」と思った人はセンスがよい。その通り、従来の経済学において合理的な最適行動をとらない人の振る舞いは行動経済学が登場するまでは「誤差」とひとくくりにされていたわけである。前述したプロスペクト理論はこの誤差の“可視化”に成功している。
具体的にいえば、私たちは1万円儲かるときのうれしさよりも1万円損をする悲しさの方が大きいし、2000円の商品を1000円で売る際には、「50%オフ」と大々的に表示した店の方が表示していない店よりもはるかに売れる。こうしたことは確かに同じホモ・サピエンスである私たちにとって思い当たるフシはあるのだが、あくまで従来の経済学ではこれは誤差であり、一方の行動経済学ではプロスペクト理論等を活用し、具体的に何倍の悲しさなのか、何倍売れるのかを割り出すのである。カーネマンはそもそも経済学を体系的に学んだことのない、ゴリゴリの心理学者なのであるが、行動経済学の創始によってノーベル経済学賞を受賞している。行動経済学については次回また取り上げたい。
棒打ち刑
「出る杭は打たれる」という言葉がある。また、「忖度する」という言葉はあっという間に日本中に知れ渡った。私もそうであるのだが、行政が主催するような著名人・学会の権威が列席する会議に呼ばれたときには到底、思ったようなことが言えないのが常である。本来ならば当該の会合には重要な使命があり、いち早く社会課題を解決するために参加者全員が本気を出して分け隔てなく議論すべきところなのだろう。しかしながら私の脳裏によぎるのは「この、エライ先生は反論を許容できる力量(能力)が備わっているだろうか」である。すなわち、異論・反論をしても許容できる人物であるかどうかをまずは推察し、どうやらそのような能力があると思えた場合にのみでしか反論をしないということになる。
最近は心理学分野の用語「心理的安全性」という言葉も知られるようになったが、参加者が皆、率直な物言いが出来るよう、主催者が冒頭で「異論・反論、大歓迎」と、「ただし、人格を攻撃するような物言いはダメ」といった心理的安全性を担保するファシリテーションをして頂きたいものだと、常に願うところである。
さて、行動経済学なる学問領域の黎明期もまた、当然のことながら従来の経済学を批判するところからのものであり、心理的安全性が担保できていない場面において(要するにほとんどの場面において)従来の権威から痛烈な“棒打ち刑”を浴びせられてきたと、行動経済学者のリチャード・セイラーは回顧している。
氏の書籍「行動経済学の逆襲」には、「あなたのやり方はここが間違っている」「こんな大事なことを無視している」と説く人が多かったという記載がある。察するに、実際に行動経済学者らに仕向けられた従来の経済学者らからの本当の“仕打ち”はこうした書籍には到底、生々しすぎて書けないレベルのものも含まれるのではないだろうか。
しかしながらその一方で、この書籍にはある有名な経済学者が「あなたが言っていることを真剣に受け止めるなら、私はどうすればいいのでしょう。私のスキルは最適化問題を解決することなんですが。」という発言も紹介されている。誰もが経済学的に最適行動をするという砂上の城に立つ、従来の経済学が時代遅れになる、これを冷静に受け止めることが出来たこの経済学者の行動こそが稀にみるホモ・サピエンスとしての奇跡、「最適行動」といえないだろうか。
ひじ掛け
さて、冒頭の総会は3日間の開催であったのだが、どうしても東京に戻らなければならない事情があって2日目の夜に神戸空港から飛行機で帰路につくことになった。チケットは売り切れ間際だったようで、「非常口付近の真ん中の席ならばとれる」らしい。搭乗してみると非常口付近の乗客には他にはないミッションが与えられており、実際に非常事態が起きて非常口を使うときにはその開閉や搭乗者の脱出援助をしなければならないのだそうだ。なるほど、人気のない席なわけだ。

また、窓際でもなく通路側でもない席は新幹線でもそうだがやはり人気がない。今回のフライトでは本来は先に搭乗するハズの窓際の人がなかなか来ないため、しばらくは1人で両脇のひじ掛けを独占するような状態が出発直前まで続くことになった。ところで、座席の境界線となるひじ掛けは真ん中の席の私が独占していいものなのだろうか。こんなところにも境界線のちっぽけな問題がしっかりと鎮座している。境界線問題、恐るべしだ。
第27回おわり。第28回につづく
第27回日本薬剤疫学会学術総会HP (2022.12.1.取得)
SNOMEDサイト
Wikipedia「オーギュスト・コント」
Wikipedia「boundari-work」




