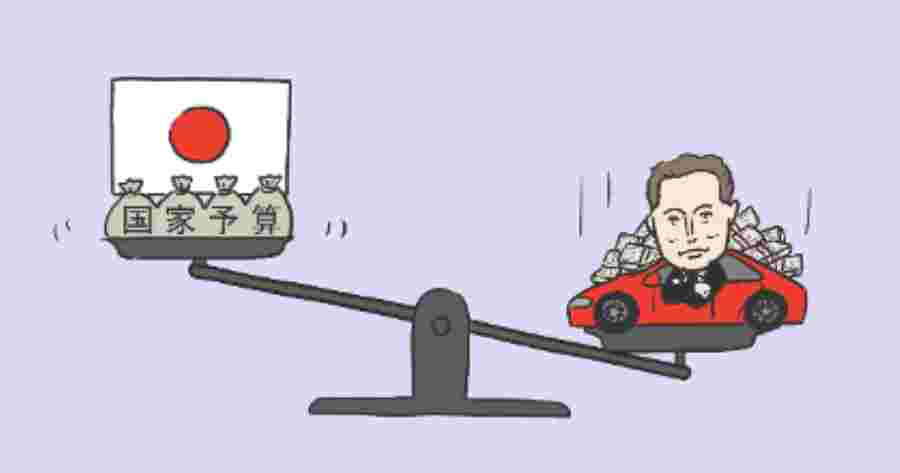第28回:心理学と経済学の交差点
- Erwin Brunio
- 2023年1月25日
- 読了時間: 10分
更新日:2023年2月17日
2023年1月25日
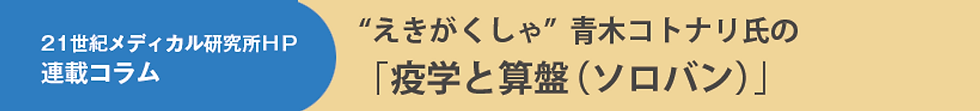
2020年10月20日から、3週間に1回、大手製薬企業勤務で“えきがくしゃ”の青木コトナリ氏による連載コラム「疫学と算盤(ソロバン)」がスタートしました。
日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボWEBサイトに連載し好評を博した連載コラム「医療DATAコト始め」の続編です。「疫学と算盤」、言い換えれば、「疫学」と「経済」または「医療経済」との間にどのような相関があるのか、「疫学」は「経済」や「暮らし」にどのような影響を与えうるのか。疫学は果たして役に立っているのか。“えきがくしゃ”青木コトナリ氏のユニークな視点から展開される新コラムです。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第28回:心理学と経済学の交差点
物価の上昇
物価の上昇が止まらない。マクドナルドは110円だったハンバーガーを1年足らずで3回値上げし170円になったという。電車の運賃も金閣寺の参拝料も上がるという。
先日、近所にある長崎チャンポンのチェーン店に寄ったのだが、1杯740円という価格にひるんでしまった。ラーメンが1000円を超えることが珍しくなくなった昨今、この価格が高いということでも無いのだろうが、1杯399円という時代が長かったことを知っている私にとって740円は躊躇する価格だ。結局、期間限定という北海道コーンみそチャンポンなる商品を食べることになったのだが、それが美味しかったのでまあそれでヨシだ。

何気ない日常の一コマである。価格の上昇というのは経済学一般論としてはむしろ歓迎すべき側面があり、要するに私たちの給料が上がるためには物理的に商品やサービスの価格があがってくれる必要がある。過去20年ほど大卒初任給が据え置かれているのは先進国では日本だけであり、先進国以外の国の中にはこの間に給料が数倍になった国もあることからその意味では物価の上昇はちょっとコラえたいところでもある。ただし、只今の価格上昇は給料上昇を伴わない、経済用語でいうところのスタグフレーションの色彩が色濃いので果たして給料のベースアップの流れにつながるかはまだ見通せないところではあるのだが。
行動経済学を知る意義
さて、今回は行動経済学について取り上げるのだが、これは心理学と経済学の境界線に位置する学問領域であることは、先回、紹介した通りである。書店に行けば、もはや経済学分野の新書といえばミクロ経済学やマクロ経済学よりも行動経済学に関するものが多い印象で、皆さんも相応に認知されている学問領域にも思える。故に本コラムでどこまで取り上げるのが適切なのかは悩ましい。
そこでコラムルール(?)としては、「行動経済学にこれまで触れたことのない一方、医学や薬学、ヘルスケア分野には明るい人」を勝手に想定することにした(該当していない方には平にご容赦願いたい)。例えば健康関連行動としてダイエットや禁煙がどうして続かないのか、定期検査の受診率を増やすためにはどうしたらいいのかといった課題に対する“処方箋”はむしろ医学や疫学よりも行動経済学の専門スキルを使う方が合理的だ。また、“逆輸入”ということでも無いのだが、医学系の研究分野では常識でもあるプラセボ効果は必ずしもニセ薬に限定されることなく、認知バイアスの代表の一つとして行動経済学分野でも活躍している。
また、医療現場やヘルスケア課題に限定することなく、冒頭のような「日常の一コマ」にしばしば役立つこと請け合いでもある。例えば「以前は399円だったのに、」という心理作用は行動経済学では参照点依存性という認知バイアスとして整理される。元の価格は幾らだったのか、という意識が不適切・非合理なまでに強く認識されてしまい、合理的でない決断を促してしまうというわけだ。この参照点依存性を踏まえるならば、店頭に並ぶ値段札でよくみられる元の価格とその取り消し線を併記した「2000円→1000円」という店側の策略にも先回りして気づくことが出来る(=売り手の“ワナ”には掛かりにくくなる)。
認知バイアスの定量化
行動経済学の出発点となる重要な概念が、私たち人類の合理性のブレ、限定合理性である。従来の経済学は人の行動が常に合理的に決定されるという前提で構築されてきたが、行動経済学ではこのようなアリエナイ生き物のことを実際の人類とは別モノとして、ホモ・エコノミカス(合理的経済人)と表現した。実際のヒューマンはこれと違う生き物であり、合理的行動をとるのは限定的ということだ。
無論、従来の経済学者らが「人は常に合理的行動をする」と思い違いをしていたわけではない。とはいえ人間らしいブレは学問として容易に許容できるものでもないのである。例えば算数の問題で「まさお君が池の周りを毎分100mで歩いていると、(後略)」という設定を私たちは幾度も目にしているところだが、「まさお君は人間じゃないね。常に同じ速度で歩けるような人は存在しないのだから。」なんて指摘をしたら先生に叱られるだけだろう。然るに「前提として人間が常に合理的な判断、行動をとると仮定して」経済学は体系化され、人間らしさに基づくブレは“誤差”として片づけられてきたというわけである。
ここで“誤差”について整理してみよう。誤差には無作為性の誤差と、傾向性を伴う系統誤差とがある。簡単に言えば前者は「バラツキ」、後者は「バイアス」と表現してよいだろう。人間のブレは経済行動にあってやはり誤差ではあるのだが、旧来の経済学がこれをバラツキとしたのに対して、行動経済学はバイアスとして捉え、しかもその定量化に成功したのである。
いうなればこれこそが行動経済学のパーパス(存在意義)であり、「認知バイアスの定量化の学問」と言い換えても良いかもしれない。一方でマーケティングの権威コトラーは「行動経済学はマーケティングの別称にすぎない」としている。コトラーの主張を無批判に受け取るならば、逆説的にはマーケティングに関するスキルを身に着けようとするとき、その学びは行動経済学分野のお勉強をしているということでもあるわけだ。
また一方で前述した「参照点依存性」などは純正なる心理学分野として十分に研究に値するテーマでもあり、このようにして玉ねぎの皮むきをするならば行動経済学は消えてなくなる心配さえある。しかしながら先回とりあげたように学問領域の境界というのは人間のご都合主義が線引きするのであって、現時点においては独立させ行動経済学と呼称するのが便利である、ということになるのだろう。
プロスペクト理論
行動経済学の心臓部、中心に位置するのがプロスペクト理論である。日々のショッピングやモノの売り買いといった経済行動の中で、実際の金額のプラスマイナスと、人間の非合理性に基づく感覚的に感じるプラスマイナスとは揺らぎがあり、これをX(実際)とY(心理)の座標軸で表したものだ。(Fig参照)。

仮にもし私たちがホモ・エコノミカス、常に合理的な意思決定が出来る生き物であったならば、1万円の損失には1万円分の損失感、1万円の儲けには1万円分の得失感を感じ取れることになるので、座標軸は1本の右肩上がりの直線Y=Xを描くはずであり、この直線には何ら価値がない。言うなれば既存の経済学はこれを常としてきたことになる。
ところがそうはいかない。具体的な例で実際と心理との間に金額的開きがどのように生じるかみてみよう。まずは「損失回避性」だ。
プロスペクト理論(1)損失回避性
仮にコインを投げて裏なら0円、表なら1万円が貰えるゲームがあったとしたら、あなたはこのゲームの参加費に幾らまでお金を出せるだろうか。100円で参加できるとしたら絶賛参加希望者は溢れるだろう。1000円でもキャンセルする人は少なそうだ。では参加費3000円となればどうだろう。あるいは4000円ではどうか。
期待値という概念を熟知している人ならばこのゲームの価値が期待値として5000円であることはすぐに理解できるはずであり、そうであるならば参加費が5000円を越えなければ検討の余地はある。しかしながら医薬品の効き目や副作用と同じように個々人で答えは一致しないだろう。それには心理面が多いに影響を及ぼしている。
私たち日本人はアメリカ人からはあまりのノーリスク主義に驚かれるようである。基本的に貯金をしないというアメリカ人にとって株式等の変動制金融商品への投資は当たり前であるが、日本人は「元本保証」という響きに弱く、どうにも元本が保証されない投資には躊躇する人が多い。これもまた損失回避性と言えるだろう。
少し気に留めておきたいのが日本人とアメリカ人との国民性の違いである。医薬品の効き目がときとして人種によって異なるように、損失回避性は国民性、文化慣習によってその開きが異なるだろうことは想像に難くない。ここから転じて行動経済学一般に研究結果の再現性に問題があるという論調もあるのだが、この話はまたの機会としよう。
プロスペクト理論(2)感応度逓減性
知り合いから5000円のホテルビュッフェランチをゴチになるという機会を得たらきっと嬉しいはずだ。ところが今度は別の知り合いからたまたま翌日にまた5000円のランチをゴチになる機会を得たとしたら、同じだけ喜べるだろうか。あるいはそのランチが3000円だったら、どのような心の動きがあるだろうか。

私たちはどんなに贅沢な食事であったとしても、それが翌日も続いたときは前日ほどには嬉しくないハズだ。経済的にいえば金額的価値は同一であったとしても翌日の心理的価値は減弱する。こうした価値(経済用語でいう効用)が頭打ちとなることを感応度逓減(ていげん)性という。
プロスペクト理論(3)参照点依存性
ご馳走してもらったビュッフェと、5000円の自腹を払ったビュッフェで行動が変わるということはないだろうか。プロスペクト理論の応用として、人からのゴチと比べて自腹のときはハッキリと「5000円」が意識されることから、モトをとらねばとひょっとしたら食べ過ぎる恐れが前者よりも高まる可能性がある。
この場合の5000円が行動経済学でいうところの参照点であり、不必要に非合理な出費5000円への意識は参照点依存性という。合理的に考えればご馳走してもらおうが自腹だろうが好きなものをとって食べるのがいいハズだが、なんだかそうもいかない。冒頭のチャンポンの場合は399円が参照点であり、値札の例であれば2000円が参照点となる。参照点というのはこのようにときと場合によって変化する。図でしめされたX軸とY軸が交差するところは数学で習った0では必ずしもないことに留意が必要である。
プロスペクト理論(4)さまざまな“派生”
期せずして人からおごってもらうとか、拾ったとか、当たったといったように労なくして得られる5000円と、汗水たらして稼いだ5000円とでは私たちは異なる価値を感じるらしい。日本でも古くから「あぶく銭」という言葉があるが、行動経済学でいうところの「ハウスマネー」は「あぶく銭」と日本語訳しても良さそうな概念である。
このようにしてプロスペクト理論を契機とした、心理と実際の価値の差が行動経済学では様々に提案され、様々に確認検証の研究が実施されている。また、前述したように日本とアメリカといったように文化の違いがあっても同様な結果になるのかといった検証も盛んだ。
その他、現状維持バイアスであったり保有効果であったりと、人の摩訶不思議なお金に対する認知のゆがみ、バイアスがこのプロスペクト理論から現在も色々と派生し続けている。また、当該の認知のゆがみはメンタルアカウンティング(心理的会計)という用語で整理されることになった。
山盛りフライドポテト
高額なビュッフェだというのに、フライドポテトを山盛りにとってきて嬉しそうな顔をしている子供を見かけると、内心、「まだ子供だな」と感じてしまうのは私だけでは無いだろう。それでは到底、モトはとれまい。
資本主義に毒されている私は、食べ放題なるサービスに身を置くと反射的に「高額な料理はどれだろう」という思考が勝手に発動してしまう。アワビやサザエ、カニなど、果たして今、自分がそれを食べたいのかどうかはおかまいなしに“金目のモノ”をまずは物色してしまう。これが大人というものだ。フライドポテトのようないつでも手に入るものでお腹を満たしたのでは勿体ない。
私たちの周りに空気のように当たり前に存在する資本主義。資本主義が無ければ経済学など誕生しなかったろう。しかしながら、経済学が教えるところの合理的行動というのは本来「人は効用(価値、幸福)が最大化するように行動する」らしい。では果たして効用の最大化行動をしているのはこの場合、私なのだろうか、それとも子供なのだろうか。
このように再考すると世界が違って見えてくる。山盛りのフライドポテトをとってくる子供の方が合理的なのだ。モトがいくらだろうが、誰かにおごってもらおうが、自腹だろうが、ビュッフェなら好きなものを好きなだけ食べるのが正解。それが出来ない私は悲しいかな、資本主義のしもべなのである。トホホ。
第28回おわり。第29回につづく