第17回:クスリの経済学
- Erwin Brunio
- 2022年1月27日
- 読了時間: 10分
更新日:2022年2月15日
2022年1月31日
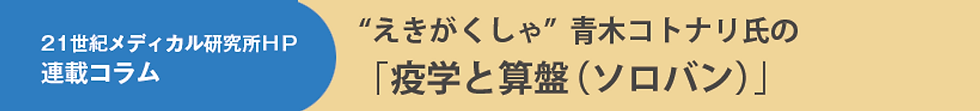

“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第17回:クスリの経済学
お年玉
2年ぶりに実家の新潟市で過ごした正月は雪景色であった。東京の放送局で報道される全国の天気予報では、冬場の新潟県といえばほぼ雪マークなので大いに誤解されているものと思うのだが、新潟県といっても山間部ではないところは年末年始に積雪していないことの方が多い。その意味でも実家の庭に積雪を見られたのは10年に1回ほどの珍しいことであった。珍しいついでに、親戚が5歳の娘さんを連れてくるというので、こちらは私にとっては初めてのご対面ということでワクワク、ソワソワしつつも慌ててお年玉の準備を元日からバタバタとすることになった。さて、5歳の子供だと幾らが相場なのだろう-。まだ貨幣価値を知らないものだと思って紙よりはコインが良かろうと500円玉を入れたお年玉袋を渡したのだが、果たして正解だっただろうか。

今回はクスリの経済学について取り上げてみたい。ご存じの通り、数年前に発売された抗がん剤が1年間の治療で3500万円もする、ということで一気に注目を浴びた“社会課題”が「クスリの価格(薬価)」である。一体それはどのような手続きで、どのようなロジックで決定されているものだろうか。恐らく、製薬業界に在籍でもしていなければ、この3500万円/年という価格の何たるかは全くわからないことだろうと思う。もちろん、価格を決定することに他分野の商品やサービスとは違いがないのだが、作った側の製薬企業が勝手に決めてはいけない、公定価格であることは(ご存知のことかと思うが)大いなる特徴だろう。
とは言っても本気で合理的な価格を決めようとすると、これは至難の業である。基本的なロジックはあるにせよ、度々その価格が改訂されている様子からみれば、お年玉袋とは言えないまでも、ある程度は「エイヤ!」で決めざるを得ないようにも思える。薬価算定の学問領域は「医療経済学」分野の一部であり、これは疫学とも関わる。何せタイトルを「疫学と算盤」とした以上、これを取り上げておかなければ、先回同様、渋沢栄一先生に怒られそうである。
価格の原理(プライシング・セオリー)
クスリの価格が何たるかを考える前に、そもそも「モノの価格ってどうやって決まるの?」という一般論を整理しておきたい。そうすることで薬価の合理性は(それがたとえ公定価格であるにせよ)どのようなものであり、一方で一般のモノやサービスとはどのような違いがあるのかが理解しやすくなるだろう。
さて、経済学部に進学した学生は「マクロ経済学を専攻するか、それともミクロ経済学を専攻するか」という岐路に立たされるのがお決まりのようである(新たに行動経済学といった選択肢も増えているようだが)。このミクロ経済学というのが別名、価格の原理学、プライシング・セオリーとも呼称される。
ミクロ経済学と認識したうえで勉強していたかどうかはともかく、私たちの学生時代の記憶を辿ってみると、当該の商品ないしはサービスを欲しがる人たちの需要と、それを提供する側の供給との混じり合ったところが「価格」といった説明を思い出すだろう。経済学の創始者とも言われるアダム・スミスは、価格の決定アルゴリズムについて、「神の見えざる手」と呼んだ。市場原理の中で放置しておけば自ずと妥当な価格に落ち着く、それは神様が見えない手であたかもその妥当な価格に誘うがごときであるとしている。こうした市場原理については、今でも確かに“落ち着くところに落ち着く”様子は私たちの肌感覚にもあるだろう。
一方でアダム・スミスが整理したところの商品の価値については、彼の生きていた当時とは様相が少し異なる。当時、「その生産に必要な労働量によって決定される(労働価値説)」、つまり労働力のコストがどれだけ掛かっただろうかということで価格を決めることが主流であったという。今ではむしろどれだけの労苦、労働力が掛かったかどうかではなく、消費する側の満足度(効用)によって決定される方にシフトしている。前者の労働価値説に対して現代のこの概念は効用価値説と呼称される。
もちろん、労働価値説が完全に否定されたという訳では無く、モノやサービスによっては今でも利用されるロジックである。現代において、一般的に整理されている価格の算定方式
は主に下記の3つと言えそうである。
(1) 原価を考慮する算定方式
・コストプラス価格
・マークアップ価格
(2) 需要を考慮する算定方式
・知覚価値価格
・需要差別価格
(3) 競合相手を考慮する算定方式
アダム・スミスの時代で主流であった労働価値説は、原価に利益を足し算して算定する方式、一方、効用価値説は顧客のニーズに合わせる算定方式として整理されるだろう。
なお、こうした価格原理の原則となっているのは、いわゆるノーマルな競争市場を想定したものであり、供給側がわずか1社だけ、あるいは数社だけといった市場では供給側による裁量が巨大化してしまう。これを独占市場、寡占市場というが、こうなってくるとアダム・スミスが唱えた「神の見えざる手」は本当に見えなくなってしまい、神様がどこにいるのか、随分と高い価格でふっかけられてしまう。現代においてはこうした独占、寡占は法に反することとされ、ヒトによる“介入”策がとられることになる。その他、価格算定の代表選手からは漏れるが、セリ市で決定される価格など価格算定のロジックは他にもある。
薬価の算定
競争市場、そして一般での価格の算定原理を概観したが、先にも述べた通り薬価の算定は自由競争市場ではなく、国の所轄にてこれを算出する公定価格である。その価格が決定するまでの大まかな流れをいえば、市場が“神の手”でこれを決めることでは全くない。
まずは当該の医薬品を製造販売しようとする者が薬価基準収載希望書を薬価算定組織に提出する。これを中央社会保険医療協議会、俗に言う“中医協(ちゅういきょう)”がOKを出せば薬価は確定となる。製薬企業にとってこの協議会の議論は戦々恐々たるものとなる。もちろん、提出側がいい加減な価格で提出するということはなく、そこには前述したような価格算定の原理等を駆使して提出するのだが、その採択を判定する側も喧々諤々(けんけんがくがく)の議論が成されることが常である。

いくつかの決めごとがあり、先に述べたように仮に似た医薬品が市場にあるならば、それと同価格とすること(類似薬比較方式)、類似薬が無い場合には基本に立ち返って原価計算方式や、海外で類似薬があるならばこれを参考にするなどで価格が決まることになる。
ご存じの方も多いと思われるが、医療費のひっ迫は国家の大きな課題であり、こうしたことからこれまで2年に1回であった薬価の見直し、改定は毎年実施されることとなった。「見直し」なのであるから、本来的には上振れも下振れも半々くらいあってもよさそうなところではあるが、医療費のひっ迫を背景として「見直し=薬価引き下げ」の方程式がほぼ意識されており、これによって製薬産業のモチベーション、つまり新薬を開発し世に出そうという「やる気スイッチ」に悪い影響がないかどうか懸念もされている。
こうしたことから、薬価の算定には「やる気スイッチ」も意識され、それは補正加算という形で通常価格に上乗せされる。具体的にはその画期性、有用性、市場性(希少疾病等、ほとんど患者さんのいない疾患に対する治療薬)、小児、先駆け審査指定制度対象(他国に先駆けて審査されるほどの魅力)を評価、賞賛する仕組みといえるだろう。
一方で、後発医薬品(ジェネリック医薬品)については先発医薬品の0.5倍価格、バイオ医薬品の後発医薬品にあたるバイオシミラー(製法からすれば完全な同一品にならないため、シミラー<類似の>と呼称する)には先発医薬品の0.7倍価格などが設定され、先発医薬品の特許切れのタイミングにて医療費高騰を防ぐための政策の一助としている。
高額な医薬品の登場
さて、最近ではめっきり報道されなくなった高額な医薬品の話に戻ろう。年間の処方費用の合計が3500万円という抗がん剤の課題は既に解決済みなのかといえば全くそうではない。その後に次々と高額な医薬品は登場してきており、年額ではなく1回の投与で3000万円の医薬品も登場し、最高価格の医薬品となると2億3300万円である。仮に保険制度でサポート出来なかったとしたら、とても一家族で払える金額では無い。つまり報道されなくなったとはいえ問題が解消したのではなく、むしろ以前よりも問題は大きくなっているのである。
ではどうしてこのように高額な価格が公的価格として認められるのだろうか。そこにはいくつかの理由がある。
【医薬品の価格が高騰化する主な理由】
(1) 製法がそもそも複雑で高コスト
(2) 画期的な新薬が世に出てくるまでに数千億円レベルの開発費用が掛かりがち
(3) 患者さんが少ない
(4) 効き目が凄い(命を100年も延ばす可能性等)
例えば、前述した2億3300万円の医薬品の適応症である脊髄性筋萎縮症(Spinal Muscular Atrophy: SMA)は遺伝性の疾患であり、これまで有効な治療法はなく、ほとんど生後2年も生きられない病気である。日本では指定難病であり全国でみても患者さんは数百人レベルという*。これを治すというのだから、むしろ“高額医療問題”とするのではなく、人類の英知が結集した奇跡の発明という見方をする方が正当にも思える。経済妥当性の視点からいえばこうした奇跡の発明に関して開発しようという動機を決して失わせてはならず、当該医薬品を黒字化するうえでの価格算定からみてもどうしても高額にならざるを得ないという事情がある。
かといって、では「誰がそのコストを払うのか」という現実問題がある。よく知られる「患者さんは費用の3割を負担」という負担軽減策でも支払える財力のある人は多くないだろう。高額医療制度なる制度はこうしたケースをサポートするものであり、患者さんが実際に支払う金額は、ほぼ無料か少額となる(桁は違うが私もこの制度の恩恵にあずかったことがある)。このようにして、「少なくともここ日本において、患者さん当人や家族にだけその負担を負わせるわけにはいかない」という文化、規制に異論のある人は少ないだろう。要するに国費、私たちの国民全員の出資にてこれを賄っているわけで、今後こうした高額な医薬品が次々と市場に登場することは、治療選択肢のない疾患への希望という美しい側面だけを見ていればよいというわけにはいかないのである。
国民皆保険制度のピンチ
科学技術はこれからますます進展し、遺伝子レベルで私たちにピッタリの医薬品がこれ
から続々と開発され世に出てくるだろうことが予想される。以前であれば1万人中2000人に効いた(有効率20%)、という、1万人に処方される薬ではなく、2000人中2000人に効いた(有効率100%)なんていう世界もまんざら夢の世界ではないかもしれない。
しかしながらその一方で、“では薬価をどう算定するのか”といえば、1万人が“顧客”だった時代が過ぎてその“顧客”が5分の1に減るならば、価格は5倍にしないと同じ稼ぎ、商売は成立しないことになる。これが市場原理だ。加えて「人の命」をどう算段するのか、先に述べた不治の病を治す薬を開発したその偉大さをどう評価するのか、そしてそのお金を誰が出すのか。私たち日本では皆保険制度がまるで空気のように当たり前に存在しており、少なくとも健常な人はこうした薬価の問題を自分事としてとらえることは難しいところがあるだろう。
現場の医師らも、通常ならば50円の既存薬で済むところを新発売の250円する薬を「何となく」処方したりする、という話も聞こえてくる。患者がそれを高額すぎると文句をいうことなど考えにくいことでもあり、これは私たちが薬価の3割負担、つまり常に70%オフであることも一因といえるだろう。問題が複雑なため「こうすると良いのでは」とここで論じることは到底出来そうにないが、私たち一人ひとりが薬価の問題を自分事として考えてみることは問題解決への大切な態度になることだろう。
医療の恩恵
先に述べた通り、私は以前、高額医療制度の恩恵を受けたことがある。あまりハッキリと記憶してはいないのだが、確か総額50万円を超えた治療費のほとんどを支払わずに済んだ。その意味で何よりその出資となる税金を支払ってくださった国民全員に感謝しなければならないだろう。

と、このようなコラムを執筆の途中、不覚にもまた入院することとなってしまい、病室で執筆中である。無料の病室も選べなくなかったようだが、コロナ蔓延の折にあっては実際上、好むと好まざるに関わらず1日プラス7700円の病室を選んで欲しいというニュアンスであったため快諾した。これは勿論、自腹で払う予定である(←だからって何??)。
*ノバルティス社サイトより https://www.novartis.co.jp/news/media-releases/prkk20200520
第17回おわり。第18回につづく




