第23回:科学の手続き
- Erwin Brunio
- 2022年7月26日
- 読了時間: 10分
更新日:2022年8月29日
2022年7月26日
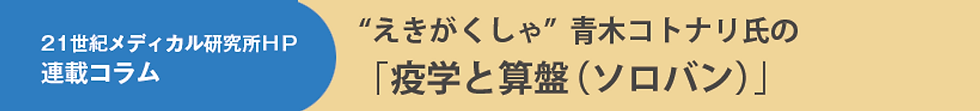
2020年10月20日から、3週間に1回、大手製薬企業勤務で“えきがくしゃ”の青木コトナリ氏による連載コラム「疫学と算盤(ソロバン)」がスタートしました。
日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボWEBサイトに連載し好評を博した連載コラム「医療DATAコト始め」の続編です。「疫学と算盤」、言い換えれば、「疫学」と「経済」または「医療経済」との間にどのような相関があるのか、「疫学」は「経済」や「暮らし」にどのような影響を与えうるのか。疫学は果たして役に立っているのか。“えきがくしゃ”青木コトナリ氏のユニークな視点から展開される新コラムです。
(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)
“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第23回:科学の手続き
科学的なもの
子供の頃、科学的なものといったらそれはロボットであった。鉄腕アトムや鉄人28号の世代より私は少し若いのだが、マジンガーZ、ゲッターロボ、鋼鉄ジーク、ライディーンと、テレビに夢中になってかじりついて見ていたアニメには、よくロボットが登場していた。もちろん、宇宙船やロケットなども科学の象徴ではあったのだが、やはりアニメによる影響力は大きく、科学といえばロボット、イコールのような存在でもあったように思う。
アニメはもはや子供だましだとバカにするものではないだろう。機動戦士ガンダムの人気は未だ衰えることを知らず、“ガンプラ(ガンダムのプラモデル)”は大きなマーケットを形成しているし、人気アニメの舞台となった場所は“聖地巡礼”として多くの人が訪れ地域活性化に貢献している。以前は「オタク」と批判的に揶揄されていたアニメ文化は、今では日本の魅力を発信するうえで欠かせないものとなった。
また、日本でロボット工学が発展したのは“科学の子”鉄腕アトムの影響が大きいという論説も耳にする。他国では人類を脅かす破壊兵器、敵のように描写されることが多く、それがロボット工学に対する生理的な嫌悪につながった一方で、日本ではロボットの存在はアトムのように友好的であったからだといった考察である。これが事実なのかどうかは証明のしようもないが、ロボット犬アイボやペッパーが他国に先駆けて商品化されたのは確かであり、あながち間違った考察ともいえまい。

ところがいつの間にか「科学的」といえばもっぱら論理的であるとか、合理的であるとか、概念的な使われ方に変わってしまったようだ。これは時代のせいなのか、あるいは単に私が大人になっただけであって、未だに子供にとっての科学的なものといったらロボットなのかどうかはよくわからない。今回とりあげる「科学の手続き」は残念ながら友好的なロボットのお話ではなく、その概念的な、理屈っぽいお話の方である。
論理学
「ポチは犬である。犬は動物である。ゆえにポチは動物である。」
こんなお話の何が楽しいのか。確かに概念的なお話は退屈で、やはりマジンガーZの方が楽しそうではある。「犬は動物である。動物でなければ犬ではない」。これは対偶と言われるもので、記号化すると「P⇒Q」ならば「Qでない⇒Pでない」が対偶であり、もし「P⇒Q」が真ならば対偶も真となる。確かに心躍るような話ではない。
こうした論理学は数学の一部として学校教育に取り入れられてはいるものの、戦前の日本ではそもそも論理学は存在しなかったようで、アメリカはこれに驚いたとも聞く。更には学校教育の中で「漢字を覚える」ことに費やす時間が多すぎることを問題視し、当時は漢字を前面廃止し、その代わりとして論理学の教育時間を増やすべきという論調もあったそうである。実際のところ、この動きの中で常用漢字という概念が登場し、何割かの漢字は学校教育の“レギュラー”から外されたようだが、一方でその代わりに論理学が市民権を得たとはちょっと思えない。
未だに日本のムラ社会では“理屈っぽい人”はさげすまれる傾向があり、例えば「理系の人は冷たい人だ」とか、論理的に合理的に丁寧に繰り返して理解してもらおうと頑張っても「話が長い」だとか、「しつこい」だとか言われてしまいかねない。私自身も論理学的(=科学的)でありたいという強い信念がある一方で、それはときと場合によってさげすまれる危険性を肌で感じるため、日常の中では科学的な態度をひた隠しにして生きている。
かくして、その論理学に対する日本の“生理的”否定論は、科学的でありたいとする「疫学と算盤」の世界観にも影を落とすことになる。例えばワクチン接種に関しての疫学調査として日本ではただひたすらに副反応症例を集め続けるというアプローチがとられたりするのだが、どんなに副反応症例を集めたところで結局のところそのワクチン接種とワクチン非接種との比較にもつながるはずもない。論理的な合理性がないのである。結果として副反応情報の累積は、国としてのワクチン接種の推奨を取り下げたり、副反応が生じた人から訴訟を起こされたりといったネガティブな帰結以外に使い道がない。本コラムでもしばしば取り上げてきた“効く”ことの証明や薬価・治療の価格妥当性などは、処方・接種情報に加え非接種群との比較ができてこそ科学的に合理性のある判断が出来るはずである。医療情報の利活用において日本が後進国となったのは、こうした論理学の国民全体への普及が不十分であることも一因なのではないだろうか。
思いつき→科学の手続き
さて、思いつきを科学として証明したり科学の法則に昇華する手続きとは、具体的にどのようなものなのだろうか。ニュートンはリンゴが木から落ちるのをみて「地面がリンゴを引きつける引力があるのではないか」とした逸話が有名であるが、この思いついた段階ではまだ科学とは言えないだろう。あるいは疫学的な整理をすれば、これは「仮説の生成」段階であって、科学の手続きの第一歩ともいえるかも知れないのだが、その後に続く“証明”する手続きとセットになってこそ「科学の手続き」といえる。
生物学・生理学・薬理学の世界にあっては「自然に生物がわき出ることはない」ことが証明されているが、これはパスツールによるフラスコ実験の成果である。当時は「(何もないところから)自然に生物がわき出てくることがある」説が否定されておらず、パスツールによる白鳥の首フラスコ(白鳥のようにくねくねと長い首のフラスコ)を使った実験がその説の息の根を止めたのである。無菌状態を確保された肉汁からは決して自然発生として微生物がわき出てきて肉汁が腐ることはない。日本語でいうところの「ウジがわく」ような現象は発生し得ない。仮に腐る(=微生物の発生)現象が発生したとしたら、その微生物はどこかからやってくる以外には有り得ないことが論理合理的な実験によって証明されたのである。
前回のコラムでは「幸せの測量」の難しさを取り上げたが、こうした私たちの主観に関わる学問領域の代表選手である心理学も、その創世記は科学とは言えないものであった。確かに心理学の仮説はフラスコ実験では証明できそうにもなく、科学としては苦手科目といえそうだ。例えばフロイトによる夢分析、「願望や欲求が別の形で実現したものが夢である」はあくまで仮説でしかなく、これは「リンゴが地面に引っ張られている」という“思いつき”(=仮説生成)と同じ段階である。故に現代科学の文脈からすれば、この仮説が実際にその通りであるという科学の手続きがなされなければこれが真理なのか、はたまた気のせいだとか妄想だとかとの区別は出来ない。そんな中で心理学に科学の手続きを導入したのはドイツの生理学者ウェーバーであり、物理学者フェヒナーである。この流れを受け、心理学の仮説を思いつきやひらめきで終わらせないための科学実験を履行する場として「心理学実験室」を創設したヴントは、心理学の父と呼ばれている。
心理学分野での「科学の手続き」
では心理学分野という “苦手科目”における「科学の手続き」というのは、どのようなものなのか。前回「幸せの測量」で取り上げたところの幸せランキングに、肝心カナメともいえる“感情”がどうして指標として採用されていないのか、その根拠となっているところの「私たちは実際の経験を正しく記憶出来ない」という仮説がどのような手続きによって証明されたのか紹介しよう。
下記の “罰ゲーム”について、どちらかを必ず受けなければならないとしたらどちらを選ぶだろうか。
(A)14℃の冷水に60秒、片手を浸す。終了後、暖かいタオルを渡す。
(B)14℃の冷水に60秒片手を浸した後で、バルブを開き約15℃に水温を上げてさらに30秒、トータル90秒、冷水に片手を浸す。終了後、暖かいタオルを渡す。
14℃の冷水は耐えられないほどに冷たくはないが、苦痛ではある。少し暖かいお湯を混ぜた15℃の冷水も暖かいお湯というわけではなく基本的にはやはり苦痛ではある。このため理屈からいえば60秒で済む(A)の方が90秒の(B)よりはマシということになりそうなのだが、実際には実験に参加した人の8割は(B)の方がマシであったと回答したという。

この研究結果は大抵の人が「経験した秒数の累積苦痛」と、「記憶された嫌な感情の累積」と一致しないことを指し示している。また、これと同じ仮説を検証するために実施された研究はこの冷水実験だけではなく、様々なデザインでの心理学実験が繰り返し行われている。経験している最中と、その経験が終了したときの記憶とのこうした乖離があるため、幸福度ランキングから短期的な感情の指標が外されたという訳なのである。
なお、冷水実験のデザインは適切な科学の手続きに則って行われている。まずは仮説として「終わりよければ全てよし」、つまり実際には90秒間の苦痛であっても、そのフェードアウトの仕方として多少なりとも苦痛が緩和されるならば最後の印象が心理的なバイアスとなって好印象を与えるだろうという想定(=思いつき)が出発点である。被験者には「それぞれ3回ずつ行う」と伝えつつ、実際には2回ずつしか行わないことで「これで罰ゲームは最後だ」という“幸福感のバイアス”が入り込まないように工夫が凝らされている。更には(A)→(B)の順序とする群、(B)→(A)とする群、そして右手の次に左手、あるいは左手の次に右手といったように主たる目的、つまり(A)と(B)とではどちらがマシか以外のノイズが決して入り込まないようにデザインされている。
この研究は心理学の大家、ダニエル・カーネマンらによって行われたものである。大腸内視鏡のようなツライ検査においても、検査終了に向けては最もツライ状況からすぐに検査機器を抜くのではなく、たとえ検査時間が2倍になったとしてもゆっくりゆっくりと外すようにした方が被験者は“記憶”としてそんなにツラくは無かったとなることもカーネマンらの研究によって確かめられている。
私たちはどうやらその一連の出来事に際しては何分、何時間継続されたかをよく記憶することが出来ず、記憶に残るのはせいぜいその中でのピーク時とフェードアウト時らしく、この“記憶のバイアス(ゆがみ)”は心理学分野ではピーク・エンドの法則と呼ばれている。適切な科学の手続きに則った研究が、様々なデザイン、様々な文化慣習の中でも繰り返し確認され、その積み重ねによって単なる思い込み、妄想なのではなく普遍性をもった「法則」として周知され、ときにはこのようにして法則として命名までされるのである。
ペッパー君は今どこに?
ところで、以前は色んなところで見かけたロボット、ペッパー君がこのところは全く見かけることが無くなくなった。実はペッパー君のコンセプトには「戦争を防ぐ」といったコンセプトがあり、人間の平均レベルより高い道徳観に基づく感情機能が埋め込まれているスグレモノである。しかしながら私の知るところではこうした機能を上手に生かした使い方をしているところはあまり見かけることが出来ず、寂しい限りである(モスクワに送りたい?)。

家族に聞いた話ではロボット犬のアイボが、マンションの「燃えないゴミ」に入れられていたそうで、ひょっとしてペッパー君もそのような憂き目にあっているのだろうか。ペッパー君は「悲しむ」感情機能を持ち合わせているので心配だ。そんな話をレストランでしていたら何だか巨大なロボットが私たちの食事を運んできてくれた。もしかしたらこの中にペッパー君が入っているのかな、と、有りもしないことを妄想しながら、ペッパー君たちが捨てられることなく今でも幸せに暮らしていることを願っている。
第23回おわり。第24回につづく




