第10回:プラセボ効果に思う
- Erwin Brunio
- 2021年10月14日
- 読了時間: 11分
更新日:2023年12月4日
2021年7月25日
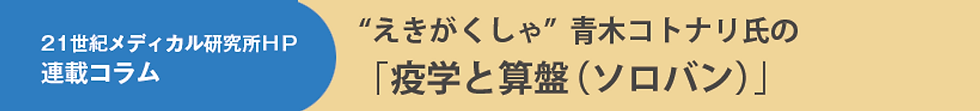

“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第10回:プラセボ効果に思う
思い込み
JR高輪ゲートウェイ駅に併設しているカフェで”コーヒーブレイク”をしていると、失礼ながらこの駅に何の用があるのだろうかというくらいに混雑をしている。かくいう私も特段この駅に用があったわけではなく降り立ったのはここから程近い都営浅草線泉岳寺駅である。赤穂浪士で有名な泉岳寺を見学したついでに立ち寄ったという事情なのであるが、カフェの窓から見える開発途上の何も無い景色が案外と心地よくもある。
この「高輪ゲートウェイ」という駅の命名については反対運動が激しかったことは記憶に新しい。どのような駅名がよいかわざわざアンケートまでとったにも関わらず、その第1位である「高輪」ではなく、132位というこの駅名が採用された理由はよくわからない。ただ、確かにシンプルな「高輪」という駅名にしてしまうのは相応しくないとも思えるのは、実はJR品川駅のある場所こそが港区高輪であり、高輪という駅名にするならばむしろ品川駅の方が相応しいだろうという事情が影響していたのかもしれない。そもそも品川駅が品川区ではなく港区にあるということはどれくらいの人がご存じだろうか。東京ディズニーランドが東京都ではなく千葉県にあることはよく知られた話だが、品川駅が品川区にあると思い込んでいる人は少なくないだろう。
こんな風にして私たちはよく思い違いをする。赤穂浪士についてもその言い伝えられている史実を辿れば、一般に言われているような「仇討ち」というのは少しおかしいだろう。松の廊下で吉良上野介を背後から斬りかかったのは彼らの主君なのであり、その主君は吉良氏によって殺害されたわけではない。吉良、浅野内匠頭、赤穂浪士・・・。何が正義で何が悪なのかという私たちの受け止め方は実際の出来事の解釈の仕方によって様々であり、解釈=事実、という方程式が成立しないこともしばしば起きる。また、そのすれ違う思い込みが社会の分断を招いたりもするのである。

さて、先回は「臨床試験という発明」のお話の途中で “コーヒーブレイク”としたところであった。臨床試験なる方法論を形成する概念や留意事項は数あれど、その中核をなすものは何かといえば、私は大きく3つの構成要素でとらえている。その3つとは、(1)倫理:ヘルシンキ宣言に象徴されるヒトの権利、(2)統計学:「あわて者の誤り」と「ぼんやり者の誤り」の折り合い、(3)盲検化:今回扱うところのヒトの思い込みを克服するというバイアスの制御、である。たかが思い込みと言うなかれ、それは私たちの想像する以上に奥深く、現代の臨床試験がそれとして成立するうえで倫理や統計学上の揺らぎと同様に、乗り越えなければならない大きな壁である。
プラセボ効果の“発見”
日本語でプラセボまたはプラシーボと表記されるplaceboなる用語は、元々ラテン語で「喜ばせる」「満足させる」という意味をもつ。以前コラムでもふれた江戸時代の医師の仕事などというのは、その当時はマトモに治療に貢献できる医薬品が無かったことから察するに言わば患者を”placeboさせる”ことが生業だったと言えるのかもしれない。
「プラセボ効果」については様々な研究がされているのだが、実際のところプラセボ効果が最もよく発揮されるのは信頼出来る医師が処方したときであって、信頼されていない人が処方したのではプラセボ効果が見えないどころかむしろ実際には有効な医薬品であっても効かないということさえあるらしい。
こうした効果が世に知られるようになったのは1955年にハーバード大学麻酔科医のヘンリー・ビーチャー博士による「The Powerful Placebo(強力なプラセボ)」とタイトルされた論文とされている。そこでの博士の研究結果ではニセ薬を処方した群であっても3人に1人の割合で効果が得られるという、その当時では恐らく容易には受け止めがたい数字であった。ニセ薬で病気を治すことが出来る-。かくして今ではプラセボといえばこれすなわち偽薬、ニセ薬のことを指すようになったのである。
医薬品として認可してよいかどうかを判断する最終テスト、臨床試験の目的を考えたときに、ニセ薬であっても3人に1人の割合で効果がみられるということがいかに都合の悪いことなのかは想像に難くないだろう。ニセ薬というのは固形物ならばパンくずであったり、液体ならば生理食塩水に色を付けたものだったりと、まさに本来は当該の病気を治せるなどという期待が0%と思われるものである。こうしたニセ薬で33%も効くならば、実際の医薬品候補において例えば2人に1人が効いたという結果を受け本当に「有効率50%」といえるのかどうかという話になる。
少し数学的に整理してみよう。有効率50%ということは30人いたならばこのうち15人が有効ということだ。一方、プラセボ効果が3人に1人ということは30人中、10人に「効いた」という“思い込み”が生じるので、では被験者30人に対して「有効率50%」を達成した医薬品候補の真なる効き目はどれ程かといえば15人の有効例のうち10人が“思い込み”なのであるから、残りの5人、つまり30人のうち5人(17%)の人にしか役に立っていないという計算になってしまう。もちろんこれは机上論でしかなく、どれだけの人がその試験で“思い込み”をするのかは不安定であろう。ただ、少なくとも「有効率50%」という試験結果を素直に受け入れることは出来そうにない。
さて、この問題の対処策として何が考えられるだろうか。先にふれたように「信用出来る医師」であることが最もプラセボ効果を起こすならば、「信用できない謎の人」に処方してもらうという手はどうか。このアプローチは倫理的に許されそうに無いどころか、先に触れたように実際には効いているのに効いていないという思い込みが今度は生じかねない(ノシーボ効果と言う)。では、このプラセボ効果を乗り越え、真に効くものだけを医薬品として合格させ、そうでないものは却下する為の試験デザインにするにはどうしたらいいのだろうか。

その解決策というのが医薬品候補となる物質と、ニセ薬のどちらかを被験者(その病気を罹患している患者さん)に処方し、その差異を比べるというものである。現代における臨床試験のほとんどで採用されているこうした研究デザインは「二重盲検ランダム化比較試験」といわれるものであるが、かくして「The Powerful Placebo」を発表したビーチャー博士はこの研究デザイン普及の最大功労者となったのである。
なお「二重盲検」の意味であるが、医薬品候補が処方されているのか、それともニセ薬(プラセボ)が処方されているのかを被験者のみならず処方する医療スタッフ側にもわからなく(盲検化・ブラインド)しているデザインのため、この二重構造を称して「二重盲検」とされる。候補物質が処方されるのか、それともニセ薬(プラセボ)が処方されるのかは「ランダム化」して決定され、その双方の治療成績を「比較」するというのが、二重盲検ランダム化比較試験といわれるものである。
思い込みの“威力”
疑い深い読者諸氏であれば、確かに医師に言われて治ったような気がすることはあれども、それは単なる気のせいであって、プラセボ効果はこうした主観的に評価をするような例えば痛みであったり、メンタル不調の領域だけに生じるのではないかと思われるかもしれない。ところが実際に知られている研究結果には、体温、血液検査などから得られる臨床検査値が改善したものや、癌が縮小したというものまである。
特に有名なのはクレビオゼンなる、当時「奇跡の癌治療薬か」と大々的に報道されていた医薬品候補を処方したライト氏のお話であろう。悪性リンパ腫が進行していてそもそも臨床試験には組み入れない予定であったというライト氏は、運良く(?)クレビオゼンの処方例となり大いなる期待に満ちた報道とともにみるみる回復し、腫瘍そのものもかなり縮小したという。ところが、「期待していたほどではない」という報道が広まると氏の腫瘍は元通りに大きくなった。そこで医師らは氏の思い込み、プラセボ効果に期待し「さらにパワーアップしたクレビオゼンが届いた」として、ただの水を処方したところ、またしても腫瘍が縮小したというのである。残念ながらこのお話はハッピーエンドではない。その後、「クレビオゼンには全く効果がない」という報道をみた氏はお亡くなりになったという。
こうした事例は実はいくらでもある。何よりプラセボ効果が「単なる気のせい」で済ますことは危険であり、また別の視点からは私たち人の身体の不思議、あるいは奇跡のような潜在的治癒力を想起させる話ではないだろうか。プラセボ効果を単なる思い込みとして済ますよりも、実際に起きていることからすればむしろそれは私たちの体内に潜在的にある自然治癒力を活性化する効果とみるほうが妥当に思えてくるのである。
ニセ薬処方の倫理的側面
臨床試験の3大構成要素として(1)倫理(2)統計学(3)盲検化をあげたのであるが、この(3)が(1)とあまり相性がよくないことには多くの人が気づいていることだろう。先のヘルシンキ宣言(人間を対象とする医学研究の原則)*には「プラセボの使用」についてこれを倫理的に受け入れてよい場合の条件に関する記載がみられる。
「(前略)現時点で最善と証明されている介入手段を比較対照として試されなければならない。証明されている介入手段が存在しない場合、プラセボの使用または無介入は受け入れられる。」
つまり、既にその疾患治療に対して標準的になされている医療行為(介入手段)があるならば、新しい医薬品候補と比較する対照群はプラセボではなく、その標準治療とするのが原則であって、そういったものが無い場合に限ってはプラセボ(ニセ薬)を使用することが倫理的に許されるということである。
さらに、標準的な医療行為(介入手段)があったとしてもプラセボ投与が許される場合の記述が続く。
「説得力を有し科学的に正しい方法論上の理由により、(中略)プラセボの使用、または無介入が必要であり(中略)最善と証明されている介入手段を受けられなかった結果として、重篤もしくは不可逆的な健康被害のリスクに曝されることはないと予想される場合。」
これは純粋なる科学との折り合いに対する倫理上の配慮といえる条件であろう。先の記述は言わば「従来の治療とガチンコ勝負して勝つか負けるか」を目的としてデザインせよ、ということであるが、より純粋に新薬候補物質の有効性を定量化したいときなどには対照群としてプラセボを選びたい要求が生じる。そうであっても、プラセボ投与群の不利益が許容出来る範囲に収まらなければならない、ということである。
実際の例で考えてみよう。例えば昨今のCovid-19に対する新たなワクチンや治療薬を認可してよいかどうかの「二重盲検ランダム化比較試験」をデザインする場面を想定する。ワクチン候補の対照とすべきは、第一選択としては既に認可されているワクチンということになるが、これだと「既存のワクチンに効き目(罹患を防ぐ効果)の面で勝たなければならない」という設計で試験はデザインすることになる。しかしながら地球上でワクチンがまだまだ足りない今は、むしろプラセボと比較することで統計的に有意な差をもってして予防効果がみられたならば、やはりワクチンとして認可すべきであろう。
然るに対照群は生理食塩水等のプラセボとしたい。このとき、生理食塩水が処方された群での不利益が先に述べたヘルシンキ宣言の記述「プラセボ投与群の不利益が許容できる範囲に収まらなければならない」というわけである。これがたやすい要求ではないことに気づかれたとしたら、倫理と科学の折り合いの難しさをご理解頂けたということになる。

愛すべき(?)思い込み
「おのれ、吉良め」と赤穂浪士が討ち入りをした事案は、当時の江戸の人たちを熱狂させ、それは現代においても忠義の象徴として、己の命を省みずに行った美談とされている。私たち人類は実際に起きた出来事をそのまま認識することが苦手なようであり、しばしばそれを善いことだとか悪いことだとかと意味合いを添えて受け入れてしまう。赤穂事件ならば少なくとも「忠義」なる“正義”のエッセンスがありまだ救われるものだと思う一方で、例えば現代のストーカー事件であったり、迷惑運転であったりという事案には、被害者側の言動を加害者の方が「悪意のある行為をされた」と思い込みをしてしまうといった認知の歪み、認知バイアスがその引き金になっていることも多いという(敵意帰属バイアス)。
悪い方への思い込みはこのように救いようがないのだが、一方で恋わずらいのような思い込みは歓迎してもよい側面があるといえるだろう。「恋は盲目」という。ストーカー行為は許されることではないが、私たち人類が機械のような冷徹さでパートナーを吟味してしまったのでは子孫が産まれることなく、この“思い込み”なくしてはとっくに死滅しているのかもしれないのだから。
(了) 第11回につづく





