第3回:ワクチン接種の科学
- Erwin Brunio
- 2021年10月13日
- 読了時間: 9分
更新日:2021年12月6日
2020年12月6日
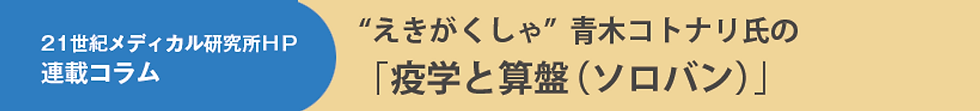

“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第3回:ワクチン接種の科学

引越しをして10ヶ月になる。埼玉県から東京都内に引っ越してきたのは勤務先が変わったからではなく、主には子供の進学が動機である。大学へ無事に進学が決まったのは良いが、キャンパスのある神奈川県に埼玉から通うには時間が掛かるうえ、通学するのに毎日通勤ラッシュに巻き込まれる子供も不憫であろうという親心といえるかもしれない。
引越の決断には迷いもあり、例えば子供を一人暮らしさせて生活費を仕送るという選択肢もあったわけで、こうした大きな意思決定の際にはプラスとマイナスとを天秤を掛けることになる。子供と私の通学・通勤時間短縮はプラス材料であるが、都内の地価は高く以前の住まいから1割ほど狭くなったというマイナス面もあった。それでも今のところ特段、後悔しているということはなく、それは事前にプラスとマイナスの要因を予め考慮して決めたから、つまり狭くなることはあらかじめ覚悟が出来ていたからでもあるのだろう。
さて、今回はワクチンのお話を取り上げる。新型コロナによる巣ごもり生活からの“生還” に恐らく最も期待されるのがワクチンの開発であろうが、期待が高まれば高まるほどリスクが見えにくくなるものである。恋は盲目、とでも言おうか。果たしてどれだけ予防効果があるのかというワクチンの“存在意義”は言うに及ばず、加えてその副反応、副作用がどの程度発生し、それはどの程度、重い症状なのだろうという点が見落とされがちになる。

社会が首を長くして待ちわびるワクチン開発がこれほどまでに時間が掛かる理由の一つもその毒性レベルの確認であって、料理のようにワクチンを「はい、出来ました」ということでそのまま市場に出すわけにはいかない。安定した品質で供給できる体制を整えることは様々な消費財共通の課題であるが、毒性の許容などという商品・サービスはワクチンや医薬品以外ではちょっと思いつかない(他にはふぐ料理、くらいだろうか)。期待と裏腹に、毒性の問題がこれまで何度となく社会問題化したという歴史が脳裏をよぎる。
ワクチンが市場に出たはいいが、例によって「こんなはずではなかった。」となりはしないだろうか。日本人は総じて心配性、リスクをとらない国民性などと揶揄されることが多く、疫学の視点で私もまた“心配性”になりかけている。
乳幼児へのワクチン接種

小さいお子さんのいる家庭であれば乳幼児への種々のワクチン接種は切実なお話であろう。産まれて2ヶ月ほどになると定期接種+オプションの形で色々な説明書が配布される。2回、3回と接種しなければならないワクチンもあるので、親御さんとしては接種のスケジュール化が結構、大変である。定期接種というのは大げさにいえば“国家的プロジェクト”であって、これは当人およびその保護者の勝手な判断で「接種しません」という訳にはいかない。何故ならば感染症というものは社会的な課題であって、当人が努力義務を怠って感染したとなれば周囲も脅威にさらされることになり、その社会的責任が問われるからである。
故に定期接種は予防接種法、という法律で規定されている*1。
予防の対象となる疾病は定期接種の対象となるものを「A類疾病」、その他、オプション(任意接種)として接種を検討するものを「B類疾病」と区分けしており、A類疾病にはジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、麻疹、風疹、日本脳炎、破傷風、結核、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児が掛かるもの)、ヒトパピローマウィルス感染症が含まれる。 インフルエンザワクチン 国内におけるインフルエンザワクチンの接種は相応の“市民権”を得たといってよいだろう。私の勤務先でも接種が推奨されている。それどころか今年は人気沸騰(?)の様子で、供給量が追いつかず誰をその投与の優先とすべきか、という国家的な議論がされている。毎年秋口になるとインフルエンザワクチンの接種推奨が報道され始め、いわば風物詩のようになった感もあるのだが、実はインフルエンザワクチンというのは毎年、その中身が変わっているのをご存じだろうか。 インフルエンザウィルスには大きくA型H1N1、A型H3N2、B型山形系統、B型宇ビクトリア系統の4種があるのだが、「今年はこれが流行しそうだ」という株をこれら4種それぞれの中から代表選手として見つくろい混合する。故にその読みがズバリであれば社会的にみても流行を抑えることに大いに貢献することになろうが、逆に外れてしまえばワクチン接種者であってもインフルエンザに罹患する人が増え、流行制御には十分な貢献が出来なくなる、という理屈になる。配合の読み次第、である。 MMRワクチン ワクチンへの希望の光に対する影と言ってよいかどうかはわからないが、病原体やその一部から病原性を弱めたり毒性を不活性化したりすることで作られる以上、どうしても毒性の問題を完全に消し去ることは出来ない。MMRワクチンは、麻疹(Measles)、おたふく風邪(Mumps)、風疹(Rubella)の予防ワクチンを3種類混合したもので、新三種混合ワクチン*2と言った方が通りがよいかもしれない。当初国内では定期接種として採用されていたのであるが、無菌性髄膜炎が多く発生したため現在では日本産のワクチンは世の中に存在していない。無菌性髄膜炎の自然発生率は数十万人に1人程度であるのに対して、MMRワクチンを接種した乳幼児のうち1200人に1人程度が発生したという。 具体的な数字として、日本薬学会のサイトでは「接種を受けた乳幼児は全国で183万1072人。厚労省によると、健康被害の救済認定を受けたのは1040人、うち3人が死亡している。(2007.1.22掲載)(2014.7.更新)」と記載されている*3。一方、海外事情は日本と異なりMMRワクチンの接種は広く当たり前に行われているようである。とある学会で伺った話では実は他国でも当初、無菌性髄膜炎のリスクが問題になったことがあったらしいのだが、以降、製法の変更などがなされこの問題が解消したという。因みにこのMMRワクチンが現在流行中の新型コロナウィルスの予防に有効ではないかという仮説もインターネット上で見つかるのだが、現時点では想像の域を出ていない。 HPVワクチン HPVワクチンに全く触れないわけにはいかないのだろう(気が重い)。子宮頸がんの発症の95%以上はヒトパピローマウィルス(HPV)に由来するのだが*4、このウィルスは誰でも生涯に一度は感染するようなありふれたウィルスである。それが長い時間を経てごくわずかな確率で発がんする人が出てくる。HPVワクチンはこの発症を抑制するものであるが、ワクチン接種後に様々な症状が報告されたため、日本では現在、その推奨は取り消されている。現在でも裁判中の案件であり、個人的な見解を述べることは差し控えるが、事実ベースとして両論を併記する意義は相応にあろうかと思う。主だった点を列挙してみよう。 (1) 複数の副作用被害を訴える声がある。HPVワクチン薬害訴訟全国弁護団による「HPVワクチン薬害訴訟 原告の声」なる文書が現在、公開されている*5 (2) 日本産科婦人科学会はHPVワクチン接種の積極的推奨の再開を国に対して強く求める声明を複数回にわたり発表して (3) 大阪大学の研究によれば、「HPVワクチン接種率の激減により将来の罹患者の増加は合計約17,000人、死亡者の増加は合計4,000人である可能性が示唆された」(2020年10月21日)*6 推奨取り消しの状況にあって国内での接種状況はわずか5%に留まるという。先進国の中で日本だけが唯一、今後も子宮頸がんの罹患率が上昇するとみられており、こうした事態を憂いている。朗報として、7月に従来よりも広い範囲のウィルスに有効なワクチン(9価HPVワクチン)が承認されたのであるが、状況が改善されることを祈るばかりである。
ベネフィット&リスク ワクチンに対して私たちの期待が高まることは必然といえるだろう。実際にワクチンによりこの地球上から根絶することが出来た感染症もあり(天然痘)、只今はポリオや麻疹もワクチンによって根絶できるのではないかという期待の声もある。新型コロナウィルスもひょっとしたらという期待をどれほど抱けるのかどうかは別として、仮に新型コロナウィルスを地球上から根絶することが出来るとするならばワクチン以外にはあり得そうにない。 一方で、これまでみてきた乳幼児への任意接種、インフルエンザワクチンの毎年の接種、HPVワクチンの接種などを自分事としてとらえたとき、果たして科学的に正しい態度で判断出来ているだろうかというと甚だ怪しいところがある。自分が病気になったときに医薬品を処方するのとは違ってワクチンはあくまで予防が目的であり、積極的に接種したくなければその理由はいくらでも見つかるだろう(面倒、お金が掛かる、副反応が怖い、痛そう)。 疫学としての狭義の立ち位置では、「是非とも接種を」というイメージがしっくりときそうだが、本コラム「疫学と算盤」としては、ワクチン接種の良いところ(ベネフィット)と悪いところ(リスク)を適切に見極め、自分の意思でこれを判断して頂きたい、が主意である。とは言っても、これを正しく見極める科学的な情報がなかなか見つからない。私の提案は、意思決定するうえで必要となる数字を公的な研究機関がワクチン接種群と非接種群とのクロス表で示す、日本としてこれをスタンダードにしてはどうか、である。具体的なイメージを表1に示す。
表 1:(おたふく風邪の予防ワクチンを想定した、仮想のデータ)

表中「無菌性髄膜炎が1200人に1人(10万人に換算すると83人)発症」という、左下の枠だけが根拠のあるデータで、他は残念ながら私の創作した数字である。こうした数字を広く国民に “見える化”させることが出来れば、我々国民の方はこの情報に加え手間や費用を鑑み自分なりに納得のいく判断が出来るようになるだろう。ただし、こうした数字を適切に示すことが出来る研究を行うには疫学専門のスキルが必須であり、また研究コストも掛かることから易しい課題ではない。具体的な研究の方法論に関するお話は何れまた取り上げたいと思っている。
ワクチン接種に際してはいたずらにノーリスクを前提とする態度も、一方で不必要に毒性を恐れる態度も適切ではないだろう。国家レベルで社会システムを構築し、適切にベネフィットとリスクについて出来るだけエビデンス(証拠)レベルの高い情報を提示出来ないものだろうか。ただし、仮にエビデンスレベルの高い情報から接種する、しないを判断するにしてもその判断が結果的に裏目に出ることがあり得ることは踏まえておくべきである。残念な結果に帰結する可能性がゼロではないという悲しさがある。国としての金銭的な救済制度は設けられているが、死亡や障害が発生した後に時間を取り返せるものではなく、この点は人類としての、現代科学としての限界点であるといえるだろう。
ところで、子供の進学を契機とした私の引越は綿密に分析し判断したつもりではあったのだが実際のところ子供はひたすらにオンライン授業を受けるばかりで、神奈川にある大学のキャンパスへは一度も通学していない。リスクとベネフィットを網羅的に列挙したつもりになっていたが、未来を見通すというのはなかなか一筋縄ではいかないものである。
(了) 第4回につづく




