第13回:クスリが効く、ってどういうこと?
- Erwin Brunio
- 2021年10月14日
- 読了時間: 12分
更新日:2021年12月6日
2021年9月27日
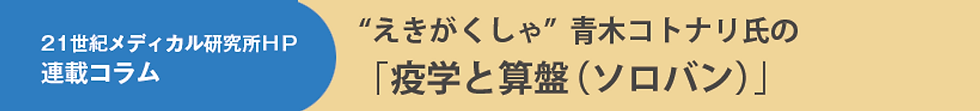

“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第13回:クスリが効く、ってどういうこと?
コラムや論説のお仕事だけではなく、学会や研修会に登壇させて頂く機会も多い。有り難いことである。基本的には自身の職務に近いところの医薬品の安全性監視や薬剤疫学、生物統計といったテーマでの講演や進行役が主なのだが、先日開催されたPharma Japan 2021*1でのセッションは社会学・哲学を主テーマとしたという意味で初めての体験であった。
主催者側から要請されたセッションタイトルは、「サイエンスの美の追求と、自由への希求」であり、さらにサブタイトル「君に患者中心主義における孤独と責任を引き受ける覚悟はあるか」と続く。何だかよくわからない。セッション開催の真意を主催者側に伺うと、どうやら昨今「患者中心」なるバズワードを良く耳にするが、それが患者さんのための話なのか、それともスマホアプリのような新機軸のビジネスチャンス、儲け話のことなのかを問い直し、少し違った切り口から眺めてみると面白いだろうということである。
セッションの中で議事進行役として展開したのが、ドイツのフランクフルト学派が唱えた「道具的理性」の概念である。「理性」が本来的に働けば「患者中心」という言葉は文字通り患者さんのためにどうするかという問いになる。一方で、道具的理性というのは部分的なところでだけ働く理性であって、これは全体をとらえたものではない。「原爆を作ることは正しいのか」とは問わずに「どうしたら原爆が作れるのか」を問う理性-。「患者中心」という言葉を前にしても、「どうやって当社の利益になるのか」という道具的理性が働いてはいないのだろうか、という訳である。
また、次いで取り上げたのは彼らフランクフルト学派が唱えた「権威主義的パーソナリティ」。人は自由を求めているようでいて実は無自覚的に権威や規制にしばられたいという性質のことである。不適切だったり古くなったりした規制や手順の修正に動けばそこには責任がのしかかってくる。周囲の賛同を得るまでは孤独でもある。一方、規制通りに仕事を進めれば批判されることは無いし責任もとらなくていい。官僚主義、前例主義は気楽で居心地がよいというのである。自由に生きていい筈なのに、権威主義とは自由であることが苦しくそこから逃げ出したくなる大衆心理、それが当時のナチズムを生んだ正体であるというのが彼らの出した答えであり、鳥が鳥かごに戻りたくなるという、「自由からの逃走」行動だ。

こうした物事の本質を問う哲学分野のようなテーマは、私たちの生活や仕事に役立たないというレッテルが貼られているようにも思える。故にこのセッションを楽しく聴講していた人がどれだけいたのかはオンライン開催でもあってよくわからないし、甚だ心許ない。ただ、ビジネスシーンにあっても、新たな道を切り開きたい、イノベーションを起こしたいのに壁にぶつかってしまうと悩む人にとって、こうした知見はその突破口を開くヒントとして案外と役に立つところもあっただろう。
クスリの有効性
さて、今回は「クスリが効くって、そもそもどういうことだろう」という、クスリの存在意義、本質的なところを立ち返って考えてみたい。「効く」とは有効性のことである。有効性のないクスリはこの世に存在する理由がない。今さらこんな話をしてもどうだろうと思われるかもしれないのだが、万国共通認識のようにも思われる有効性なる概念は、実は疾患領域が違うと意味合いがかなり違うことがあり、ここを抑えておくことが研究をデザインするうえでの肝でもある。 さらには、クスリなるものの価値を正しく見積もる意味でも有意義なことに思える。私たちの日常では500円のランチよりも3000円のランチが、1泊1万円の施設よりも10万円の施設の方が価値があるといったように、その価値は比較的金額換算できるものが多い。しかしながら経済的視点は必ずしもクスリの正しい価値を計る指標にはならないだろう(製薬企業の経営目線はともかくとして)。クスリが効くとは何かということを突き詰めることで、経済的視点ではない、本来的なクスリなるものの価値を正しく見積もることが出来るようになると思えるのである。
(1)感染症治療薬の有効性
コロナ禍における巣ごもり生活の出口は一体、いつ頃になるのだろうか。ここにきてワクチンだけではなく、治療薬も次々に出始めてきており、これらが有効打となればどうにか長いトンネルの先が見えてきそうだ。ところで、「感染症治療薬が効く」とはどういうことだろうか。体調不良を引き起こす原因となる体内のウイルスや菌が全て死滅するか不活性化することと同値でとらえることも出来そうであるし、あるいは体調が元通りになるということをもってして、菌やウイルス量がどうであろうが関係なく「クスリが効いた」と表現することも出来そうである。どちらが正しいのだろうか。 医薬品として認めるかどうかの臨床試験をデザインする方法論の立場に立てば、これはどちらも正しいということが出来るだろう。もちろん、それぞれに善し悪しはある。何より前者の方針で「クスリが効いた」とするには当該菌やウイルス量を測量できる科学技術の進歩を待たなければならない。つまり100年も前であればそもそも叶うことのないアプローチであり、最新の技術をもってしても測定精度の課題を完全には解消しきれていないところでもある。 一方で後者のアプローチは患者さんに問うより仕方なく、そこには思い込みややせ我慢、コミュニケーション能力(赤ちゃんや認知症の患者さん等)などのフィルターが正しく機能しなければならない。ただ、「効く」の哲学的な本質はその人にとって「役立つ」ことでもあり、インベーダーゲームのようにインベーダー(ウイルス)がいくつ死滅したかをもって「効く」指標とするよりも、本質的をとらえるならば後者の方に理があるといえるだろう。
(2)生活習慣病治療薬の有効性
糖尿病・脂質異常症・高血圧・高尿酸血症など、生活習慣が発生原因に深く関与していると考えられる疾患の総称が生活習慣病である*2。このカテゴリーの“病気”においてはそれそのものが直接の死因にはならず、こうした身体の状態が長く続くことによって引き起こされる心不全や腎不全、虚血性心疾患といった、直接、命に関わる病気の引き金となるいわば“予備軍”である。然るに「生活習慣病治療薬が効く、とはどういうことか」と問えば、これは感染症治療薬とは様子が違っており、病気予防に貢献する、その意味ではワクチンにも近しい、予防薬的な色合いがある。 高血圧治療薬を例にとってみると、最近では「血圧をコントロールする」といったトクホ(特定保健用食品)のコマーシャルもしばしば目にするようになり、これは高血圧治療薬と同じ目的を果たそうとしているようにもみえる。また、最近ではスマホアプリに代表される生活の“行動変容”を促すタイプのアプリが、実際に生活習慣病を防止する効果を出す可能性がハッキリと見えてきたこともあり、日本でも治療用としてこれから種々のアプリが医療機器認可を受けることになるだろう。

一方、医薬品に目を向けると、生活習慣病治療薬の市場はそもそも大きく、特に高血圧治療薬分野においてはその「高血圧」なる“病気”の定義がしばしば変更されることから、「製薬企業は病気を開発している」と揶揄されてしまうことがある。確かに、収縮期血圧の目標値が1987年の180mmHg以下であったものが、2004年には140mmHg以下に、2008年には130mmHg以下と立て続けに変更されたことなどをみると*3、実際に高血圧治療薬市場は大きくなっている。 もちろん、健康リスクに対する科学的知見を根拠に目標血圧値は変更されているのであり、このような批判は決して的を射たモノではないのだが、正直に言えばこうした皮肉に共感できなくもない。医薬品の製造販売業は同じ行動をしているのに解釈の仕方によって、ときに「命の恩人」ときに「死の商人」と、評価の振り幅が激しく因果な商売である。何より製薬企業の、経済の論理からすれば感染症治療薬や抗がん剤との大きな違いは「敵を退治する」目的のものではない故、「ずっと装備する」、永続的な処方が前提となる意味において経営の安定に資する疾患市場という見方が出来る
(3) 抗がん剤の有効性
一世代、二世代ほど前の抗がん剤において「抗がん剤が効く」とは、「がん細胞の縮小」のことを指していたといってよいだろう。今からみれば不満足な有効率しかなかったこの領域において、当時「がん細胞を退治する」ことは、残念ながら周囲の正常細胞にも少なからぬ危害がおよぶアプローチであった。これはテロの基地を攻撃する際の近隣住民の安全性確保が危ぶまれることにも似ている。 抗がん剤分野における治療薬の進歩はめざましく、もはや「がん=不治の病」という図式は少なくとも一部の領域においては完全に無くなっている。感染症治療薬と同様に、敵といってもここでは菌やウイルスではなくがん細胞―を退治することを目的とはしているものの、「敵との共存・共生」に寛容なところもある。敵(がん細胞)を完全に死滅させるのではなく、体内にがん細胞が残るとしても、その増殖を避けたり、他の臓器に転移することを防いだりといった方策をとりながら、その人の人生に悪い影響をもたらさないようにするというのが現代版の「抗がん剤が効く」という意味として解釈されるだろう。敵の退治と共存・共生の2系統の戦略があり、その意味においては慢性治療薬における「装備する」色合いもあって、「効く」ことの意味合いは両疾患領域の中間くらいであろうか。 打ち手が「退治」一辺倒ではない故に、旧来のような「がん細胞の縮小」は主たる目的とはなり得ない。前述の通り、クスリの本質が患者さんに役立つものだという視点に立って抗がん剤の有効性を評価するには、「その患者さんがその後、何年生存したか」という視点と、「病態が安定して生活の質が保たれている期間がどれくらいか」という視点の双方がある。 有効性の測定指標については次回に詳しく取り上げようと思うが、前者を測る指標を全生存期間(OS、Overall Survival)、後者を測る指標を無増悪生存期間(PFS、Progression-Free Survival)と呼称する。どちらかといえばOSの方がスンナリと「クスリが効いた」という価値観と一致しそうなのだが、医薬品なる特異な商品の場合はまた厄介な難題もあり、実際的にはPFSの方が重宝されているといえるかもしれない。 先に述べた通り一部のがん領域においては有効性向上の進歩がめざましく、患者さんが何年生存したかを観察する研究デザインとしたのでは、その観察に要する年月があまりにも長い。結果として優れたクスリが世に出てくるタイミングを遅らせてしまったのでは本末転倒だろう。故にOSにおけるエンドポイント(患者さんの死亡)を待つよりもPFSにおけるエンドポイント(死亡または腫瘍の増大)を用いて「効く」を判定するという“ご都合主義”も、良いクスリをいち早く世に出すためにという意味では歓迎されるところである。 実際のところは抗がん剤の臨床試験では双方を指標とする場合がほとんどであり、要するにどちらを主役にするかということが検討材料となる。OSを主とするのか、それともPFSを主とするのか。“主審”に選ばれるとそれはプライマリー・エンドポイント、残念ながら“副審”となった方はセカンダリー・エンドポイントと呼称する。ただし、本質的な意味ではOSの延長こそが治療の目的に合致するため、主審・副審の選抜とは別にPFSの方はOSの代用品ということでサロゲート(代替)・エンドポイントという“称号”も持ち合わせている。
有効性と有用性
有効性と有用性は私たちの日常使いの中では特に意識されずに使われており、しばしば混乱が見られることもある。しかしながら、医療やクスリの世界にあってその定義はハッキリと区別される。クスリにはときに有効性と肩を並べるほどに気になる副作用リスクの課題があり、「このクスリは有用だろうか」と問うならば「有用性=有効性+安全性(+その他)」という方程式となる。 安全性という言葉も広い概念ではあるが、ここでいうところの安全性とはほぼ副作用リスクのことだけを指しているとみて差し支えないだろう。他の心配事や悩み事、トラブル一般は「+その他」として整理される。具体的には飲み間違い、過量投与、適応外処方、異物の混入、他のクスリとの飲み合わせによる心配事等々。さらにはクスリの有用性を語るには日本が皆保険制度であることからあまり意識されないことが多いが、お金の心配も重要である。 また、同じ効き目であっても週に1回通院しなければならない治療よりは、月に1回の通院の方がありがたいだろうし、注射剤よりも錠剤、飲み薬の方が一般的には嬉しい。1ヶ月早く仕事復帰できれば生活費によい影響をもたらすだろう。こうした有効性や安全性とは別の側面の諸々が「その他」として整理される。 薬事行政の変化として印象深いのは、国際的に合意され運用されていた定期的安全性最新報告書(PSUR、Periodic Safety Update Report)が、平成25年に定期的ベネフィット・リスク評価報告(PBRER、Periodic Benefit Risk Evaluation Report)に差し替わったことである*4。特にこの時期には頻繁にベネフィット・リスク評価の議論が盛んに行われており、これがいわば「有用性」と翻訳されるような複合概念である。 最近はこうした議論には落ち着きがみられており、先の「有用性=有効性+安全性+その他」なる方程式にあっても、些細なものは検討の遡上にはあげないこと、また薬価の違いなど経済的なことはベネフィット・リスク評価とは別モノとして扱うことなどが合意されている。とはいえ、ベネフィット・リスク評価の歴史は浅く、まだまだ万国共通認識がされている概念であるとは言い難い。
哲学病?!
「クスリとは何か」「クスリの存在意義とは」といった哲学的なお話をすると、煙たがられること請け合いである。それでもやはりこうした本質に立ち返って考えてみることも大切ではないだろうか。

さて、哲学者の永井均先生(日本大学)によると哲学者というのは「他に例のないほどの重病人」だそうで、一般の私たちが何となくやり過ごせる日常の出来事にいちいちつまずく特性があるらしい。例えば誰かの手を汚して殺傷させた牛・豚・魚などを喜んで食しながら、一方の手では飼い猫の頭をなでることの悪魔性。ペットショップでかわいい犬が売られていく一方で、売れ残る犬の行く末の悲劇を気にとめない鈍感性、、、。
我が家では猫や犬を飼ったことはないが、海辺で捕まえたカニを飼ったりしたことはある。先日、亡くなったカニは我が家に来てから年ほどは元気で生きていた。一方でもちろん、食用としてのカニは大好物だ。どうやら私の哲学病は軽症のようである。
(了) 第14回につづく




