第8回:確からしさを考える
- Erwin Brunio
- 2021年10月14日
- 読了時間: 11分
更新日:2021年12月6日
2021年5月29日
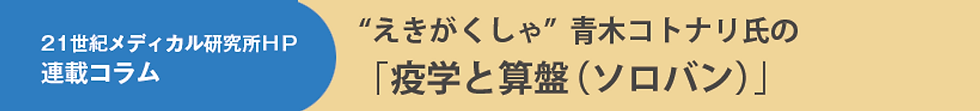

“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第8回:確からしさを考える
いわゆるマンボウ
いわゆるマンボウ。自分の勉強不足を棚に上げて言うのも何だが、初めて聞いた言葉に「いわゆる」が冠されていることに戸惑ってしまったのは、大阪で「まん延防止等重点措置」が施行されたニュースを聞いたときのことである。そもそもこのような打ち手があることもそれが緊急事態宣言とどう違うのかもよく知らない私は、少なくともこの報道機関側からみたら無知、常識知らずに分類されるということになるのだろう。
果たしてコロナの感染防止に際して行政の打ち手が一体、何種類あるのかは私には皆目見当も付かないのだが、この調子だと次は「いわゆるアンコウ」だの「いわゆるタツノオトシゴ」だの、新手の打ち手が登場してくるのかもしれない。
冗談はさておき、こうした打ち手の施行に際しては、いかなる打ち手を繰り出そうがとにかく反射的に異論を唱えるという人たちが一定数いるようだ。もちろん、自由主義国家にあって色んな意見を自由に発話できることは何より有り難いことではあるし、意見を発出すること自体は何も悪いことではない。
しかしながらどうにもそれが科学な色彩を全くまとっておらず、単なる持論、思い込み、当該の政治家嫌いに起因する感情的な反論に感じられることがしばしばあり、日本全体としての科学的リテラシーの低さと、それに起因する社会的分断が広がってきていることをとても悲しく感じている。
そんな中、海外の人の入国制限を決定した事案について「エビデンスは有るのですか?」「科学的根拠は?」と質問した野党議員の発言は、有名な医学研究者による「初めてのことにエビデンス等は無い。待っていたら手遅れになる」という発言と相まってネット上では「論破」されたことになっている。
確かに、「とにかく反射的に異論を唱える」姿勢に疲弊していた人にしてみれば、ケチの付け方が間違っているということで溜飲を下げた人も多かったかもしれない。ただ、「とにかくケチをつける」という姿勢が疑われたとしたら、これは確かに適切性に欠く態度だろうが、「科学的根拠は有るのか」と問うこと自体は間違った姿勢だとは私には思えない。むしろ「初めてのことにエビデンス等は無い」という表現の方には少々、言葉足らずの響きがあるようにも感じられる。これは今回取り上げる「確からしさ」というテーマと密接に関わってくるところでもある。
あわて者の誤り
政治に限らず白黒、勝ち負けをカッチリと決断しなければならない事案は、とかく科学と相性が悪い。何より科学というものは往々にして実験等を幾度も幾度も繰り返していくことでその確からしさがどんどん濃くなったり、あるいは薄くなったりといったように濃淡、グラデーションがあるもので、これは確証(性)の原理という。
その中にあって、特に即決しなければならない事案というのは、それがかなり不明瞭な中でなさなければならないため、「あわて者の誤り」をしてしまう可能性がどうしても高くなってしまう。今回のコロナ感染を防ぐことは、例えば感染者ゼロだけを目標にしてよければまた話は違うが、一方で社会生活、経済活動を相応に継続させなければならないという側面との折り合いも課題である。故にいかなる対策を決定しようが逆の立場から容易に反論することが出来る。
同様な構図は司法にもみられ、「疑わしきは罰せず」という原則はあるものの、実際のところはそればかりを踏襲したのでは真犯人を取り逃がす可能性が増大してしまう。一方で冤罪ゼロはもちろん必達の要求ではあるものの、かといって本当に「99%クロ」のような事案についても無罪として良いかは議論が分かれるのではないだろうか。
前回まで眺めてきた医薬品やワクチンについても副作用ゼロ、副反応ゼロを目指すことは感情的な面で大いに共感される合い言葉であろうが、一方で、では効き目を大幅に落としてまでこれを達成するのが正しいかといえばこれまた議論は分かれるだろう。特に日本は他国と比べて「ノーリスク主義」と揶揄され、元本を保証しない株式よりも利回りがかなりゼロに近くても元本が保証される定期預金のファンも多いようで、然るに前述した「あわて者の誤り」は他国以上に許して貰えそうにない。
即決せざるを得ない局面での決断者が、その判断が裏目の結果となったとき、必要以上にその責任を問われてしまうというニュースをしばしば見かける。これでは何も手を打たない政治家が最も政治生命を延ばしてしまうようにも思えてしまう。
ぼんやり者の誤り
「あわて者の誤り」の反意語は「ぼんやり者の誤り」である。無論、これは辞書に載っている話ではなく、統計学の世界の話である。統計用語における第一種の過誤というのが、「αエラー(アルファーエラー)」であって、これが現実社会ではまさに慌て者がよくやるタイプの失態と一致している一方で、第二種の過誤「βエラー(ベーターエラー)」はぼんやり者が時折やってしまう失態と一致している。誰が名づけたか知らないのだが、「A(ア)」の字を使った「あわて者」、「B」の字を使った「ぼんやり者」は見事な語呂合わせで、この語呂合わせの秀逸さは「1192(イイクニ)作ろう、鎌倉幕府」の比ではないだろう。
然るに、前述の決して「あわて者の誤り」を犯さない「何も手を打たない政治家」とはつまり「ぼんやり者の誤り」を常に犯しているともいえよう。また、どちらのミスを犯しやすいかは人それぞれの特性があって、勢いで結婚してしまうとか、焦って高級マンションを購入するといったタイプの人は恐らく、その逆に婚期を逸するとか、もっと良い物件がでるかもしれぬとずっと賃貸暮らしをするというエラーは起こさないだろう。

ビジネスシーンにおいてはビジネスチャンスを的確にとらえるスタートアップ企業などは大いに「あわて者の誤り」に対して寛大である一方で、チャンスを逸してしまう「ぼんやり者の誤り」には決して寛大には成り得ない。私はあいにく(?)比較的大企業に勤めているので、何をするにもどの部署に話を通しただとか、どの会議とどの会議に付議をしなければならぬといった手順が身体中に染みこんでいて、結果的には先の政治家よろしく「ぼんやり者の誤り」を頻発している。
もちろん多くの部署の目が入るということは、スタートアップと比して「あわて者の誤り」について起こしようが無さそうであるという利点は確かにある。しかしながら技術革新のスピードが速い現代にあって「あわて者のミスは決して許さない」のでは機を逸することと同値でもあり、激烈な国際競争の最中にあって生き残れるのだろうかと心配になったりもしている。図体の大きい組織は大企業病なる病に侵されていると揶揄されたりもする。
ワクチン・医薬品の「確からしさ」
さて、先回はクスリが効くということをどのように確かめたらいいのか、という課題を考えていたところであった。もちろん、前回紹介したように動物実験から始まって、フェーズ1~3とヒトへの投与をして確かめるのであるから、それで話は済んだだろうと思われるかもしれないのだが、それはあくまで手続きの話でしかない。「確かめるとはどういうことか」の本質を哲学的に考えることは、実のところ私たちの命にも大いに関わる話である。
では何故、命に関わると言えるのだろうか。医薬品にせよワクチンにせよ、それを国として承認してよいかどうかの白黒を判定しなければならない。ザックリいえば「効くことが確認できていない」ならば未だ承認することは出来ないし、「効くことが確認できた」ならば一刻も早く承認すべきだろうことは異論が無いだろう。
然るに、何をもってして「確認できた」とするかによっては我々が切望するワクチンやコロナの治療薬が承認される時期に関わる話で、遅くなった場合には「承認されなかったために失う命」がある。一方で確認が不十分であるにも関わらず承認してしまい、結果として看過できない程の副反応、副作用による重篤な被害がもたらされ、最悪の場合は「承認されたために失う命」がある。
つまり「効くことを確認する」行為は尊い命と密接に関わる一大事なのだ。ここまでみてきたように、「あわて者の誤り」を必要以上に恐れてしまっては、許容出来ないレベルの「ぼんやり者の誤り」、つまりは他国が承認したにも関わらずいつまで経っても日本では承認されないという誤り、エラーが増長してしまう。かといって「あわて者の誤り」を許してくれるかといえば、前述したようにノーリスク主義の国民が結果として副作用被害をもたらしたニュースを耳にしたら、大炎上、承認を決断した責任者は極悪人の如くに断罪されかねない。
ではどうするのがよいか、実際のシーンで妥当解を考えてみよう。前回紹介したCOVID-19ワクチン候補の有効性が全体としては95.0%であるのに、アジア系に限定すると74.6%であったという数字は日本人としては気になるところである。簡単に言えばこの結果をもってして日本で承認するうえで効くことが「確認された」と言えるのか、それとも言えないのか。
普段から「日本人で効くことを確認しなければ」という視点は医薬品を承認する際のほぼ必須要件的である我が国にあっては、この報告書だけで国内承認を了解するというのは到底、許容できない「あわて者の誤り」リスクを含んでいるようにもみえる。ただ、確かに日本人で効くことを確認しなければという意見には全く賛成なのであるが、その確認をどの程度まで完了しなければ承認できないだろうかといえば、非常事態の今は「あわて者の誤り」に平生よりも寛大である方がより妥当な判断ではないだろうか。
実はこの74.6%には“オチ”があって、何よりアジア人のプラセボ(ニセ薬の投与)群は809人と、それなりの人数を観察してはいるものの、その中での疾病発生はわずか4人でしかない。つまり「本剤群」がこのプラセボ群の治療成績に対して全体の95.0%並みかそれ以上の成績となるには、被験者815人のうち1人も疾病が発症しないという結果しかないことになる。実際には1例発生したのでそこで得られた(4人を1人に減らした)74.6%という数字は、統計学、確率論の世界では95.0%との表面上の差異ほどにはセンセーショナルなものではない。
然るに「815人+809人」を確認しただけではアジア人の観察が足りないとして更に観察数を増やすよりも、日本でもいち早く承認し日本人ではどうかという宿題はそのワクチンが市場に出回ってから確認する、というのが非常事態下の最適解に思えてくる。もちろんこれは何ら承認申請に際して権限も責任もない私の個人的な意見でしかなく、その判断ということを切り取るならば少なくとも科学が白黒を付けてくれているわけでは決してない。やはり決断というものは科学とは相性が良くないようで、つまりは「確認された」という言葉を「科学的に確認された/されていない」「エビデンスが得られた/得られていない」と表現したところで、そこには曖昧さが混ざる。科学は大抵、白黒の判定まではやってくれないのである。
白と黒
帰納法という言葉をご存じだろうか。我々は何度も何度もスワン(白鳥)を見る機会があり、その姿は常に白く美しく、これが繰り返されることで「スワンは白い」ことを確証する。実験や観察においても前述した通りに幾つもの類似案件が累積されることでその確からしさが色濃くなる。こうしたアプローチを科学の用語では帰納法というのであるが、一方で「帰納法では証明(エビデンスを得ること)が出来ない」ことも知られている。実際に黒色のスワンがオーストラリアで発見されたことはこれを象徴する出来事であったという史実がある。

他方、水が100度で沸騰することもしばらくは確固たる「エビデンス」であった時代もあったようだが、その後に高地では少しばかり低い温度で沸騰することが新たなエビデンスとして差し替えられている。科学的という言葉に私たちは直感的に「100%正しいことが証明されたこと」という受け止め方をしがちであるが、哲学者カール・ポパーはむしろ「反証できる可能性がある」ことこそが科学であるとした。ただし、それは残念なレッテルというよりもむしろ曖昧な表現のままでは反証することすら出来ないのであるからして、故に表現の仕方が明瞭で反証できる素地があるという科学の表現は誠実だ、というエールの色合いが濃いのである。
意思決定は常に白黒を付けなければならない。科学はその確度を十分に高めるには、あるいはその“エビデンス”を否決するには、かつてニュートン力学を相対性理論が否定したように時には何百年、何千年もの歳月が必要なこともある。然るに意思決定は「あわて者の誤りとぼんやり者の誤りをそれぞれどの程度、許容するのか」ということに帰結する。行政の判断について自身の意見と大きく異なったときに私たちは自分の考えこそが正しく、行政の考え、判断は間違っているとしばしば確信する。
しかしながらどうだろう、果たしてそれほどまでに自分の考えが正しいという科学的根拠はどの程度のものなのだろうか。ただ単に思い込みや個人的な損得勘定によるということではないと言い切れるだろうか。もちろん、自分の意見を表明すること自体はむしろ歓迎すべきことだろう。ただし、くれぐれもそれは感情と抱き合わせるのではなく、あくまで一意見として表出することを流儀として守りたいものである。
こうしてみてくると冒頭に述べた「エビデンスはあるのか」は、恐らく「エビデンスレベルはどの程度か」という問いに差し替えた方が妥当だろう。そうであれば、人の往来を制限することで感染症の拡大を相応に制御できたという、過去の歴史や海外での事例が全く無いことではないため「それなりには有る」と答えることが出来る。
この状況をもってして、確かに現代日本における実績が無いからといってつまりエビデンスが無いというのでは、些か説明不足、言葉足らずの感が否めない。科学的根拠には濃淡があるのが常であって、白鳥と黒鳥を見分けることとは話が違うのである。
(了) 第9回につづく




