第6回:クスリの科学(3)クスリの今
- 2021年10月14日
- 読了時間: 10分
更新日:2021年12月6日
2021年3月11日
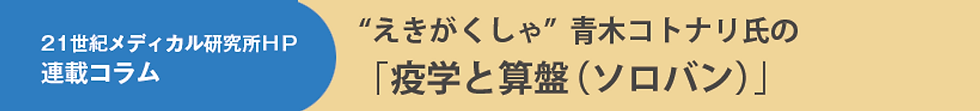

“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム
「疫学と算盤(ソロバン)」 第6回:クスリの科学(3)クスリの今
サイエンス・フィクション
先回、本コラムに登場してもらったウルトラマンや仮面ライダーだけではなく、漫画「ドラえもん」もまた、新作映画が度々上映されるなどその人気は衰えることがない。作者である藤子・F・不二雄さんはその「ドラえもん」や「キテレツ大百科」についてSF作品、つまりサイエンス・フィクションとしてカテゴライズされることを好まず、自身のSF作品のことを「すこし・不思議」として解釈していたそうである。
氏の予言通り、ということでもないのだろうが、ドラえもんに登場する発明品の中で幾つかは現代の科学技術によって実現しているものも多くある。多言語変換する「ほんやくコンニャク」や腕力・筋力の不足を補う「スーパー手袋」、自身そっくりの銅像を作れる「そっくり銅像キット」など、もう少しばかり時代が進めば「そんなに不思議ではない」となりそうである(順に翻訳機、ロボットスーツ、3Dプリンタが該当しそうである)。
中でも極めつきは「糸なし糸電話」であろうか。通話機の携帯化が社会実装された今ではもしかしたら本作品の登場する回はお蔵入りしてしまっているかもしれない。藤子さんご自身も恐らくは作品に登場する幾つかは実現されることを想像されていたようにも思え、だからこそフィクションにカテゴライズされることをヨシとはしなかったのかもしれない。
今回はクスリの現在地点について取り上げてみたい。のび太くんはドラえもんの連載が始まった昭和45年に小学校1年生~6年生という想定である(各々の学年別にドラえもんは別作品が雑誌に掲載されている)。のび太くんが大人になって久しい現代社会において、小学生時代ののび太くんからみたら、昨今開発された医薬品の数々は間違いなくSF、フィクションの世界でしか描くことが出来なかったようなものばかりとなっている。
作用機序の“獲得”
これまでみてきた通り、クスリの“創世記”はアヘンがケシから採取されたように、「薬草探し」からクスリの候補を見つけるアプローチが採られてていた。日本でも推古天皇による「薬狩り(くすりがり)」なるイベントが定期的に行われていたという記録が日本書紀にあり、同時期に行われていた「鹿狩り」もまた、クスリになると信じられていた鹿の角を採取する目的であったそうである。

しかしながら現代においてはこのようなアプローチが創薬活動として行われることは無く、近代以降では前回紹介したエールリッヒ博士による人工的な化学合成によって得られた物質をクスリ候補とするアプローチにシフトしている。これを成し遂げた主因は医学・薬学というよりはむしろ化学であって、現代の私たちの常識であるところの、分子とは原子が結合して出来ているのであって、どれとどれが化学反応すると新たに物質が構成されるかという学問が、「それはクスリの発展に寄与する」とは知らずして貢献したといえる。
加えて、前回みてきたように眼鏡職人であるヤンセン父子らがより高性能な眼鏡の延長線としてミクロの世界を覗こうと、これまた「それはクスリの発展に寄与する」とも思わずして発展した電子顕微鏡、X線検査機器、pHメーター、放射線同位体といった技術革新によって「どうしてそのクスリは効くのか」、論理的に理解出来るようになってきたのである。
この「どうしてそのクスリは効くのか」というメカニズムのことを薬学では作用機序(さようきじょ、mechanisim of action、MOA)というのだが、効き目のメカニズムを明らかにすることが出来るようになったことは、それまでの言わば下手な鉄砲とは進歩のスピードが全く違ってくることは想像に難くないだろう。例えばアヘンの効き目は紀元前より知られていたものの、その「どうして」は1970年代まで謎であり、然るに第二、第三のクスリを自然界から探し出そうとするのは天文学的な効率の悪さであったことだろう。
因みにアヘン(の主成分であるモルヒネ)が身体に作用するのは、外傷やストレスを受けたときに放出されるエンドルフィンの先頭部分に偶然、よく似た構造をしていたからである。エンドルフィンに代わってその受容体と結合することでアヘンを身体の中に入れた人は概して満足感・達成感によく似た心持ちとなる、といったメカニズムである。
“代用品”としての生物学的製剤
物質が身体の中でどのような所作をするのかがわかれば、クスリ作りの研究者には最大の恩恵となる。何だかわからず様々な物質を身体の中に入れてみることとは大違いであり、以降、様々な“革命的”医薬品が市場に次々と登場するようになった。「生物学的製剤」の登場もその中の一つである。
生物学的製剤の製法は化学合成とは異なり、遺伝子組み換えや細胞培養といった技術を用いるもので、バイオテクノロジー応用医薬品、もっと簡単にバイオ医薬品とも呼称する。その始まりは簡単にいえば「身体の中に通常存在するものが欠品してしまうのでその代用品」としてクスリの開発が始まっており、その初期を代表するものはインスリンであろう。我々は通常、健常であれば血糖値を自己調整する能力があり、その主役であるインスリンは膵臓で作られる。これがうまく働かなくなってしまうと糖尿病ということになるため、それを補充する目的でクスリとしてのインスリンが開発された。また同様に赤血球を増やすエリスロポエチンは健常であれば適量が腎臓で作られるのであるが、これが不足してしまうと血液が慢性的に不足する。エリスオポエチン製剤はいわば赤血球の代用品ということである。
「代用品」ついでに、クスリという範疇を飛び出したお話になると、ご存じの通り只今は「再生医療」への期待が高まってきており、これは不足した臓器、つまり何らかの事由でそれを失ったり、モノとしては身体の中にあるものの機能していなかったりといった臓器の代わりを人工的に作ってしまおうというものである。

こうした技術が結実すると例えば心臓や脳までもが代替できるわけで、理屈からすれば“永遠の命”への挑戦ということでもある。因みに「代用品」の概念は哲学分野の問題とも地続きであることはご存じだろうか。他人の血液を輸血することを禁じている宗教もあるし、仮に血液、臓器とパーツが次から次へと差し替わっていった場合、どこまでいけばその人では無くなるのか、という問いは「テセウスの船」なるパラドックスを想起させる。
テセウスの船はこのようにして老朽化したパーツを取り替えていった場合、その老朽化パーツを使って作られる新たな船と、どちらがテセウスの船なのかというお話である。既に心臓や皮膚、顔立ちまでも技術的に差し替えが可能な今、自分が自分であることの定義が科学の進歩によって揺らぎ始めているのである。
モノクローナル抗体
さて、現代における生物学的製剤の代表選手ということでいえば、前述した補充療法にかわって抗体、特にモノクローナル抗体ということになるだろう。医薬品市場で上位ランキングされる生物学的製剤がほとんどモノクローナル抗体である。モノクローナル抗体というのは、以前にも触れた通りPCR、ゲノム編集と並んで分子生物学の3大発明の1つといわれる。
医薬品名の末尾が「マブ」と呼称されているものは「mab=Monoclonal Antibody」の省略形であり、それとすぐにわかるように命名されている(ただし、物質・成分としての名称なのでクスリの商品名ではないのだが)。モノ、つまり「単一の」抗体を「クローン」、つまり遺伝子的には全く同じものを作る。抗体というのはご存じの通りウィルスや細菌といった病気の原因となるもの、つまり抗原に対して戦う分子のことで、これは前述した「補充」的ではあるのもの、欠品や機能不全を補うというよりもむしろ「加勢」という方が近いかもしれない。
守衛の少ない城に大群(ウィルス、細菌)が襲ってきている状況にあって、モノクローナル抗体は心強い大援軍といったところだろうか。特定の抗原に限定して効果を発揮することから従来のような化学合成により作られたクスリよりも毒性、つまり副作用が起きにくいことになる。
モノクローナル抗体の製法は極めてユニークである。一例としてある種の癌に対して有効なモノクローナル抗体の作り方を見てみよう。退治したい標的のがん細胞をマウスに注射して抗体を作る。次にそのマウスの中で作られた当該のがん細胞御用達の抗体を作る細胞(B細胞)を一旦とりだすのだが、細胞は身体の中から取り出すと本来的にはすぐに複製を止めて死んでしまう。
そこで、この細胞に「無限に増え続ける能力」を付与させて融合細胞とするのだが、この「無限に増え続ける能力」をもった細胞というのは、要するにがん細胞特有の能力である。つまり正常細胞に“異常細胞”であるがん細胞の能力を合流させて、ハイブリッド細胞とするというアイデアが凄いところでまさにSFである。このハイブリドーマ技術を確立したミルスタイン博士は1984年にノーベル賞を受賞している。
クスリとするために、この融合細胞を選別し培養、増殖させることで当該のモノクローナル抗体が大量生産される。化学合成による製法と比べるとその技術は複雑であり、安定した再現は容易ではない。また化学物質ではなく細胞という、物質として不安定なものを取り扱う必要性が生じてしまう。その象徴ともいえるのが「バイオシミラー」であろうか。
医薬品の特許が切れた際には当該の製薬会社以外が同一の有効成分で医薬品を販売することが許されるのだが、こうした後発薬が「ジェネリック医薬品」と呼称される一方で、生物学的製剤の場合は全く同一のものを作ることができないため、バイオ後発薬は「シミラー(よく似ている)」ということで「バイオシミラー」と呼称される。また、形状として注射剤であること、製法のみならず品質の維持管理にもコストが掛かることから高価となりがちで、もはや社会問題化しつつある高額医療問題も引き起こしている。もちろん、それだけの効き目が期待されているからということの裏返しでもあるのだが。
未来型?!の治療戦略
前述した「再生医療」そのものはクスリでは無いのだが、関連したクスリも登場している。「再生医療等製品」なるワードを聞いたことがあるだろうか。これは2014年から施行された薬機法、正確には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」にて新たに加えられたカテゴリである。
この医薬品では無い、クスリ(のようなもの)とは一体何だろうか。その一例としてCAR-T細胞療法を紹介しよう。これは抗体を産生する細胞(T細胞)を体内から取り出し、がん細胞と戦うCAR*能力を加えて体内へ戻す、という治療に用いられるものであり、つまり元々は患者さんご本人(の細胞)が“原材料”である。再生医療といえばiPS細胞などから物理的に網膜や鼓膜を作る技術が開発されているが、再生医療等製品はこのような再生医療そのものではない。あくまで実在する自身の細胞であって、これに病魔と闘う能力を加えるという戦略であり、具体的には細胞医薬、組織工学製品、遺伝子治療、ウィルス療法などが含まれる。
さらには光免疫療法も大いに注目されている。これは身体の外側から近赤外線光にて退治すべきがん細胞をピンポイントで死滅させる治療法である。その近赤外線に反応するInfrared(赤外線)700という化学物質を抗体によってがん細胞まで運ばせどこにがん細胞があるかを一目瞭然とすることで可能となる戦略(治療法)である。がん治療領域では従来、三大療法とカテゴリされていた(1)手術による外科治療、(2)抗がん剤による化学治療、(3)重粒子線治療や陽子線治療といった放射線治療に、(4)免疫療法が加わったばかりであるが、この光免疫療法はいわば第5のアプローチといえるだろう。

こうしたクスリやその類型は、病気や薬物治療といったメカニズムが解明されたからこそ開発出来たものであり、まさに“SF的”であるともいえよう。もちろん、それはフィクションではなく現実であるという意味でサイエンス・フィクションではないSFである。ただ、「すこし・不思議」というよりも研究者ではない私には「すごく・不思議」な世界である。
(了) 第7回につづく




