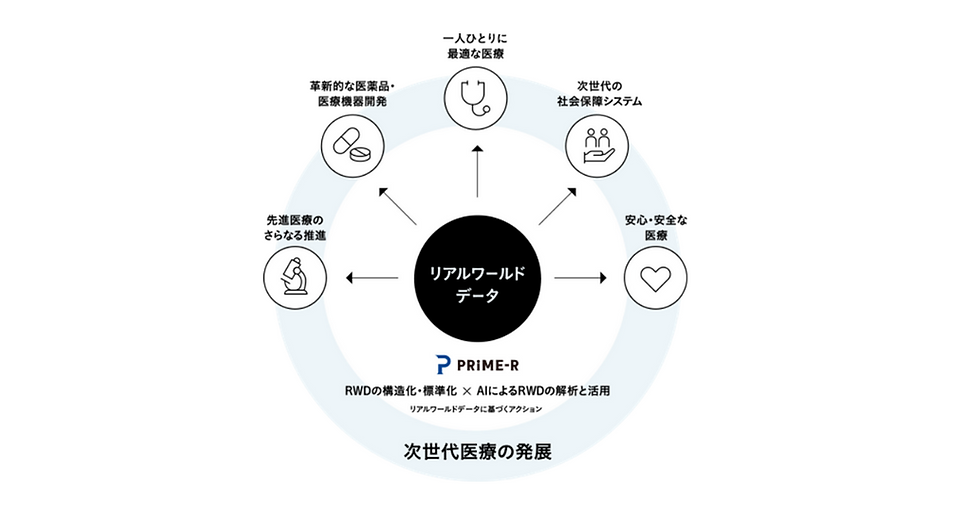スペシャルインタビュー
- 2023年2月27日
- 読了時間: 13分
更新日:2023年3月6日
「自然と人を繋ぐ。アーティスト橋本敦史に聞く」
物語は言葉を紡ぐ。彫刻は形を繋ぐ。しかし物語と彫刻が目指すものは同じ。読む人、見る人の共感と感動である。彫刻家・橋本敦史は言う。「人と自然の間にある乖離。普段は気にもしない隔たり。僕は人と自然の間に作品を置いてこの2つをつなげたい」。
この春、橋本は中国深圳のツインタワーのパブリックスペースに「MOON 深圳パブリックアートプロジェクト」と称する大型彫刻を完成させた。
スペシャルインタビュー 「自然と人を繋ぐ。アーティスト橋本敦史に聞く」は、注目を集める彫刻家・造形作家 橋本敦史の現在、彼を育んだ過去、そして目標とする未来を語ってもらった。
(聞き手:21世紀メディカル研究所代表 阪田英也
(元にっけいあーと副編集長、元日経ビジネス編集部長))

「MOON 深圳パブリックアートプロジェクト」
中国のキュレーターが惚れ込んで決めた一大アートプロジェクト
――中国・深圳で完成されたプロジェクトについてお聞かせください。
橋本:プロジェクト名は、「MOON 深圳パブリックアートプロジェクト」。3年ほど前から自分の作品を「世界に届け!」という思いで、Instagramに載せていました。そうしたら、中国のパブリックアートを制作する「Aart」という会社のキュレーターが目を留めてくれて、昨年(2022年)突然連絡が来たんです。そのキュレーターはMOMOさんといって非常に日本語が流暢でした。
突然の海外からの依頼ですので、最初は身構えました。けれどMOMOさんは僕自身や僕の作品をしっかり調べてくれていて、電話やメールで少しずつ僕から話を引き出していきました。そしてZOOM会議で面談するうちに、「深圳でこういうプロジェクトがありますが、やってみませんか」という話になりました。
誰の紹介でもなく、いわば直接発注。これまでは画廊やギャラリーが画家や彫刻家とクライアントの間に立って商談を成立させていたのが、SNSの発達で大きく変わったということです。
――完成した作品は、「Aart」が制作したプロモーション・ビデオ(本インタビュー掲載)で見ることが出来ますが、かなり大型ですね。
橋本:直径4.5mを超える作品です。最初はプロジェクトの作品サイズは分かりませんでした。「Aart」もMOMOさんも2つのタワーの間の広い空間で どのくらいのサイズにするかを測りかねていたんだと思います。
僕の作品のMOONの中で40cmくらいのものを3Dスキャンして向こうに渡し、細かい造作についてはメールと電話で要望と指示を出して進めました。もともとのMOONの材質は木材とステンレスの組み合わせなのですが、オープンエアのプロジェクトでは木材は腐る。そこで木材部分を銅に代えてステンレスとの組み合わせで作品を作りました。
作品独特の色やステンレス部分のテクスチャの表情などは、よくやってくれたと感謝しています。「Aart」は中国で巨大なオブジェなど大型のアート作品を数多く手がけています。従来のやり方は、作家を現地に呼んで作家と一緒にコミュニケーションを取って作り上げていくっていうものですが、コロナでそれができないから遠隔操作=リモートコントロールになったということなんです。
――2つのタワーを統合、融合させるようなイメージの広場に橋本作品は設置されました。ツインタワーの所有者はどのような業種なのですか。
橋本:詳しくは分からないのですが、招商局集団(しょうしょうきょくしゅうだん)という中国の巨大な企業だそうです。海運から貿易、輸出入の全域をカバーしている企業だと、「Aart」から聞いています。これまであったタワービルの対面に新しいタワーが建設されて、その間に広場が出来た。ビルの名前は「タイムタワー」で、その間を埋める広場は「時間広場」と名付けられました。
考えてみると、「時間広場」の中に「MOON(月)」を置く。広場を埋めるモニュメントとしては最適だと考えたのでしょう。
――「時間広場」の中に「MOON(月)」を置く。いいフレーズですね。でも正確な作品名は違っていますね。
橋本:ええ、正しくは「THE SUN &THE MOON」。月ばかりでなく太陽を組み合わせた作品です。先方は「月だけでなく太陽もつけたい」という感じでした。私の作品「MOON」を月と太陽というテーマに変えてくれないかといわれたんです。
既存のビルと新しいビルの対比となる。そこに時間の経過があり、時間がその土地の変遷を支配している。ツインタワーの真ん中のモニュメントはその象徴であり「時間の象徴」だと。太陽が沈んで月が出て一日が終わり、その繰り返しが続く。そういう時間の永遠性みたいな、いうなればエタニティを表現する。キュレーターのMOMOさん、そして制作会社にはそういう意図があったと思います。
この間、日夜を問わず連絡を取り合い、僕の意図と先方の希望を繰り返し議論し、作品に仕上げました。最終的には僕のコンセプトとイメージを変えることなく、「時間広場」に設置できました。
2月に入って、プロモーションビデオを見る限り作品は完成していますが、日本では恒例の作品除幕式やツインタワーのオープニングセレモニーもコロナ禍の影響で行われないようです。でも、やっぱり確認したい。この目で見たい。今年中には深圳に行こうと思っています。
橋本作品の根幹をなす「自然の力」「人間の営み」そして「永遠のとき」
――深圳プロジェクトの基盤となった作品「MOON」についてお伺いします。「MOON」を作ろうとした動機、作品に込められた思いとは。

「MOON」
橋本:月は地球の潮の満ち引きを動かしています。その満ち引きが海岸線を、海辺の景色を大きく変える。僕はサーフィンが趣味で、潮の満ち引きを実体験としてからだに感じます。そのとき自分のからだの7割が水であり、潮の満ち引きと同調することを実感します。ある時は月を綺麗と思い、ある時は不気味に感じる。月の持つ地球の自然への力、その地球の地表にいる人間への力、そして永遠に続く「時間」。これを形にして作品を見る人に僕が感じることを伝えたい。これが「MOON」をつくった原点です。
僕が考える作品づくりの基本は、「そもそもアートは自分自身とこれを取り巻く外界、つまりは自然や人間の社会をつなげるもの」ではないかということです。普段は自然や社会と人間の間に存在する境目は全く意識しない。人はそして自分は、いつも自然や社会と一体だと思っているからです。しかし人間の感情が悲しみや怒りや絶望に支配されるとその境目は忽然と現れる。そのとき分断されていることを深く思い知ることになる。であるなら、最初から境目は存在するけれど、自然や社会という外界と人間は繋がっているんだという意識を持つことで救われるのではないか。その拠り所として、繋がっていることの証明としての僕の作品、そしてアートの存在意義があるのではと思うのです。
死線を2度乗り越える。そこに脳神経外科医である父の存在が
――橋本作品には、Blood Vessel(血管)、Hemispatial agnosia(半側視空間失認)、Brainbow(神経細胞の観察手法)、Synapse(神経細胞間の接合部)など、医学とりわけ脳とその機能、構造をタイトルとする作品が多くあります。これらの着想はどこから来ているのでしょうか。
橋本:着想というより実体験からのものです。医学や医療、そして父が専門とする脳神経や血管を想起する作品づくりは、自分自身の体験が契機となっています。実は死にかけたことが2度あって、1度目は中学3年の夏です。受験勉強の合間に友達と琵琶湖に自転車で行きました。

「Blood Vessel(血管)」
琵琶湖には湖畔に浮いてるドラム缶のいかだがあって、そこに乗って釣りをして遊んでいました。そのドラム缶をつなぐ鉄パイプを渡っているときに湖に落ちて鉄パイプに腹部を強打したんです。かなりの激痛で、自分では「あばら骨を折った」と思い、自転車を手押しして30分かけて家に帰りました。
あまりの痛さで母に「すぐ寝る。明日病院へ行く」と言ったことは覚えています。布団に入って意識朦朧とする中、その日はたまたま父が早く帰ってきました。「敦史があばらが痛いと言ってる」と母に聞いて、僕を診て「すぐ検査できる病院に連れて行く」。
CTを撮ったら片方の腎臓がつぶれていました。父が早く帰って来てなかったら出血多量で死ぬところでした。大津赤十字病院のお医者さんが言うには、「お父さんが1時間でも遅かったらダメだったかもしれません」と。
――お父さんが早く帰って来なかったら彫刻家 橋本敦史は存在しなかった。
橋本:そのとおりです。父に助けられて今があると本当に思います。そして死にかけた2度目は、脳の皮質異形成というものによる症状でした。この皮質異形成が原因で2回失神しました。1回目は32歳のとき2008年のことです。車の運転中に「キーン」というすごい耳鳴りして、その後気づいたら救急車の中でした。後から聞いた話では、偶然僕の後ろにいた車が「なんか変だぞ」と僕の車に付いて来てくれた。
僕の車は僕が意識を失ったまま、ノロノロと数百メートル走りコンクリート壁にぶつかって止まったそうです。車はフロント部分が大破しエアバックが作動して怪我はしませんでしたが、大津赤十字病院に救急搬送されました。
――その事故の前の橋本作品には「Blood Vessel(血管)」に似た「TREE」という血管をモデルとした作品がありますね。
橋本:不思議ですよね。父は京都大学の脳神経外科の医者なので、その影響もあったと思うのですが、「TREE」をつくっている頃はそんなこと考えもしませんでした。1回目の失神のときには特に異常は見つからず、経過観察となりました。父の勤務する京都大学病院で精密検査して、小さな脳異形成の可能性があり、経過観察となりました。
――1回目の失神では手術することなく回復されたのですね。そして2回目は。
橋本:事故の数か月後に実家のガレージをアトリエとして作品を制作している最中に起きました。冬の寒い時期で厚着していて、トイレから出る時に上着を着ようと思ったら着れない。なんとも表現しようがないんですが、着れないんですよ。見えないでもなく、感覚がないでもなく、認識ができない。後から父に尋ねたら、私の症状はHemispatial agnosia(半側視空間失認)と説明されました。
この症状を持つ人は、例えばお弁当を渡してもその半分は食べないそうです。視覚では見えてるけど認識してないので食べないんです。実際に僕がそうなりました。そして今度はトイレから出ようとしてドアのノブが掴めない。そして出られない。そこからめまいがして意識がなくなり倒れました。幸いにも倒れた場所が実家のリビングから見える場所だったので、母が気づいて家の中に入れてくれました。実家でなく他の場所だったら凍死していたと思います。

Hemispatial agnosia (半側視空間失認)
――倒れた後、救急搬送されたのですか。
橋本:いいえ、そのときは意識を回復して検査だけを受けに行きました。翌日、体調も戻ったので、実家のガレージのアトリエで制作を再開したときのことです。昨日までの作業での進み具合が自分の考えていたよりずいぶんと進んでいる。「誰がやったんや」。不思議な感覚でした。自分がおかしくなっていることは自覚していましたから、京都大学病院で精密検査を受けました。父は脳神経外科医ですから僕の病気は守備範囲です。担当の先生に検査結果を聞いているときに父が診察室に入ってきて、MRIの画像を見て手術をすると言いました。
――そしてお父さんご自身が実の息子さんの手術をした。私は日経メディカルという医学雑誌の記者をしていたので、外科医が自分の家族の手術をするのは稀ということを知っています。お父さんはよく決断されましたね。
橋本:担当の先生は、一般的には経過観察をする、とのことでした。父は症状の原因となった責任部位を残しておけば、後々の人生に大きく影響する、と考えたのだと思います。また異形成が右頭頂葉にあり、創造性に関係している部位と考えられているので、僕のアーティストとしての将来を考え、自分の責任として自分で手術すると決断したと聞いています。その後今まで失神や症状も出ることもなく、元気に過ごしています。2度死にかけたのを2度とも父に救ってもらった。子が親から受ける恩を超えて、僕は脳外科医の父のもとに生まれて本当にラッキーだった、自分の人生を与えてくれたと思っています。
――2度の稀有な体験が彫刻家 橋本敦史を創ったのですね。作品に与えた影響についてはいかがですか。
橋本:結果的に、手術で取った組織を顕微鏡で見てはじめてわかったような、脳の小さな皮質異形成というものが僕の運命であり、その後の人生で作品のテーマを授かったと思っています。いまは、「病気してよかった」と思えるくらいです。30代の半ばぐらいで大病を経験し、その病気を乗り越え自分が作家として生きていく覚悟ができました。
また自分にとっての大きな出来事は、ある意味、気持ちの整理がついて、今まで不安だったことが不安でなくなる。実際には状況が変わらないけれど、「やれる」と思うことができるということです。
僕自身の作品コンセプトである「自然と人間を繋ぐ」ことも、以前は抽象的な思い込みだった気がします。しかし病気という実体験、死の淵を彷徨ったことでより具体性を増して作品の中に表現できるようになりました。
「自然と人間、その関わり」をテーマに、彫刻を“続け切る”
――作家としての原点をお聞きします。お父様は世界的な脳神経外科医、お母さまは若いころからアートに関わり、多くのアーティストを知人、友人にお持ちです。ご両親からのアートの触発、影響、ご自身が彫刻家を目指した経緯についてお話しいただけますか。
橋本:小さい頃はパイロットになりたかった。しかし片方の腎臓を失って諦めざるを得ませんでした。大学浪人していたとき父が親友の東京芸術大学出身の画家を紹介してくれました。ベストセラー「ゴッホの遺言」を書いた小林英樹さんです。小林さんに会うとご自分が講師をされている中之島美術学院という予備校に行くことを薦められました。そこで2年間、美術の勉強をして、毎日が楽しくてしょうがない。自分の天職がアートだと気づきました。

「FLOWER」
振り返ってみると、母は父と結婚していなければアーティストとして生きていきたかったはずと思います。いまも年中、僕と僕の作品について話をします。父も親友が小林英樹さんだったり、実は自分の家が芸術性に溢れていたんだと思います。中之島美術学院の2年間はその後の京都芸術造形大学での学びへとつながっていきます。
また、父と交流のある建築家の安藤忠雄さんに僕の作品をお見せしたところ大層気に入って下さり、ご自身が設計されたホテルのロビーに僕の作品「Blood Vessel」と「FLOWER」の2点を置いてくださいました。そのホテルは京都の任天堂旧本社の跡地に立つ「丸福楼」です。安藤さんの設計された建物に僕の作品があるということは、大きな自信と意欲に繋がっています。
――最後に今後の目標と彫刻家・橋本を取り巻くメディア、ファン、オーディエンスに何を伝えていきたいのかをお聞きします。
橋本:目標は「続けること」。芸術家は、続けることが一番困難であり「続け切る」ことが大切です。「大きな仕事をやるぞ」よりも、まず続け切ろうと。彫刻家としてとにかく歩みを止めない。
次に作品の大きなテーマは「自然と人間、その関わり」です。最近、人間が自然の一部であるということが忘れ去られているように思います。また自然との乖離がどんどん進んでいく。SDGにしてもCO2(二酸化炭素)排出量削減にしても人類の過去のツケの埋め合わせをパッチワークのようにやってるように思えます。もっとナチュラルに納得できるアプローチがないか。そういったことを真摯に考えさせ実現に近づかせる力がアートにはあるように思えます。
また、彫刻というものづくりでも、3 Dプリンタで作品を作ったり、コンピュータで図面を描いてそれがそのまま削り出されたりします。しかし人が手作りしたものと全く同じものができたとしても、何故か心がない。人が作ったものには何か“ゆらぎ”があります。機械が作ったものは綺麗に出来過ぎていて、この“ゆらぎ”がないんです。“ゆらぎ”とは「心地良い いい加減さ」。“ゆらぎ”があることが人の安心につながるのではと考えています。
(了)
橋本敦史 動画メッセージ